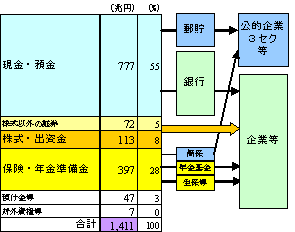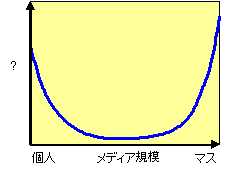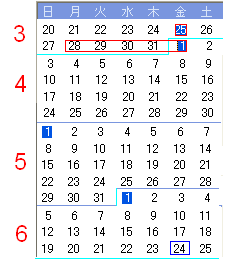(「やっぱり、磯崎はフジ派だ!」とか言われると困るのですが・・・)、
ブログ界では、かなり法律に詳しそうな方まで、「ニッポン放送の新株予約権はどう考えても有利発行で違法だ!」とおっしゃる方が非常に多いようです。
村上ファンド(株式会社M&Aコンサルティング)さんも、以下のような理由をあげて、この新株予約権の発行を危惧されてらっしゃいます。
http://www.maconsulting.co.jp/PDF/050225_PR(J).pdf
・発行済株式総数を大幅に超える多大な新株予約権を株主総会の決議なくして特定の第三者に対して安価にて発行するものであること(発表のあった23 日の終値6,800 円に対して、新株予約権の行使価格は5,950 円と時価よりも低く、新株予約権の発行価格も約336 円に過ぎない)
・新株予約権の行使により調達する資金(最大約3,000 億円)の使途が明確でなく、希薄化した株式の価値が将来的にどの様に高まるのか株主は理解できないこと
・フジテレビによる公開買付け期間中の発表であり、株価に大きな影響を与えたこと(発表のあった23 日の終値6,800 円に対して、発表後の24 日の終値は6,280 円)
まったくおっしゃるとおりですし、この新株予約権には有利発行以外の論点もいろいろありそうですので、この新株予約権の発行がOKなんてことを申し上げるつもりは全くありません。
ただ、新株予約権の条件をもう一回良く読みなおしてみると、「有利発行かどうか」という論点に絞れば、「有利発行ではない」という気がしてきました。
発行価額に影響を及ぼす主な要因
ニッポン放送のプレスリリースに書かれた新株予約権の要項のうち、有利発行に関係しそうなものをピックアップしますと、以下の通りです。
(4)新株予約権の発行価額
1 個につき3,362,731 円(1 株につき336.2731 円)
(9)新株予約権行使の際の払込金額
各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、各本新株予約権の行使により発行または交付する株式1 株当たりの払込金額5,950 円(以下「当初行使価額」といい、必要な場合、第24 項または第25 項に基づき修正または調整したものを「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた金額とし、当初は59,500,000 円とする。
(11)新株予約権の行使により発行する株式の発行価額
1 個につき62,862,731 円(1 株につき6,286.2731 円)
(ただし、第23 項および第24 項または第25 項によって変更されることがある。)
(15)行使請求期間
平成17 年3 月25 日から平成17 年6 月24 日までとする。
(17) 新株予約権の消却事由および消却条件
当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の発行日の翌日以降、当社取締役会で定める消却日に先立つ1か月以上前に、新株予約権証券を当該消却日までに当社に提出すべき旨を公告し、かつ新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に対して通知を行った上で、当該消却日に、本新株予約権1個あたり3,362,731 円にて、残存する本新株予約権の全部または一部を消却することができる。一部消却をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(18) 新株予約権の譲渡制限
本新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。
(24)行使価額の修正
平成17 年4月1日以降、毎週金曜日(以下、「決定日」という。)の翌取引日以降、行使価額は決定日まで(当日を含む。)の5 連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの5 連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値に相当する金額(円位未満小数第2 位まで算出し、その小数第2 位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。)に修正される。
なお、時価算定期間内に、行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値に調整(かかる調整は、公正で合理的なものでなければならない。)される。
5,950円で行使できるのは1ヶ月後の1週間だけ
まず誰しも、第(9)項の「新株予約権行使の際の払込金額」が5,950円なのが「カチン!」と来るわけです。直前の株価が6,800 円なのに、それより12.5%も安く(87.5%で)発行できるオプションなんてけしからん!というわけですね。
ただし、良く読むと、「(24)行使価額の修正」で、平成17 年4月1日以降、毎週月曜日に、前週金曜日までの5 連続取引日の終値の平均値に行使価格が修正されるわけです。(上限、下限無し。)
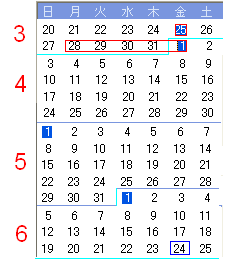
行使可能になるのが3月25日からですから、4月1日まで1週間しかありません。
つまり、5,950円で行使できるのは1週間だけです。
また、おそらく、フジテレビはこの第一週に約3,000億円もの大金を全部払い込んだりしないでしょう。(あと一ヶ月でそれだけの資金調達は無理っぽい。)
取得者側のコストで考えるとディスカウントは7.6%に過ぎない
仮に一部払い込んだとしても、先にフジテレビは1株あたり約336円を新株予約権に払っているわけです。5,950円と足すと6,286円。これは直前の終値6,800 円に対して92.4%であり、7.6%のディスカウントでしかありません。
しかも、合計6,286円で取得できるのは、発行決議の1ヶ月後の1週間だけなわけですから、それって、普通の増資(決議から2週間ちょい)よりちょっと払込までの期間が長い時価発行増資と同じとも言えます。ご案内のとおり、10%程度のディスカウントまでの増資は、判例や実務でも有利発行とはみなされてないようです。7.6%のディスカウントしかない1ヶ月先の増資は有利発行とはいいにくそうです。
2週目からのタイムバリューは相当小さい?
さらに、翌週(4月4日)からは、前週の平均「時価」でしか行使できないわけです。これ以降は、(ライブドアのMSCBとは違い)ディスカウントもついてません。つまり、翌週からのオプションバリューはほとんど無いんじゃないでしょうか。
フジテレビとしては、つまり4月4日以降は、株の取得コストは結局1株当たり「時価+336円」かかってしまうわけですね。つまり、(流動性とかマーケットインパクトを考慮しなければ)、「市場と同じ値段で株が買えるというだけの権利」に、1株あたり336円も払わせられるわけです。結果としてフジテレビとしては市場における「時価」より合計取得コストが(有利どころか逆に)高くなっちゃう・・・。
もちろん、浮動株が少ない現状では、そもそも市場で買える株数が限られるわけですが、そういう流動性リスクをオプションバリューとしてどう組み込むかですが・・・。(あまり、見たことがないですね・・・。)
しかも、(フジテレビとニッポン放送が「グル」だと考えればあまり関係ないとも言えますが)、第(17)項の発行会社のコールオプションと第(18)項の譲渡制限条項も、理論的なオプション価格を大きく下げる要因ではあります。
というわけで、このオプションって(詳細に三項ツリーモデル等で精緻な計算をするまでもなく)、「有利」と主張するのはかなり難しいと言えるんじゃないでしょうか。
(っていうか、誰か以上のような内容のこのオプションを一株当たり336円で買いたいって方、いらっしゃいますか?)
(1ヶ月後の株価にもよりますが、現時点で。)
同様に、「これを発行したおかげで株価が下がった」とか「株価を下げるためにこれを発行した」というのも厳しいかも知れないですね。純資産倍率(PBR)が1近辺の会社ですし、新株予約権だけ発行して株を発行しなかったら、一株当たりの価値は高まりこそすれ安くはならないはず。フジテレビ側は、まだ行使するどころか引き受ける旨の機関決定すらしてないわけですし。
というわけで、裁判所では、有利発行以外の論点で争われるんじゃないかと想像いたします。つまり、「安く発行はしてないかも知れないが、フジテレビに大量に新株予約権を発行するのはズルい」という主張が認められるかどうか、ではないかと。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。