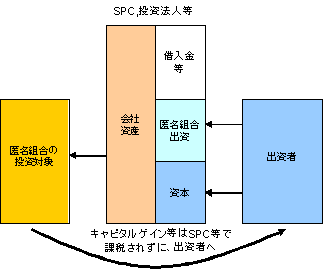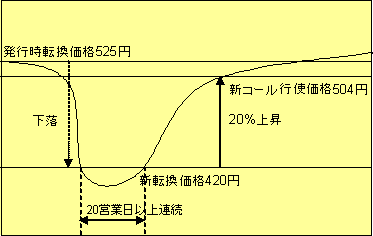krpさんが「経営・会計通信」「少数株主を追い出す(完)」で少数株主を追い出す(スクイーズ・アウト)の方法についてまとめておられます。
事後設立による検査役検査の回避の方法については、
それ以外の方式の場合は、磯崎さんはいくつか可能性を上げておられますが、私は、公認会計士や税理士による算定によるしかないと思います。
とおっしゃってます。
磯崎哲也事務所でも、事後設立の価格等の証明やっております<(_ _)> ので、わざわざ検査回避の方法を考えてビジネスチャンスを減らすこともないのですが(笑)、私は、前回ご提示した方法も場合によっては使えるのではないかという気がするのですが。
また、このロキテクノ等のスキームをもう一ひねりして、例えば完全親会社を作った後にもう一段ロキテクノが株式移転で完全親会社を作ってその株式をSPCに譲渡したらどうでしょうか?その株式はSPCが設立された後に「製造(?)」されたものなので、「(2) 成立前より存在する財産」にもあてはまらない気がしますが。
つまり、被買収法人の株式を取得後、まず下図のように完全親会社を設立するわけですが、

ここで、もいっちょ被買収法人の完全親会社を設立し、
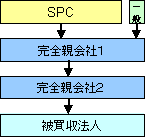
「完全親会社2」の株式をSPCに譲渡した後、
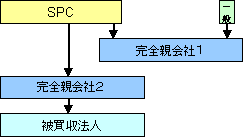
完全親会社1を清算して、少数株主のスクイーズ・アウト終了、ということになります。

会社が層に分かれて剥離していくところが、ミズクラゲの幼生(ストロビラ)がくびれて分裂していくところ(ストロビレーション)に似ていて「かわいい〜」かと。(女子高生とかに人気が出そうです。)
これを「ストロビレーション方式」(笑)と命名したいと思います。
参考URL:
信州大学教育学部生物 坂口研究室
ヒドラ・ミズクラゲ紹介:
http://biology.shinshu-u.ac.jp/sakaguchiHP/hydraframe.html
ポリプからエフィラへの変態:
http://biology.shinshu-u.ac.jp/sakaguchiHP/hydra/aurita5.html
SPCが新設法人であっても、この完全親会社2の設立日はさらにそれ以降ということになりますので、どうみてもその株式は、「SPCの設立以前には存在しなかった資産」、ということになるんではないかと思いますが、どうでしょうか?
SPCは一番最初に被買収法人の株式を取得してしてますが、これは「事業のため継続して使用する」目的ではなく、SPCの目的は完全親会社2の株式を(継続)保有することです。
「完全親会社2といっても、被買収法人と中身はほとんどいっしょじゃねーか」というツッコミもあろうかと思いますが、仮にも別法人ですので違うものですし、「加工されたものはアリ」にしていただけないと、(例えば)「資本金1千万円の法人が、会社設立前から存在する木材を使って会社設立後に製作された51万円の机を買ったら事後設立なのか?」というようなことになってしまってキリがありません。
「SPCの子会社が製造したものをSPCが保有するのはけしからん」というのであれば、SPC1、SPC2を作って、SPC1で「製造」したものをSPC2に販売して、SPC1は完全親会社1と合併した後にいっしょに清算、ということでもよろしいかと。
まあ、こうした法的な判断が定まっていないことや、休眠法人の簿外負債リスクやデューデリの手間がイヤという方は、会計士等に価格等の証明をご依頼ください。
事後設立は現物出資の検査の潜脱を防ぐための規定ですが、もともと「あんま意味ねーじゃん」という批判の強かった規定ですし、「会社法制の現代化に関する要綱試案」(7ページ下)
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI39/refer01.pdf
でも、検査役の調査制度は廃止する方向ですので、こうした証明ももうすぐ必要なくなるかと思います。
(ではでは。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。