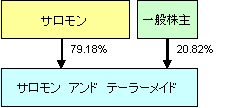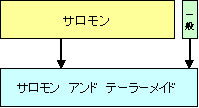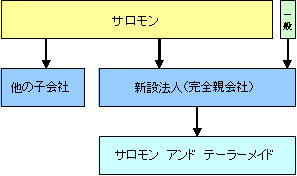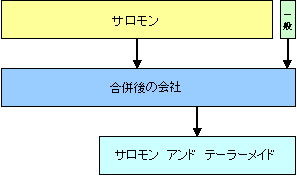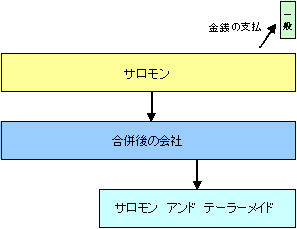本日のお題は、TOBして100%子会社化を計ろうとしたけどTOBに応じない株主が仮に残っちゃった場合にはどうやって出て行っていただこうか、というお話です。
本日、JASDAQ公開のサロモン アンド テーラーメイド株式会社のTOB(公開買付)の公告が日経に載っています。昨日の終値950円より約26%高い1株1,200円で公開している株式すべてを買い付けて上場廃止にする予定とのことで、これをお手本にさせていただきますが、まず、公告の「1.公開買付けの目的」によると、
公開買付者(注:フランス法人サロモン エス・アー)は、本公開買付けにおける目的がアディダス・サロモングループにおける戦略的経営の実現の一環として対象会社を公開買付者の100%子会社とすることにあることから、本公開買付けにより対象会社の発行済普通株式の100%を取得するに至らない場合であっても、引き続き対象会社の100%子会社化に伴う組織再編を進めていく予定です。
ということで「既存の株主は全員出て行っていただきます。(決意は固いよ。)」というところを示しつつ、以下のようなスキームで株主を「追い出す」ことを想定しています。
まず、現状は、こういった株主構成になってるわけですが、
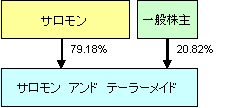
これをTOBして、全一般株主が応じればそこで100%子会社化完了です。
株主がちょっと残ってしまうとこういう形になるわけですけど、
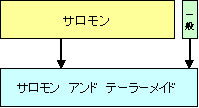
ここで、以下のように「株式移転」(商法364条)を行います。
この関係で、公開買付者は、本公開買付けの実施後、株式移転により対象会社の全株式を所有する完全親会社を設立し、
で、こうなるわけですが、
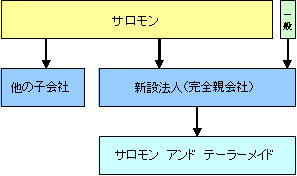
完全親会社をアディダス・サロモングループの他の100%子会社に吸収合併させることを検討しています。
ということで、さらに、こうなります。
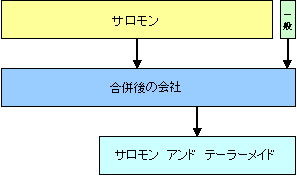
この場合、株式移転により、それまでの対象会社の株式は完全親会社に移転し、対象会社の株主に対しては特定の移転比率に応じた完全親会社の株式が割り当てられ、従来の対象会社の株主は完全親会社の株主となります。株式移転が行われた場合には、日本証券業協会の店頭売買有価証券の登録等に関する規則に従って対象会社の株券は店頭登録が取り消され、対象会社の株式は株式店頭市場において取引ができなくなり、これを将来売却することが困難になることが予想されます。
なお、公開買付者は、完全親会社の株式を店頭登録又は上場することを検討しておりません。
ということで、「TOBに応じなかった場合は、どうにもなりまへんで。」と言っておいて、トドメで、
また、その後の合併において、完全親会社の株主で存続会社の株式の1株未満を割り当てられる株主には、商法の規定に従って金銭が交付されることになります。この場合に交付される当該金銭の額は、本公開買付けにおける買付価格と異なる可能性があります。
といってます。
(ここが最大のポイントですが)、サロモン アンド テーラーメイドの現在の発行済株式数は15,510,000株ですが、例えば、残った最大の株主が10,000株保有しているとし、株式移転でも同じ株数だけ株式が発行されて、合併する他の100%子会社が155株しか発行していなくて、被合併会社の株式10万株に対して合併会社の株式1株が割り当てる吸収合併を行うとすると、合併後の会社の株式数は155+155=310株で、残った最大の株主の株式は0.1株分の「端株」になってしまいます。
この端株を金銭で買い取ってしまい、100%子会社化を達成しようということだと考えられます。
こういうのを「squeeze out (merger)」といいます。
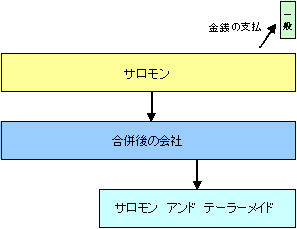
(本日はこのへんで。)
参考URL等
「会社法制の現代化に関する要綱試案」に対する意見(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e40106bj.pdf
我が国経済の活性化には企業再生ファンド等による再生は非常に重要であるためある株主(支配株主)が少数株主に対し株式の売り渡しを請求できる権利を認める制度(スクイーズ・アウト)を設けるべきである。
「デットとエクイティに関する法原理についての研究会」報告書(日本銀行金融研究所)
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2001/kk20-3-1.pdf
株主間の利害対立に関する典型的な問題としては、「多数派株主が、株主総会における議決権等法律上与えられた権限を利用して、少数派株主を会社から追い出す」という、いわゆるスクイーズ・アウト(squeeze-out)と呼ばれる問題がある。
「世界から見た日本のプライベートエクイティ」ウォーバーグ・ピンカス・ジャパン マネージングディレクター深川哲也氏 (独立行政法人経済産業研究所)
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/03061301.html
第4に、少数株主の扱いです。米国の場合ですと、スクイーズ・アウトといって、対価をキャッシュで払って強制的に買い取れますが、日本ではできません。日本では、株の単位を大きくしていって、端株扱いにしてしまうという姑息な手段が使われたりします。
高崎経済大学論集結合企業と代表訴訟(2・完)山田泰弘
http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/45-3/yamada.PDF
また、結合企業の形成と解消を一度に行うことも、その合法性に問題があるものの、実務上行われ、ジャパニーズ・スクィーズ・アウトと呼ばれているようである。ジャパニーズ・スクィーズ・アウトとは、企業買収において、買収対象会社の総議決権数の3分の2を取得した後、買収対象会社につき株式交換・株式移転を行い、新たに買収対象会社の親会社となった会社から、対象会社の株式を100%譲り受けた後に、親会社を清算してしまう方法をいう。
合併等に際し1株未満の株式の譲渡代金を被合併法人等の株主等に交付した場合の適格合併等の判定(国税庁)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1053/01/1_4_2.htm
(端株主にお金を支払っても適格合併に該当しなくなることはない、という内容。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。