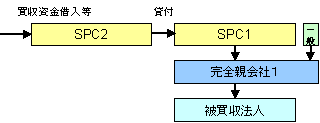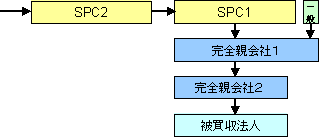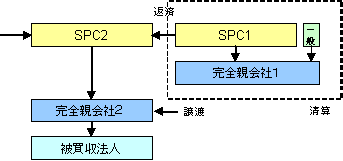本日の朝日新聞朝刊の「反時代的密語」で、梅原猛氏が首相の靖国参拝について書かれてます。梅原氏は、昭和五十九年に行われた首相の靖国公式参拝の合憲性を審議するために儲けられた藤波官房長官の私的諮問機関「靖国懇」の中で、靖国参拝に2つの理由を挙げて反対したそうですが、その理由の一つがちょっと興味深かったです。
記紀に示される伝統的神道は、味方よりむしろ味方に滅ぼされた敵を手厚く祀るが、靖国神道は自国の犠牲者のみを祀り、敵を祀ろうとしない。これは靖国神道が欧米の国家主義に影響された、伝統を大きく逸脱する新しい神道であることによる。
なるほど。確かに、菅原道真とか平将門とかは、やっつけた相手のほうのタタリを恐れて祀られたものですし、仮に首相が靖国参拝をして「二度と戦争を起こさないという誓いを立て」ているのだとしても、殺された米兵やアジアの人々を弔っているという感じはあまり伝わってきませんね。
憲法や政教分離を考える前に、そもそも「人はなぜ宗教的活動を行うのか」という疑問があるわけですが。説明の方法のひとつとして、「それは一種の”情報処理”的必要性から生じるのだ」という考え方ができるかも知れません。
人を人たらしめているものは「情報」です。子供のころから積み重ねてきた記憶や考え方などの「情報」によって自分は自分として存在している。また、人が死んだら骨しか残らないかというとそうではなくて、その人に関することは、その人を知る人たちの脳の中に「情報」として残ります。
「人が死んでからも残って人々に影響を与えるもの=霊」とすれば、「”情報”は霊である」と言えるかも知れません。また、自分を自分たらしめているものが情報であるとすれば、人は死んでも形を変えて生きている人々の脳の中に(分散してネットワーク的に)生き続ける、と言えるかと思います。つまり、「天国は、人々の脳のネットワークの中にある」とも。
脳というのはコンピュータのようにクールに情報処理を行うマシーンではないし、心と体は二つにきれいに分離されたレイヤーではなく、脳が感じるつらいこと楽しいことは、体にも社会にも様々な影響を及ぼします。
失恋や死で大事な人を失った場合でもスパッと気持ちを切り替えてしまえばいいものを、そうはいかないのが人間ですし、ましてや人を死に追いやったりしたら「向こうも悪いんだ」とは思ってみても、苦い気持ちは残るし心や体にも大きな変調をきたしても不思議ではない。
本来、「色即是空、空即是色(現実=情報、情報=現実)」であって、世界は単なる情報としてしか認識できないし、我々の認識そのものが社会を作り出しているわけですが、そういったクールに悟った状態を「あるべき姿」と考えると、人の心にはいろいろと「バグ」やら「セキュリティホール」やらがあって、特定の情報は、そのセキュリティホールを激しく突いて攻撃して来る。
さらに、そうした「いなくなった人に関する情報」は、脳の中に思い出として静的に存在することもありますが、場合によっては自ら増殖し、周囲に広がっていく。つまり、「ミーム」性もあります。
菅原道真などは、幼少のころから学問に秀でていて人々に対する(情報的)影響度も高かったとのことで、大宰府への左遷以降、道真に関する情報は京の人々の間で口から口へ「ミーム」として強力に伝播したのではないか、と想像します。
「敵を祀る」というような宗教行為は、こうした情報やミームからのセキュリティホールをふさぐための「パッチ」の一種と言えるかも知れませんね。つまり、北野天満宮とwindows updateはある意味同じカテゴリに入ると。
草薙素子もネットと融合して文字通り「情報」(=霊(ghost))になった、ということですが。(つまり、”in the shell”でない”ghost”。)
脳だけが形成していた社会に、blogのようにどんどん「セマンティック」に進化するネットが加わることによって、「霊」や「宗教(すなわち、脳の”OS”を前提とした社会のガバナンスのモデル)」のあり方も当然変化していくはずかと思います。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。