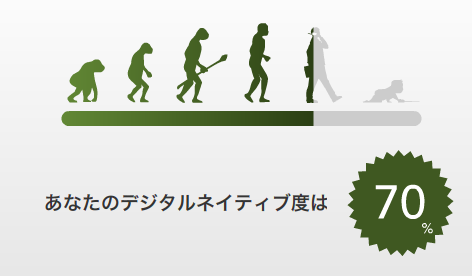何人かの方から、「ブログ更新されてませんけど、生きてます?」というお問い合わせをいただいたので、とりあえず生存のご報告まで。
「仕事が忙しいんですか?」とのご質問もいただきますが、仕事もボチボチやらせていただいておりますものの、それよりも、前にも申しましたとおり、最近「放送大学」にハマっちゃいまして、それでブログを書く時間がなくなっておりまして。
放送大学は昔からあったわけですが、前にも申しました通り、アナログ放送時代と違って
放送大学 + 地デジEPG + HDDレコーダ + インターネット(Wikipedia等)
という組み合わせはサイコー!でございまして、好きな時間に好きな授業を(場合によっては早回ししたり、巻き戻したりして)見て、わからないところはネットで調べるなどすると、まるで、大昔の映画「禁断の惑星」

に出てくる、古代の異星人が遺した「頭の良くなる機械」のような感じなのであります。
(実際に頭がよくなってるかどうかはともかく)、情報はものすごい勢いで流れ込んで来て、今まで断片的だった知識が、「あ、なるほど、こことここがつながってるんだ!」とAha体験の連続。こりゃー、やめられまへんわ。
「学ぶ理由は十人十色」で、非常に多様な科目があるので人によって見方は異なるでしょうけど、私の場合、下記のような科目がハマりました。
情報通信技術系科目
非常に熱心にわかりやすく解説されてますし、「なるほど」と勉強になる部分があります。(ただし、なにせ技術革新のスピードが速すぎる領域だけに、ネットで毎日見ている情報に授業が追いついていない面はあります。)
法律系科目
法律系の科目も、(もちろん内容は非常にしっかりされてますが)、放送大学の授業の中では、単に基本書などを読んだり大学で授業を受けたりするのと、あまり変わらない方かなあという気がします。
ただし、「裁判の法と手続」など、最高裁判所判事の部屋に入って背景に皇居の緑をながめながらインタビューに聞き入るなど、放送大学ならではの普通ではなかなかできない体験もできます。
分子生物学、細胞生物学系
これはすごい。
私が高校で生物を習ったのはもう30年も前になりますが、ヒトゲノムの解読に代表されるように、それ以降のバイオ系領域の進展というのは、すさまじいものがあります。
もちろん、その間も新聞や雑誌などで情報を拾っていたわけではありますが、授業で体系立って説明してもらえるのに加えて、
「DNAがほどけてRNAに転写されて、リボソームがうんぬん・・・」
というあたりになると、超よくできたCGによる説明があるのと単に本を読むのとでは格段の差があります。
時々、NHKでもそっち系のいい番組をやってはいますが、記者の人の目を通してマイルドに仕上がっているのと、研究している学者の方が直接語るのでは、新聞記事とブログくらいの差、おそば屋さんのカレーと本格インドカレーくらいの差があるのであります。(おそば屋さんのカレーの方が好き、という人もいるでしょうし、それはそれで結構なのですが、私は本格インドカレーの方が好き。)
行動生態学系
これもすごい。
昔から大ファンであります長谷川眞理子先生による「動物の行動と生態(2004)」が10月からはじまってますが、前期にやっていた長谷川寿一・長谷川眞理子ペアによる「進化と人間行動」も何ともすばらしい。
これは、DNA、細胞、器官、個体、群・・・といった「多レベル」間の利益相反のある進化といった視点や、人間の脳などのハードウエアが、基本的には石器時代の狩猟採集生活に適応したものとなっている、といったお話で、最後の方にはゲーム理論的な合理的行動と、実際の人間行動の違いのお話なども出て来て、経済学にもつながっております。
私は経済学科出の人間ですので、どうしても合理的行動から出発して、その例外として限定された合理性を考える、というアプローチでモノを考えてしまっていたのですが、社会や経済の素直な理解としては、石器時代の脳の人間が集まって合理的っぽいことをしているという方が実態をよく表しているなあというコペルニクス的展開が私の頭の中でありました。
経済政策
大学院の授業ですが、ミクロ経済学から財政、金融、労働、変動相場制下のIS-LM分析・・・といったあたりまで、幅広くわかりやすくまとめてあるので、国民全員の必修科目にしてもいい気がします。しかも海外も含めたいろんなビデオや、岩田一政日銀副総裁(当時)とか中村伊知哉慶應義塾大学教授、石井岡山県知事へのインタビューなども入っていて、なかなか、普通の大学の授業にはない、放送大学ならではの贅沢な内容になってるんじゃないかと思います。
芸術の理論と歴史
芸術が単なる絵を描くといったテクニックのお話でなく、その時々の社会や文化や哲学と密接な関係をもって成立している、といったことが学べる授業。例えば、ルネサンス期の芸術と、メディチ家のビジネス、新プラトン主義哲学者の招聘などの関連が理解できます。
大学と社会
まだ一回目しか見ていないんですが、パリ、ボローニャなど、ヨーロッパ中世で成立した大学は、大学がある都市との間で抗争・対立があったため、対抗上、学生や教職員の「ギルド」的な性質を帯びていた一方、学問は理論武装としての「力」の性質があって、都市や国の間で大学の取り合いがあり、大学の分派がヨーロッパ各地に分散して行くことになった、といったあたりが非常に興味深いのであります。(なぜ作品のことを「masterpiece」というか?、とか、universityの語源は同業者組合だ、とか、ウンチクもいろいろ身に付きます。)
現代の会計
石川純治駒澤大学教授の授業。会計の授業を中世の複式簿記の成立あたりからはじめるというのは王道ではありますが、実際に1494年のルカ・パチョーリの最古の簿記書「SUMMA」(Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità=算術幾何比例要覧)の現物の表紙の写真や、それが「簿記」の本ではなく数学の本であったことなどは、まさしく「教養」。
また、全15回を通じて、会計というのが社会の要請を通じて(例えばフローとストックの間で)変遷を繰り返して来たこと、現在の「金融資産会計」が過去の取得原価主義の単なる修正で延長線上にあるものなのか、それともまったく新しい考え方なのかといった視点、会計には「コモンロー」ではない「エクイティ」的な考え方が含まれることなど、会計専門家の方々が見ても、非常に深い内容になっているのではないかと思います。
これは、長銀(終わっちゃったけど)やライブドアなど、会計と法のせめぎあう領域で裁判をされている裁判官、検察官、弁護士などの方々にも、ぜひ見ていただきたいシリーズ。
宇宙とその歴史
天動説から地動説への転換からはじまって、恒星、銀河、銀河団、といった宇宙の構造に至るまでの壮大なお話。杉本大一郎教授のご方針で、単なる技術的な話に終わらず、宇宙からの情報を取得してそれをどのような認識・モデルに落として行くか、限られた情報からいかに全体像を推論するかといったあたりが、一般の社会生活などにも役に立つのではないか、という視点からの作りになっているので、味わい深い内容になってます。
以上のような授業を見まくると何が起こるかというと、原子・分子からDNA、細胞、社会、地球、宇宙といった多元的な視点から人間や社会が理解できる(ような気がする)ということでして、これは、昔、手塚治虫の「火の鳥」
を一気読みして、宇宙から原子、太古から未来までの多元的な視点から人間とは何かを考えさせられた強烈かつ幸福なエクスペリエンス以来の感動と言ってもよろしいかと思います。
普通の大学・大学院や、ネットの大学等でも、これだけクオリティの高い interdisciplinaryな話を一気に聞けるという機会はまず無いと思いますので、そういう意味では希有な体験であります。
各授業15コマ×45分づつあり、ご紹介していない授業も見ておりますので、これだけ見るだけで100時間以上はかかっておりまして、ブログ書いてる暇がなくて申し訳ないです。そろそろめぼしい(私が興味ありそうな)授業は見尽くしてきた感がありますが、もうちょっと残ってますので、落ち着いたらまたブログ執筆に復帰したいと思います。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。