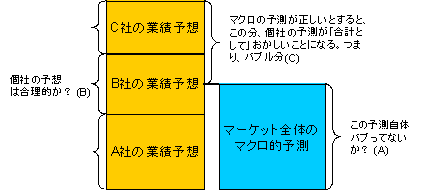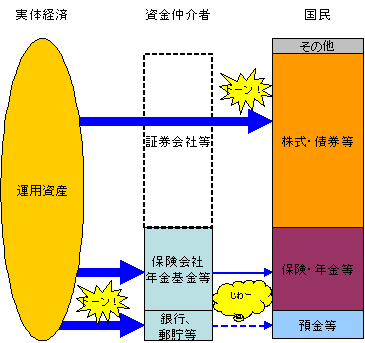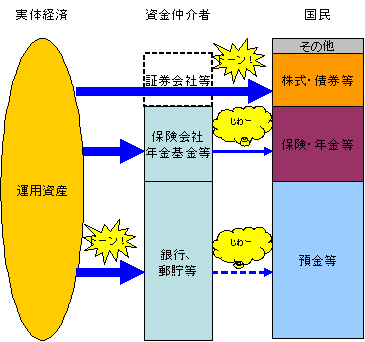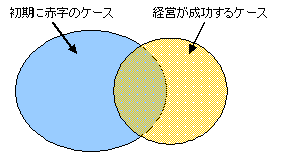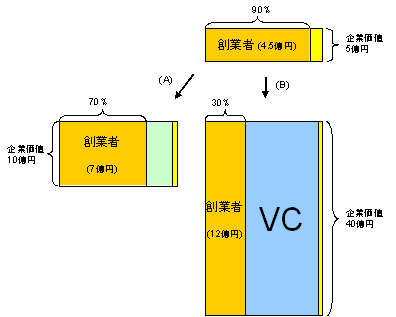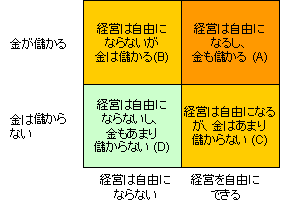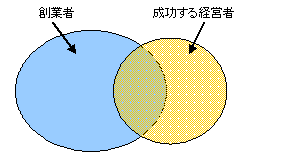「mtanaka」さんから、「バブって、いーとも!」(我ながらナニなタイトル・・)に、今まで見たことないような長文のコメント(A4で4枚分くらい!)をいただきました。
いろんな論点をまとめていただいてますので、(mtanakaさんにというよりも、そうした論点に対して)、以下、私のコメントを述べさせていただきます。
(引用部がmtanakaさんのコメント)
Google のIPO、Dual Class 等に関する議論を非常に興味深く見せていただいております。
どうもありがとうございます。<(_ _)>
本問題は様々な形で議論されていますが、個人的には以下の4つのレベルで本問題をみるべきかと思います。
ということで、mtanakaさんは、
1.経営の失敗とチェック機能
2.株主の失敗とチェック機能
3.資本市場の失敗とチェック機能
4.国家の失敗 アメリカ体制の失敗
の4つのレベルを挙げられてます。
Googleが考えるべきなのは1か、せいぜい2のレベルのお話ですよね。
3、4はマクロのお話で、政府なり規制当局が考えるべきことですね。
さらに、バブっているといってもまだ数兆円程度。これがマクロ経済に壊滅的な影響を与える、というようなモノとはちょっと考えにくい。
しかも、Googleは時価総額はともかく、まだ、たかだか純利益数百億円程度の「中堅企業」にすぎません。このレベルの会社が、IPOするときにマクロ経済的影響まで考えておかないといけないってのはちょっと酷です。
「純利益100億円、従業員数1000人を越す企業が株式公開その他のファイナンスを行う場合には、2名以上のマクロ経済学者からの意見書を添付しなければならない。」というようなレギュレーションを作ったら意味があるでしょうか?
ないですよね。
また、この程度のファイナンスが自由にできないような規制は、経済の活力をそぐ悪影響の方がはるかに大きいと思います。
以下、詳細。(長いのでお時間のある方だけどうぞ。)
1.経営の失敗とチェック機能
経営者も人間である以上、失敗はありえます。その場合、現在の資本主義社会では取締役会が経営者の失敗を監視する責務が与えられています。
Googleの場合は、3頭体制によって業務遂行をおこなうことを常態とすることによって、ここでのチェックアンドバランスを図ろうとしており、また、名だたる経営者を社外取締役に配置することによって、取締役会の決定が公正を期すことをアピールしています。これらのガバナンス構造は争点にはなってはいません。
(争点になってない、というのは、意見の対立がない、ということですか?)
Googleの取締役会、各種委員会によるレベルのガバナンスのしくみは形式、人材ともに、やるべきことはほぼやりつくしており、合格点をあげられるんじゃないかと思います。
(最新の議論を盛り込むとしたら、あと、CEOと会長職の分離くらい?)
(ご参考エントリー:「Googleのガバナンス構造の整理」)
2.株主の失敗とチェック機能
しかし、取締役会の構成がいかに緻密に公正に組織されていようが、それに信任をあたえる株主総会が偏向していれば、企業経営は正しく運営されないかもしれない。
ここで、大きな意見相違が見られます。Google のIPO方式に異を唱える論説は、この株主監視のレイヤこそがもっとも本質的なガバナンスの実施形態であると見ています。取締役会のありうべき暴走行為に対してもっとも効果的な規制をおこなうものが株主総会であって、ここでの判断の総体こそがもっとも「神聖」なものであり、それを恣意的に構成してはならないというのが異議派の論点です。
一方で、江藤健太郎さんなどのGoogle擁護派は、株主総会による管理機構というものはもっとも優先的なまた、正しいガバナンスの実施機構ではない、と主張しています。これは「会社は誰のものか」という古くて新しい問題であると同時に、誰が最も正しく事業の将来を判断できるのか、という本質的な問題にもかかわります。Google擁護派は昨今のいきすぎたイクイティゲームへのアンチテーゼとして、Googleの判断を擁護し、外部資本家による短期業績偏重の価値基準では、Googleの真の潜在的経済価値を発揮できないと主張します。(磯崎さんは、もっとドライに、別に法に抵触してないんだからいいんじゃないの、それなりのスタビライザーもちゃんとあるんだし、というご意見だとお見受けしますがそれについての意見は後に述べます。)
いえ、私も、法に抵触していないことだけが理由じゃないです。(念のため。)
また、「会社は株主のもの」なのはもちろんとしても、実際、株主が議決権を行使できるのは、多くて年数回程度なので、どう考えたって株主総会の議決権を会社の舵取りやガバナンス機構の中心に据えるのは無理があるじゃないですか。
一方で、「株式市場」は毎日秒単位で動いています。特に、Googleの場合には、世界でもトップクラスのすごい流動性が期待できますので、ここで非常に「なめらかな」市場メカニズムによる監視機能が働くことが期待されます。
別のエントリーでも申しましたが、株式会社では「所有と経営は分離」されており、またインサイダー規制により、株主は基本的に一般に公開された情報以外の情報をもとに何か判断できるわけではないです。
例えば「不動産のオーナー」が、不動産の管理をまかせている人に、「あの物件は最近どうかね?」と聞いて、管理人が「それはインサイダー情報なので教えられません」なんていったら張っ倒されますが、公開会社では逆に「会社の所有者」がそういう情報を個別に入手すること自体が犯罪につながる可能性が高いわけです。
株主が会社を「所有」しているというのは、かように、普通の「所有」概念とは全く異なるものです。「会社は株主のもの」という言葉を勘違いして「所有者=何でもできる」てな前提で、実効性のないしくみの話をしてもしょうがないと思うんですよ。
つまり、「会社は株主のもの」というのは、主として「経済的」な意味であり、公開会社の場合、その株価のメカニズムによる会社への影響の方が議決権のよりはるかにデカい。ただし、Googleの場合、「買収」で株を買うのだけは止めてね、ということです。これも、別エントリーで申し上げたとおり、この規模の買収は(Googleが元気なうちは)、独禁法に抵触しかねない領域の話になりますし、Googleが弱ってきて時価総額が1/10くらいまで下落して今後自力で回復する見込みがなければ、VCも経営陣もClass BをClass Aに転換して、会社ごと売っぱらっちゃった方が得です。そこに「経済的な」ガバナンスのメカニズムは強く働くわけです。
残念ながらこれらの主張の両方とも真理でもあり、また偽でもあります。いかなる場合においても株主総会の判断が「長期的な全体の利害」に照らし合わせて正しい判断をしてきたとはとても立証できません。同様に過去のパフォーマンスがどれほどすばらしかったにせよ、Googleの創業者の二人が今後もその他の人間よりも正しい事業判断を継続しつづけると立証することもできません。
ただ、Googleはイレギュラーであるにしても既存の株主主権のルールに違反しているわけではありません。梅田さんがアントレプレナーの資質として以前言われるように、既存のルールをすみのすみまで理解しきって、それに則った上で「ひょっとすると逆手にとって」大きな資金調達とそれによる長期的ビジネスの実現を仕掛けようとしているのです。
その意味で、ビジネスオペレーションの法的ルールの掟にしたがって彼らなりの[Not doing evil」を実践しているにすぎません。
他方、公共の光に照らされた議論においてのみ真理が開示されるという観点は、資本主義をこえた、アメリカ民主主義を貫く非常に大きな価値基準でもあります。もしも二人の創業者のもくろむ長期成長のシナリオが真に株主にも利益をもたらすのであれば、別の文脈でJeff Bezosが社内の反対勢力に対して非常に苦労しながらもそうしたように、明確な説明を試みるべきです。君達にはどうせ理解できないだろうといわんばかりの態度が梅田さんを憤慨させているのだと思います。
分厚いS-1であれだけ詳細に説明してるのに、なぜ「君達にはどうせ理解できないだろうといわんばかりの態度」ということになっちゃうのか、それがオラにはよぐ解がんねえだ。
「オレの自宅まで直接説明に来い」ってことなんですかねえ?
いずれにせよ、技術的な商法理論上のみでは扱えない観点がここには含まれており、個人的にはこうした公共民主哲学はアメリカ社会の最も尊敬すべき一面であると考えています。こうした価値観をもつ人々は、単にGoogleに投資さえしなければ良いじゃないか、といわれてしまうかもしれませんが、それだけでは済まないということを以下述べます。
(ふむふむ?)
3.資本市場の失敗とチェック機能
おそらく、ベンチャービジネスの適正を考えれば、こうした資本市場の失敗如何を問題にすること事態が、ベンチャービジネスの実践者としての資格を失うことになるのかもしれませんが、明らかに資本市場の失敗というものも存在します。
いうまでもなくそれがバブルです。これは社会全体にとっては大きな損害と軋轢を生み出す一方で、ベンチャービジネスクリエイターにとっては結果極大化のためのドライバーでもあり、必要悪でもあります。
Googleが上場することによる株式市場へのインパクトはプラスでもありえ、またマイナスでもありえます。一説には時価総額数兆円ともいわれてはいますが、彼らの真意がどうであろうと、また彼らの経営がいかに正しく運営されていようがされていまいが、ここでバブルは「発生しえ」ます。もしもかりにGoogleがバブル相場を誘発し、その後創業者の采配の失敗といびつな株式構造による是正の遅延が響けば、数兆単位の損害を株式市場にもたらすこともありえます。これは直接間接に実体経済に必ず飛び火します。会社がパブリックになるというのは、そういった意味で直接投資家の懐以外の経済にまで波及するわけで、Googleのような企業であればなおのことです。しかし、こうしたダイナミズム自体は資本主義プロセスにとっては必要悪なのであって、そうした「ありうべき社会的結果への配慮から」株主構成を透明化しておけということは、アントレプレナーにとって大きな矛盾を要求することでもあります。こうした失敗の存在を了解しつつも、より大きな創造性の発露のもつメリットを優先するというのが資本主義の原則であるからです。ここには解決されえない、資本主義制度の大きな文化的矛盾(ダニエルベルがいったものよりもより今日的な意味でのもの)が存在しています。
しかし、磯崎さんは、米国においてはこうしたバブルに対する免疫が日本よりははるかに高い、日本での免疫力が低いのは銀行による一極集中型の金融システムにあるとおっしゃっています。たしかにそのとおりかもしれません。しかし、問題は、当然のことながら、米国は米国国民のみによって成立している単一経済圏ではなく、国家政策を通じて世界経済とつながった存在であるといことです。
おっしゃることはごもっともだと思います。ごもっともではありますが、私がずっと申し上げてきたのは「だから、どうせいっちゅうの?」ということです。
経済は、お天気などと同じで「カオス」であり、人間のあるアクションは、どこにどう波及するかわからない。ある要因がどのように波及するのかを事前に完全に予測して行動するなどということは人間には不可能じゃないですか。
日本の土地バブルのように、金融資産比で数十%が消えて無くなっちゃうようなものは「悪」と言ってもよろしいかと思いますが、Googleの時価総額はアメリカの個人金融資産比で0.1%以下の金額、さらに実際に調達するのは数千億円程度で、0.01%以下の金額です。たとえ、この全額がクラッシュしたところで、米国や全世界の経済の中で十分ショックを吸収できる額でしょう?
例えば300万円貯金のある人が300円の宝くじを1枚買ったとします。それは「堅実な出費」とは言えないかも知れないが、それがもとで家計が破綻する心配をしたり、「射幸心をあおることにつながるのでけしからん」てな話をしないといけないことですかね?
もちろん、「カオス」ですので、よく引き合いに出される、「中国の蝶が羽ばたいたせいで、アメリカがハリケーンに見舞われる」というようなことが起きないとは言えません。が、だからといって、その蝶にハリケーン被害の責任を問うんですか?
4.国家の失敗 アメリカ体制の失敗
ここで見ておくべきもうひとつの観点が存在します。それは国家体制の問題です。こうした市場の失敗に対して、過去において政府はなんらかの形で国家が介入をおこなってきました。ひとつには監査機構によって、競争条件を可能な限り均一化させること、もうひとつはおきてしまった資源配分の失敗や偏向に対して福祉政策で修正をおこなうことです。しかし、21世紀になって顕著なのは、こうした資本主義のメカニズムが国家を超えて適応されることによって、富の偏在が「国家間でも」現実に発生してしまうということです。確かに競争のルールは公正だったかもしれない、しかしその結果の不平等は目にあまりとても甘受できないという問題です。広い目でみればこうした結果の不平等が、テロリズムの形で米国の社会体制への脅威、ひいては経済体制への脅威をももたらしているともいえます。
おっしゃるとおりですね。
(で?)
経営の失敗を株主が是正し、株主の失敗を資本市場が是正し、資本市場の失敗を国家が是正するという多重構造によって現実の社会は成り立っていますが、上述のように、かならずしも上位の是正機関が正しく是正機能が果たせると確約されているわけではありません。多くの複合的な要因でカタストロフに陥ることもあれば、予想外にうまくいくこともあるでしょう。いずれにせよ、Googleの資本構成の提案に関しては投資家がその是非を判断するでしょう。またそのサービスについては顧客がその是非を判断します。しかしそうしたチェック機構の存在を持ってしてもなお資本市場は本件で大きなバブルを引き起こすかもしれません。それが予想外の社会的損害をもたらすとしても、ビジネスオペレーションの法的ルールにさえ則っていれば良しとされるべきでしょうか。私はこの点の警鐘を鳴らしている点で梅田さんの趣旨に賛同します、と同時に過去に梅田さんが説かれたベンチャービジネスの適正についての論述について、同じ観点から賛同しかねます。やはり、アントレプレナーであってもビジネスオペレーションの法的ルール以外にも守らなくてはならない公共市民としてのルールがあると思うからです。
それは、We are 「Not doing Evil」と無邪気に標榜するだけで済まされるものではなく、公共市民としての自らの権利と責任またある種の限界を、社会に対して明確に表明することだと思います。
それは、S-1のリスクファクターにクドいほどいろいろ書かれていることではまだ足らん、ということでしょうか?あれ以上何を表明すればいいのでしょう?
マクロ経済学者や倫理学者、宗教学者、コンピュータ科学者などからなるIPO審査委員会を作って審議してからじゃないとIPOできないというような仕組みにしたらよろしいのでしょうか?
アメリカ民主主義の誇リ高い公共意識と、グーグルの描く、ある種無機質なNon-Digital Divide の理想郷。ガバナンス論のより先にはこうした根源的な価値判断の地平が広がっているように思います。
アメリカ民主主義の誇り高い公共意識なんて今時あるんかいや?というむきもいらっしゃるかもしれません。たしかにそうかもしれませんが、私個人としては米国の日常社会のそこかしこ(私としては人づてに話を聞くことしかできませんが)や、WestWing などのエンターテイメント番組、そしてもしかしたらStarTrek などの3文スペースオペラ(私は大好きなんですが)にも、いまだ脈々とこうした公共意識が根付いていると信じたいと思っております。
乱文失礼いたします。
繰り返しになりますが、Googleのどこが公共性に欠けるのか、またGoogleに、もし公共意識を欠くところがあるとしたら、具体的にあと何をすれば許していただけるのか?、ということです。
「リスクがあります」
あるに決まってんじゃん。
計画経済が「無菌」の状態を志向したとすれば、資本主義は「菌は存在する」という前提のしくみにしているところがシステムとして強いところだと思います。
菌やウイルスで風邪も引くけど、それによって免疫力も付く。無菌環境は、万が一無菌状態が破られたときには抵抗力が無い非常に脆弱なシステムです。
Googleはもしかしたら乳酸菌じゃなくて「バイ菌」かも知れないが、それほど重篤な病をひき起こす菌とは今のところは考えられない。
であれば、何か発症するまでは放っとけばよろしいんじゃないでしょうか。
それで経済がちょっと病気になったとしても、それによってさらに経済は強くなります。
何事も「やってみなはれ」でっせ。そこが資本主義のええとこでっしゃろ?
(では。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
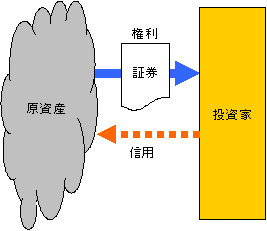

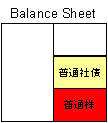
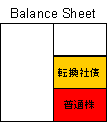
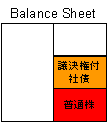
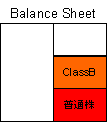
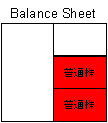
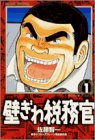 「壁ぎわ税務官」
「壁ぎわ税務官」