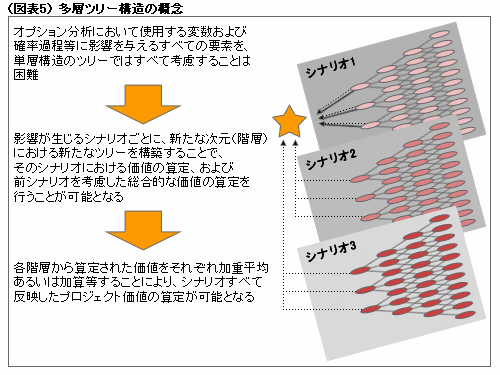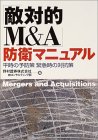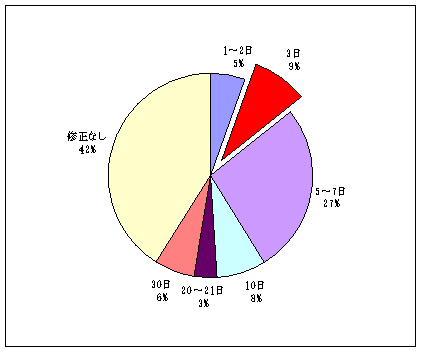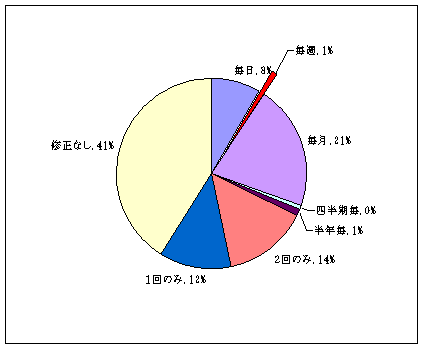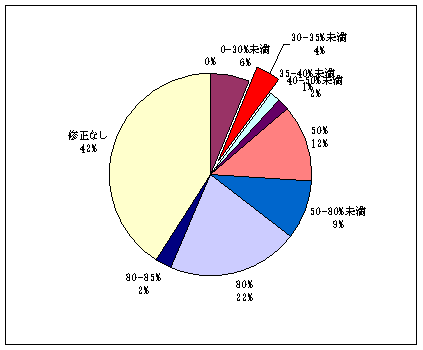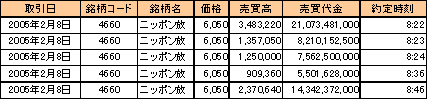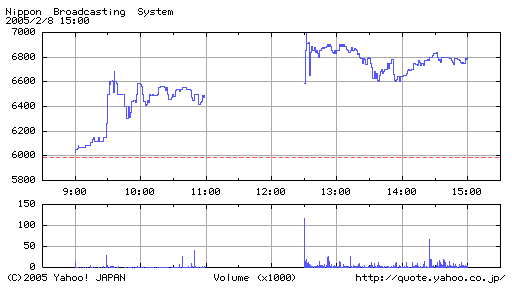こんばんは、滝川クリステルです。もとい、磯崎哲也です。
昨晩のフジテレビ「ニュースJAPAN」では、一っ言もライブドアについて触れてませんでしたね。(ちょっとびっくり。)
(追記あり:2/11 6:00)
さて、47thさんからトラックバックいただきました。
それにしても、磯崎さんも、またセンセーショナルなタイトルを・・・いえいえ、昨日は取り急ぎ思いついたことを書いたので、やや舌足らずなところもあったのかもしれませんが、私は、ライブドアの今回の取引を「違法だ」なんて・・・そんな大それたことは申し上げていないんです・・・信じてください。
ただ、「アグレッシブ」あるいは「法的リスクが高い」ということを言いたかっただけですので・・・(え?同じこと?)
ただただ、依頼者から相談されたら「お薦め」はしませんが、「どうしてもやりたい」というのであれば、「違法行為には加担できませんので辞任します」というような話ではなく、「えー、本当にいいんですか?知りませんよ・・・」(渋々)というレベルの話です。
ということだそうです。
私も「違法か?」と言っただけで、「違法だ」とは申し上げてませんので、念のため。(笑)
>みなさま
ただ、先日のエントリーの最後にも書きましたが、私としては、フジテレビさんに、「違法だ!」と言って、告発するなり、東京地裁の民事第9部あたりに駆け込むなりしていただいて、司法がどう判断するのかは、(不謹慎に聞こえるかも知れませんが)、非常に見てみたいところです。
住友信託 vs UFJの件もそうでしたが、今までは、「そんなことで裁判所のお世話になるなんて、いやですわねー」という感じだったものを、お白州の場に引き出すことで、いろんなことがオープンになって、法制度の問題点やあるべき事前の手当などが広く周知されるので非常に社会に与える教育効果が大きいと思うんですよね。
買収防衛策整備の必要性
先日、買収防衛にお詳しい某弁護士さんが、
「ドイツやイギリスなど、ヨーロッパでは、議決権の30%を買いたい人は(既存株主が売りたいと言えば)100%買わないといけないという、攻める側への規制がある。つまり、”経営にコミットする人”にしか買収を許さない。
一方、アメリカでは、攻める側にこうした公的な規制がない代わりに、守る方もライツプランやポイズンピルで自由に防御していいことになっている。
これに対して、日本では、攻める方は自由だが、守る方は規制でがちがちに縛られている。守る側に圧倒的に不利。」
とおっしゃってました。
今回も、ライブドアさんはわずか1/3超を取得するだけで、フジサンケイグループ全体に非常に大きな影響を与えられてしまうわけです。
いわば、釣り人が糸を垂れて、撒き餌(TOB)をせっせとやって魚がたくさん集まってきたところを、横から悪ガキが、タモで一番大きいのを数匹ごそっと持って行っちゃったようなもんですからね。
それにつけても、以前、梅田望夫さんの記事に関連して行ったGoogleのdual classの株式によって買収防衛するのがいいのか悪いのかという議論が思い出されますが、私はやっぱり、アメリカでは「相手が銃を持ってるかも知れないから、自分も銃で武装する権利がある」という考え方で均衡が図られているんだと思いますし、Googleの取締役は、「MicrosoftやYahooが斬りかかってきたらどうするか?」という点にも注意を払ってIPOしたのは正解だと思います。
日本でも、今まで、「日本は安全だから、別に身を守ることなんて考えなくてもいいや。」と考えられてきたわけですが、今回のように横から人が集めた大物をかっさらうような「やんちゃな悪ガキ」がたくさん登場しつつあるわけですから、真剣に防御策を考えないといけないですね。
大株主異動のインサイダー取引
と、今ふと大変なことを思いついちゃいましたが。
以前、「ニッポン放送株式取得とインサイダー取引」で、双方がTOB等を知っていて取引する場合にはインサイダー取引にならないという規定(167条)をご紹介しましたが、TOBでない方の証券取引法第166条第6項第7号にも、同様の規定があります。
しかし、両方とも下記のように、
七 第一項又は第三項の規定に該当する者の間において、売買等を取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る特定有価証券等について、更に第一項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場合を除く。)
と、「市場外で」行うことが条件になってます。
昨日申し上げたように、今回の場合、「市場外」で行ったのならTOBにしないと違反ですし、もし、ライブドアが大株主になることを知っていた場合、「市場内」で取引を行ったのなら、インサイダー取引に該当してしまうんじゃないでしょうか。(知っていたとしたら、ですが。)
昨日のVWAPに対して、手数料分くらいしか乗ってないわけですが、インサイダー規制は
「利益が出る出ないに関わりなく」違反になります。
また、違反になった場合には、利益だけが没収されるのではなく、それに関わる「財産」が没収になります。つまり、仮に(仮に、です)全部そうだとすると700億円くらい。
うーん。このへんは大丈夫なんでしょうか。
今回の開示のタイミング
「しがない」さんからコメントいただきました。
YAHOOファイナンスのインサイダーではないかという書き込みは東証の適時開示情報サービスを見てのコメントじゃないでしょうか。
http://www.tse.or.jp/disclosure/index.html
こちらで7日以前の買い付けについては8:20分に開示されています。
ほんとですね。ありがとうございます。
知ってないとその時点で、「ライブドアと村上は繋がっている。」(ヤフー掲示板のコメント)というところまで考えがおよばないんじゃないかとも思いましたが、まあ同じ六本木ヒルズですし、ニッポン放送といえば村上ファンドですし。もちろん、これが証拠になるというようなもんでもありません。
ToSTNeT取引の約定詳細についてはこちら。
http://www.tse.or.jp/market/tostnet.html
この買い付けについては適時サービスのほうで9:25分に開示されているようです。
ほんとだ。だから9時半で値段が跳ね上がってたわけですね。ありがとうございます。
ちなみに、教えて頂いた東証さんの「ToSTNeT取引-超大口約定情報」では、「ToSTNeT-1の株券に係る単一銘柄取引のうち売買代金が50億円以上のもの」だけ公開されてます。
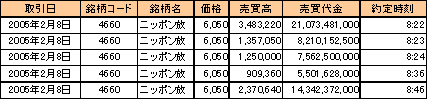
これを足しても9,370,270株、約567億円にしかなりません。
自分の持ち株数とぴったり同じだったらバレバレなわけですが、この開示を抜けようとおもったら、50億円以下に細かくわけて約定させればいいわけですしね。
ん?
まてよ。もしかして、上述の「大株主」のインサイダー取引違反を回避するために、まず、「前日まででライブドアが大株主になったので、大株主が異動しますよ」というのを8:20分に開示して、その直後の8:22分あたりからToSTNeTで取引を開始したということでしょうか?
ライブドアさんが、35%のうち先に一部を普通取引で取得したのは、「ToSTNeTで入手する予定の分」では33%に足らないからだとばかり思ってましたが、よく考えたら、
株式会社ライブドア:1,756,760株(発行済株式総数の5.4%)
株式会社ライブドア・パートナーズ:9,720,270株(発行済株式総数の29.6%)
合計:11,477,030株(発行済株式総数の35.0%)
ですから、33.33%ギリギリ取得するんだったら、何もライブドアが先行して5%超取得して、わざわざ開示する必要もなかったわけですからね。
(追記)ホントにインサイダー取引にならないのか?
(2/11 6:00)
taka-mojitoさんからコメントいただきました。
さて、今日は、読んでいて若干気になった点があったので、勇気をもって一言。
「主要株主の異動」は、確かに証取法166条の重要事実に該当するのですが、これがインサイダー取引となるのは、ニッポン放送の会社関係者がその職務等に関し、その事実を知って公表前に取引を行った場合、または当該ニッポン放送の会社関係者から当該情報を受領した人が公表前に取引を行った場合ではないでしょうか。つまり、従前の株主とライブドアとが、ニッポン放送の会社関係者と無関係に(会社関係者から情報を得ずに)、直接情報交換を行った場合には、どちらもいわゆるインサイダーとはならず、証取法166条の規制対象とはならないのはないでしょうか。
おっしゃるとおりですね。
というか、帳簿閲覧権を持つ3%以上の株主は「会社関係者」ではあるのですが(証取法166条�(2))、インサイダー取引に関係するのは、「当該権利(帳簿閲覧権)の行使に関し知ったとき」ですから、今回は関係ないですね。大変失礼しました。
ご指摘ありがとうございました。
加えて、「主要株主の異動」は、発生事実ですので、厳密にいえば、従前の株主とライブドアとの取引成立によって、その事実が発生するということで、取引の時点では重要事実が発生していないということにもなるのではないでしょうか。
ここは微妙だと思ったわけです。
つまり、株主はおそらく複数名いるわけで、仮にいきなりToSTNeTで10%の株がライブドアに異動して「事実」が発生したとすると、少なくとも二番目以降の取引をする株主は、「事実の発生後」に取引をしたことにならないでしょうか?
(今回の場合、先にライブドア本体による普通取引での買い集めして当日9:20分にはリリースしてますし、そもそも帳簿閲覧権に関係ないので、今回はそこは関係ないわけですが。)
あと、仮に「主要株主の異動」が発生した場合、公表を行うべきなのは、ニッポン放送のはずで、ライブドアが開示を行ったとしても、インサイダー取引との関係では、重要事実の公表にはならないと思われます。磯崎さんが「主要株主」ではなく、「大株主」という用語を用いているところに、ひょっとして意味があるのかもしれませんが、とりあえず気づいた点を指摘させていただきました。私の方に誤解等あるようでしたら、ご指摘いただければ幸いです。
(インサイダー情報に該当する大株主の移動があるとして)、それに関する大量保有報告書の提出や適時開示や報道があっても、ニッポン放送が公表するまでは取引しちゃだめと解されるでしょうか?(166条だけ読むとそうとも読めますが。)
ニッポン放送は、大量保有報告書が出されたら、その内容をプレスリリースしないといけなかったでしたっけ?
さて、仮に一昨日にタイムスリップして、「ホリエモンが某大株主等から合計35%のニッポン放送の株をゲットするらしいぜ」という情報を「会社関係者」等から聞いちゃった場合に、みなさんならニッポン放送株を買いますか?ということですが。
儲かるのは確実。でも、絶対有罪にならないかしらん?「バスケット条項」等にひっかかる可能性はないか?というようなことで、どうも、まだ「地雷」が残ってるような気がしてなんとなくおっかないですが、やっぱり、(荒っぽく言うと)、どんなに儲かるのが確実な一部の人しか知らない情報であっても、「会社の内部」から出た情報でなければ、インサイダー取引にはならないということですね。
と、今見たら、taka-mojitoさんとやりとりされて、47thさんも記事で、きれいに整理されてらっしゃいます。こちらも大変参考になりますので、ぜひ、ご覧ください。
(追記その2)167条対策は?
47thさんの「ブロック・トレードとインサイダー取引規制」(2)へのリンク。
TOBの場合のインサイダー取引の解説をしてらっしゃいます。
施行令31条に要注目のもよう。
(取り急ぎ。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。