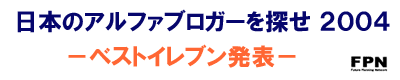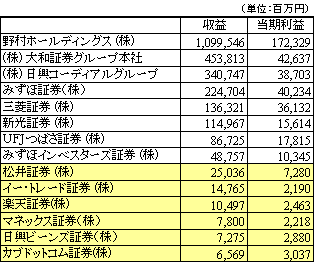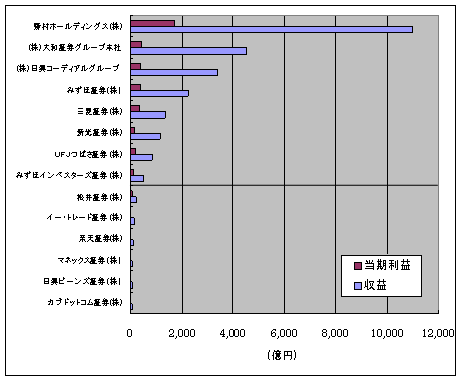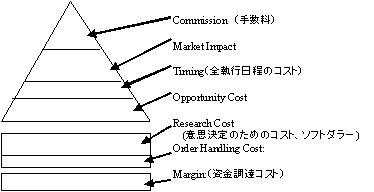一昨日のエントリー、「ファンドの外国人投資家への課税「強化」、ですって?」に対して、Bewaad Institute@Kasumigasekiさんから「続・バカには正しくバカと言おう」というトラックバックいただきました。ありがとうございます。
(このBewaadさん、現役の霞ヶ関官僚の方らしいのですが、いろいろ記事を拝見すると、霞ヶ関内部の考え方などが垣間見れて、非常にためになります。)
さて、一昨日の私の記事の要旨は、
みなさん、本件を新たな課税ととらえてらっしゃるようですが、税法上今でもすでに外国人投資家が払わないといけない(誤解を恐れずに平たく言えば「脱税」してるともいえる)税金を払えと言ってるだけじゃないの?。
これを考えた方は「低能」どころか、批判を浴びている株転がし的なファンドを含む事業投資的ファンドへの外国人投資家を中心に、日本が取るべき税金をきっちり確保するとともに、VCをはじめとする一般的な株式投資には比較的影響が出ないようにし、さらに税率も過度に高いものとならないことにするという、なかなかうまい落としどころを考えたもんだと思いますし、これで対日投資が減るというような大げさなもんでもないでしょう。
ということだったのに対して、トラックバックしていただいた内容は、
isologueの「ファンドの外国人投資家への課税「強化」、ですって?」での議論は、要すれば今回の措置はもともとファンドであっても課税される前提であったことについて、その「ファンド」とは何かという点であまりにもグレーゾーンが広かったものを、きちんと課税対象だと「明確化」した、というものです。この点については、LP(Limited Partnership)とかLLC(Limited Liability Company)といった類の、主としてアメリカ法に基づく準法人組織に対応する日本法の規定がなかったことに問題があったように思います。
従来の日本法に基づく制度に当てはめれば、民法上の(任意)組合か商法上の匿名組合が似通っているわけですが、これらは基本的に各出資者に租税負担が帰属し、ファンド自体には法人格がないという取扱いなので、法人税の対象にはなりません。では、上記のLPやLLCその他類似の組織には法人格があるのでしょうか、それともないのでしょうか。法人格があるのであれば法人税の対象になりますし、なければ対象にはなりません。
結論から言ってしまうと、アメリカでの取扱いは目的により法人格がないようにもあるようにも取り扱うというもので、何らかの行為がなされるときに、それがLP等への各出資者の行為と考えた方が合目的的なものについては法人格はないと考えますし、逆であればあるものとして取り扱われます。今回の租税の取扱いはこれらの組織について、こと法人税を課すかどうかについては法人格があると考えますよ、ということです。
ということでした。
私の説明が悪くかつ非常に文章が長かった面もあるかと思いますが、これ、ちょっと違うと思います。
つまり、私が「うまい落としどころ」だと思ったのは、以下のような点からです。
うまさその1:パススルー性は認めた点
もともとのグロービスの堀さんのコラムでも、「今回の課税強化はこのパススルー性の否定で、国際的にもおかしい」という旨のことが主張されており、また今回のBewaadさんの記事でも、今回の課税強化でファンドのパススルー(pass through)性自体が否定されたように読めるのですが、今回の「強化」では、ファンド自体に法人税を課さない「パススルー性」には手を付けてません。
課税されるのはあくまで、ファンドの構成員であるLP(Limited Partner=投資家)。
ファンドは、LPが払うべき税金を「源泉徴収する」(代わりに取り立てとく)だけで、ファンドが法人税を課されるわけではありません。
今後は日本版LLPもできますし、税務上パススルーのファンドが日本経済の再生や新しい産業の創成に役に立っているというのは、私は逆に今回の件で、課税側にも着実に認識されてきているのではないかと思ったのですが、どうでしょうか。
うまさその2:「キャピタルゲイン」には課税しないこと
これも一昨日のエントリーに詳しく書きましたが、外国法人等のキャピタルゲインには課税しないというタテマエは一応貫かれているところもうまいです。
「課税してるじゃん!」というツッコミが聞こえてきそうですが、あれ(法人税法施行令第187条�)は「実質的な中身は事業譲渡だから課税します」という趣旨なわけですね。
つまり、まず、外国法人等であっても、日本国内で「事業」をやっていたら課税されます。これは当然ですよね?不平等条約下じゃないので、外国人といえど「日本国内で」行った事業の儲けに日本政府が課税権を持つのは当然です。
また、外国法人等が国内でやっていたその事業を営業譲渡して儲かったら、それにも課税されます。これも納得できますよね。
では、日本でやっていたその事業を、営業譲渡じゃなくて会社丸ごと「株式」の形にパッケージングして譲渡したらどうでしょうか。実態としてはさっきと同じ事業丸ごとの譲渡なのに、「それはキャピタルゲインだから課税されない」というのはヘンですよね。
しかし一方で、例えば3%しか持ってない人は、「会社を経営していた」というよりは、純粋にフィナンシャルな投資をしていたわけであり、そのキャピタルゲインに課税するのはよろしくない。
・・・ということで、法人税法施行令第187条�や所得税法施行令第291条�では、「事業譲渡類似」の線引きを「25%以上」としていたわけです。今回から初めてというわけではなく、昔からもう既に。
じゃあ、どうやって「25%」を判定するかですが、令第187条�は、子会社とか奥さんとかお妾さん等に株を分散させたりしてても、まとめて25%と見ますよ、ということを定めています。(これも以前から。)
4 第一項第三号ロに規定する特殊関係株主等とは、同号ロの内国法人の株主等及び当該株主等と第四条(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。
要するに「グル」「仲間」はひとまとめで考えますよ、ということです。
それでは、ファンドのGPや各LPは「グル」なんでしょうかどうでしょうか?というと、みんなでまとまって投資しているので、普通の人の感覚だと明らかに「グル」じゃん?と思うと思うのですが、どうでしょうか?
今まで、上記の条文の「その他これに準ずる関係のある者」なのかどうかがいまいちはっきりしてなかったので、今回そこを「明確化」したというわけです。
今回の「課税強化」に反対される方は、理論的にはここ(つまり、各LPはまったくバラバラな投資家であり、それを束ねても事業譲渡類似にあたらないのだ、ということ)を攻撃しないといけないんじゃないかと思います。
(ただ、一般の国民は、再生ファンドが弱った日本企業を買って短期で高く売却するような行為は、まさに「日本国内での事業譲渡」にしか見えないでしょうし、「ファンドの個々の投資家は一人づつ別々です」というのも詭弁にしか聞こえないと思いますので、「政治的には」、対内投資が減る、というような言い方のほうがいいのかも知れませんが。)
うまさその3:タテマエ上「減税」です。
ということで、今までもそうした外国人投資家がそういうケースには日本で納税しなきゃいけなかったとも考えられるわけですが、これ、もし納税するとなると、例えば投資家が法人なら法人税率(〜30%)で税金を計算して納めないといけません。
ところが、今回の源泉徴収は20%ということになったわけです。
税制大綱の記述だけではよくわかりませんが、現行の匿名組合の規定と同じように20%の源泉徴収だけで課税関係が終了するのであれば、(タテマエとしては)「減税」ですよね。
「脱税」してた(または、条文はそうは読めないという「見解の相違」のある)人から見ると、当然「増税」に見えるわけでありますが。
というわけで、まとめますと、今回の「強化」は、「ファンドに」課税されるわけでもなければ、「(ピュアな)キャピタルゲインに課税される」わけでもありません。
−−−
いずれにせよ、税金というのは、取られる側からすると、どんな理屈があろうと絶対イヤなわけです。(笑)
しかし、以上のように考えてくると、今回の「課税強化」は、「取りっぱぐれをなくす」という意味の「強化」であり、日本の課税権の範囲を考えると極めて合理性な施策なんじゃないかと思うんですが、みなさん、どう思われますか?
(ではまた。)
(追記)
ご参考:切込隊長氏の本日の記事。「例のアレの増税に関する議論」
例によって(切込隊長ブログのトラフィックが多いからか?)、トラックバックのタイムアウトエラーが出てしまって、2回もトラックバックがついてしまいました。すみません。
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。