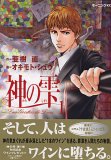火曜日の「『サラリーマン』によって日本の資本市場は歪められているか?」に対して、本石町日記(bank.of.japan)さんからコメントいただきました。
2003年の長期金利急騰(0.4%→1.4%)はサラリーマン的なリスク管理(VAR)によって引き起こされ、VARショックと呼ばれています。大手銀行のALM運営がサラリーマン的な側面が強いためで、ヘッジ会計に隠れて見えにくいですが、壮大なる失敗とみられる例がディクロージャー誌などにこん跡が残っている銀行もあります。一方、うまくいくと業務純益の半分をトレジャリー業務で稼ぎ出しますから、取るポジションは時として凄まじいです。銀行勢は概ね期初の買い、期末の売りのパターンが多く、レミング的な行動を取るケースが多いので、これをうまく逆手に取る機関投資家も存在するようです。さすがに最近はVARショックの教訓から、銀行勢は無茶なデュレーション長期化は避けているようです。
とのこと。
メディアで届きにくいタイプの情報
「VARショックと呼ばれています」ということですが。この「VARショック」という用語はgoogleで検索してみても、なんと13件しか表示されません。うち、生きてるのは10件くらい。(本石町日記さんのページ2件を含む。)
また、新聞(日経4紙、朝日、毎日、読売、産経)では、この用語はいっさい引っかかって来ません。検索対象を広げると、「日経公社債情報」でやっと一件ひっかかってきました。(おそらく)専門家の間では使われていても、一般の人にはまったく届かないタイプの情報の一つと言えるかと思います。
最近だんだんわかってきましたが、新聞や雑誌の方々は、「あ、その説明だと、うちの読者には難しすぎます〜」と、かなり低いレベルでフィルターをかけちゃうんですよね。先日も、連結財務諸表の教科書のはじめから3ページ目くらいに書いてあるような説明をご説明したんですが、「あれから部内で”読者には難しすぎるんじゃないか”とケンケンカンカンガクガクの議論になりまして・・・」ということになったり。
ここで想定されている「読者」は、数式で言うと「足し算」「かけ算」くらいまでならOKという方ではないでしょうか。だけど、足し算やかけ算でも(1+r) nといった「複利」とか「年金数理」的な要素が入ってくると、おそらくもうダメですね。
消費者金融で「複利」の概念がわからずに多重債務者が発生したり、牛乳やガソリンなら一円でも安い商品を探すのに、保険となると実質が何百万円も違うものを平気で契約しちゃったりするというのを見ても、「一般の人」のレベルというのはそういうレベルなんでしょう。
いわんやσとか√とかが出てくるものなんて、とんでもないわけです。
(以前も、「銀行のリスク管理状況、知ってます?」で、新聞では(日本で最も重要なことの一つかもしれない)金融機関のリスク管理手法についてはまったく記事になっていないということをお伝えしました。)
さらに。先日、テレビ局の方と話をしてたら、
「テレビって、”3つ”になるともうキツいんですよ。
『ホリエモンvsフジテレビ』というように2つの対決だと絵としてまだイケるんですが、北尾さんが出て来た時点でもうアウトですね。(笑)」
とのこと。
3つでもうだめですか・・・。orz
確かに、ブログ界でも「あいつはフジ派だ」「こいつはホリエモン派だ」と、人の属性を「1ビット」でしか区分けできない方がたくさん散見されましたので、「普通の方」が何かを2ビット以上使ってカテゴライズするちうのはかなりキツいのかも知れません。
また、テレビのアナウンス原稿というのは一分間にだいたい300文字だそうで。1秒間に5文字。2バイトコードとして5×2×8=80bps(・・・って、20年前のパソコン通信より情報量が少ないじゃん!!)
テレビって、数十Mbps以上送れる帯域を、すごくムダに贅沢に使ってらっしゃるわけですね。
VaR管理は「サラリーマン的」なのか?
ところで、このVaRショックというのは、「サラリーマン的」なんでしょうか?
私も不勉強でよく存じないのですが、さらっとあちこち見た感じでは、「個々の銀行にとっては合理的な行動が、社会全体としては大変なことになる」という(システミックリスク的な)例のようにも見えます。リスク限界の設定もBISとか制度的なものからある程度決まってくるものなのかどうか・・・。
ただ、そのもととなった判断のVaRモデルが、どこの銀行でも似たようなものであり、なぜ似たようなものかというと銀行員がサラリーマンだから、「他行でもこうやっております」てな感じで同じようなモデルやリスク限界の設定を採用したとすると、確かにサラリーマン的なのかも知れません。
思い出されるのは、確か87年のブラックマンデーの日に、当時の山一証券の大手町支店の店頭で株価が大暴落してるのを見て、私なんか(株も持ってないのに)「こりゃもう世界の終わりかー」と、(マンガでいうと額に縦の線が入っちゃってる感じ)だったのですが、毛皮を着た金持ちそうなおばちゃんが窓口の男性に向かって、
「ちょっとあんた、これだけ下がってるってことは買いなんでしょ?」
と、食い下がってるのを見て、「はー、世の中にはいろんな考え方の人がいるもんだなあ」と思ったわけです。
以前、「ネット投資家の参入による「新しい生態系」」で、以前は20%を超えていたTOPIXの推定リスク(日立製作所さんのRiskscope による)が、最近ではなんと10%を切る数値になってきたということをお伝えしました。つまり、ちょっと上がると売られる、ちょっと下がると買われるような市場になってきたんじゃないかということかと思います。
全員が一斉に「売りだー」という思考パターンにはまってしまうのは、市場としては非常にまずいわけでして、機関投資家が「売りだー」と思っても、それをまったく別の発想で買う人がいるというのは、「いい市場」ですよね。
全員が「長期ロング」ではなく、「いろんな観点」から短期で売買する人が増えてきたというのも、「いいこと」なんじゃないでしょうか。
以下、資料
前述の、日経公社債情報の記事が、「VARショック」という概念を理解する助けになると思いますので、ちょっと長めに引用させていただきます。
<郵貯のリスク管理新手法>「RaVEC」が始動。2004/12/27, 日経公社債情報
(略)
日本郵政公社が2004年度から完全導入した郵便貯金のリスク管理モデル「RaVEC(ラベック)」の詳細が明らかになった。大手銀行など金融機関が運用のリスク管理として広く導入しているVaR(バリュー・アット・リスク)が現時点での資産価値の変化だけを見るのに対し、これに将来の期間損益の変化も加えたCEVaR(Company Earnings and Value at Risk=企業価値変動リスク)を取り入れたのが特徴。VaRに比べ急激な金利上昇に対するリスク許容度は高くなり、試算では長期金利が4%台まで上昇しても保有債券の売却を迫られることはないという。(中原敬太)
金利が上昇した際に郵便貯金が抱えるリスクには、国債などの保有資産の価値変動と、定額貯金の預け替えに伴う将来損益の変動という2つが存在する。大手銀行や生命保険、損害保険など幅広く使われているVaRは、現時点での資産のリスク量に固定されているため、短期的なトレーディングのリスク管理には適しているが、将来の収益も含めた長期的なリスク管理には向かない。
これに対し従来、郵便貯金でリスク管理として使ってきたBaR(アーニング・アット・リスク)は、期間損益の変動リスクの管理はできるが、資産・負債の時価評価には対応できていない。
このため郵政公社では、郵便貯金にはこの両方のリスク管理を導入すべきと判断。VaRとEaRを組み合わせたCEVaRを採用したシステムを構築した。郵貯が商標登録した「RaVEC」はCEVaRを逆さにしただけだ。
具体的には、金利、為替、株価について1万通りのシミュレーションを実施してリスクを計算する。1万通りのうち、最悪95%値、つまりベストシナリオから数えて9500本のケースをリスク管理値とし、この場合に、P/L(損益)ペースで3年連続の赤字に、B/S(資産・負債)ペースで債務超過にならなけば、許容範囲として認められるという仕組みだ。
例えば、2004年3月末時点の資産・負債をベースに郵政公社が試算したリスク感応度を見ると、金利が0.1%上昇した場合のその他有価証券がB/Sに与える影響は1020億円のマイナス。
仮に長期金利が3%上昇したとしても資本に与える影響額は3兆円強で、期末の資本3兆6663億円の範囲内におさまる。同様に、為替は10円円高でB/Sに2650億円のマイナスの影響があるほか、株価は日経平均株価が1000円下がるとP/Lに2180億円のマイナスの影響があるとしている。
2003年の金利急騰局面で金融機関が債券売りを急ぎ「VaRショック」と言われたように、VaRは長期金利の上昇に対する許容範囲が狭い。これに対し、CEVaRは金利が大幅に上昇しても、リスク量の増え方が限られる。仮に量的緩和政策の解除によって長期金利が上昇した場合でも、郵貯が債券運用に大きな変更はない公算が大きい。
郵貯だけで約100兆円の債券を保有するため、金利上昇時のリスクを危ぶむ声も根強いが、こうしたリスク管理手法の導入により、民営化議論の渦中にある郵貯の安全性を強調する狙いもありそうだ。
(BaR(アーニング・アット・リスク)とあるのはEaRの誤植でしょうか。)
「こうしたリスク管理手法の導入により、民営化議論の渦中にある郵貯の安全性を強調する狙いもありそうだ。」とのことですが、この郵貯のシステム、日経公社債情報2件、日経ビジネス1件の3件しか記事になってないので、まったく「強調する狙い」がハズれてるという気もします。
以下、webの(数少ない)検索結果から主だったモノを
公的債務管理政策に関する研究会(第8回:2003年9月5日)
議事要旨(委員 本間 正明 座長、池尾 和人、富田 俊基、藤井 眞理子)
http://www.mof.go.jp/singikai/saimukanri/gijiyosi/ksk008.htm
それから、資料1にいう「VaRショック」のメカニズムについて解説して頂けないか。(中略)
VaRショックのメカニズムについては、6月までの低金利下において金融機関の国債保有が増加し、デュレーションが長くなっていた中、金利上昇による含み益の減少やボラティリティの上昇により、リスク・リミットを突破してしまったものと思料される。こうした問題は今後も発生し得る問題であり、銀行の貸出が減少し、国債投資が増加する中で、こうしたリスク管理手法やリスク・リミットの設定の仕方が適しているのかという点については、今後の課題といえるのではないか。
マーケットから見た公的債務管理政策について(2003年9月5日)
日興シティグループ証券債券本部 チーフ・ストラテジスト佐野一彦
http://www.mof.go.jp/singikai/saimukanri/siryou/ksk008_1.pdf
三菱証券「債券投資デイリー」(2004年7月16日)
金融市場戦略部チーフ債券ストラテジスト石井純
http://www.mitsubishi-sec.co.jp/houjin/s_report/souba/200407/16.pdf
� 相場変動の「加速度」がつきやすくなることで、昨夏のような“VaR 相場(VaR ショック)”が発生しやすくなる
三菱証券「債券投資ウィークリー」(2005年2月10日)
石井純チーフ債券ストラテジスト、長谷川治美シニア債券ストラテジスト
http://www.mitsubishi-sec.co.jp/houjin/s_report/fi_st/2004_2nd/st0210.pdf
98年末からの“資金運用部ショック”、03年夏の“VaRショック”による0%台からの金利急騰は、債券バブルの破裂と捉えられよう。
本石町日記(さん)
http://hongokucho.exblog.jp/2228748/
http://hongokucho.exblog.jp/1266032/
本日の日経金融(日銀、手探りの内部改革)は…
問題の本質が分かっていない。(中略)
また、ある委員は「現場に近い担当者を呼んだ方が実態をつかめる」と言っているが、今の日銀の問題は現場に聞いても実態が掴みにくい、ということだ。なぜなら、圧倒的量的緩和でインタバンクは死んでおり、掴むべき実態がない。また、情報収集において、両ウイングとも全般にアナリスト的ないしリサーチ的なアプローチを取る傾向が強く、個別情報の収集力が弱体化している。昨年のVARショック時には、現場からの情報では何が起きているのかつかめないため、企画関係者が自ら情報収集に動いた形跡すらある。
日銀の政策決定に関する情報の流れもどーなのよ、ということですね。
「若き知」(2004.3.30)久保田博幸氏
http://fp.st23.arena.ne.jp/keio/k0403.htm
昨年の債券市場におけるVARショックを見てもリスク管理は機械的にするべきものではない。マニュアルも必要かもしれないが、マニュアルで想定していないリスクに対処できなければ本当の危険は防げない。
西村信夫の「MNC」266
http://sv3.inacs.jp/bn/?2004070060427644014774.mnc
続・金融再編/メガ・バンク統合=VaR ショックを誘因か?
三菱証券・金融市場戦略部チ−フ債券ストラテジストの石井純さん(略)は、「MTFG とUFJ の経営統合でくすぶり始めた債券需給を巡る憶測」と題して、概ね次のようにコメントする——。
三菱東京フィナンシャル・グループ(MTFG)とUFJグループは、本日にも経営統合に向けた基本合意を正式発表するという(各種報道より)。債券市場は、世界最大の資産規模となるメガ・バンク統合が債券需給等に及ぼす影響を気にして、ざわつき始めた。そこで、それを“一般論”の範疇で、思考実験してみた。ポイントは主に次の4点だと思う。(以下、記述無し。)
J.B.A.掲示板
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9038/geobook_2.html
Mr.Bond – 04/01/30 16:07:49コメント:
都銀のバランスシートを見ると、03/7月に有価証券93.4(うち、国債54.1)兆円あったのが、債券市場が暴落した9月末には90.2(同、49.2)兆円と各々、△3.2(同、△4.9)兆円と、VARショックが輪をかけて大幅に減少しました。その後、11月には94.8(同、55.5)兆円と各々+4.6(+6.3)兆円と、残高だけ見ると都銀の債券ポートフォリオは復元されたように見えます。事実、日本証券業協会の投資家別売買動向を見ても、10〜12月累計で(長信銀も含まれていますが)3.2兆円の大幅買い越しになっています。ここで、良く考えてみてください。VARショックの後遺症はなくなったわけではありません。許容されるリスク量は、債券10年国で計算すると、6月ピークの6割弱しか保有することができません。にもかかわらず、債券残高が既に既往ピークを超しているということは、言葉を変えると「短中期債を大量に抱えて、少なくなった債券保有可能枠を使っている」ということです。そのために、昨年央の債券ポートフォリオの収益性に比べると、リスク単位辺りの収益性は著しく見劣りしていると言うことが予想されます。従って、債券相場が、1.5%台から1.2%台へ利回低下しても大きく相場を下げるような「戻り売り」が出てこなくなっているのだと思います。今年(=03〜04年度)は、恐らく大きな戻り売りができるような銀行は出てこないでしょう。むしろ、今まで債券ポートで業務純益の4〜5割前後を稼いできた収益を、これからはどこがカバーするのか注目されます(今の状況であれば、株の売却益に頼るしかないかもしれません)。有価証券部門でも、これからは達磨さんになって静かになるポートと、起死回生を狙って勝負に出る銀行と、2つのグループに分かれてくるでしょう。前者は意外に収益余力のある銀行で、後者は背に腹は変えられない、追い込まれた銀行が銀行の屋台骨をかけて一発勝負に出てくるのかも知れません。いま、私が予想する金融環境であればこれからは熾烈なサバイバル戦が始まろうとしているかも知れません。
(以上)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。