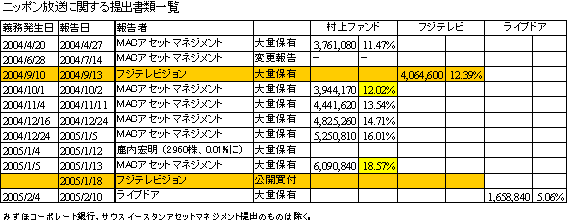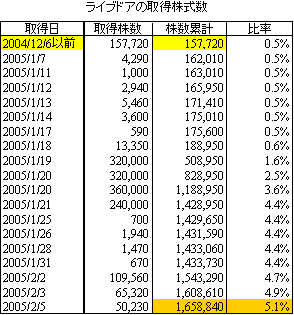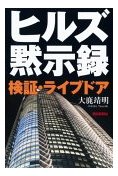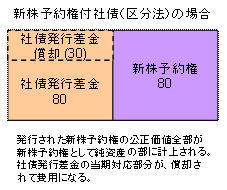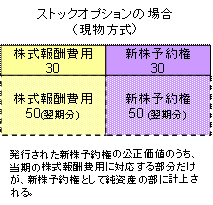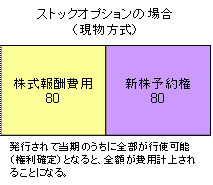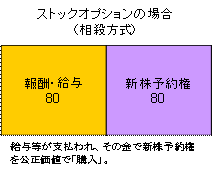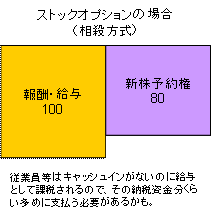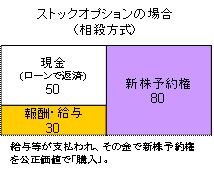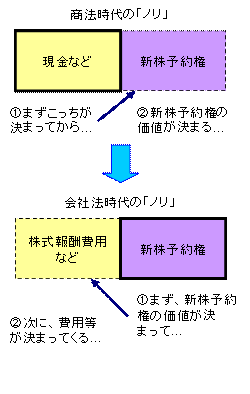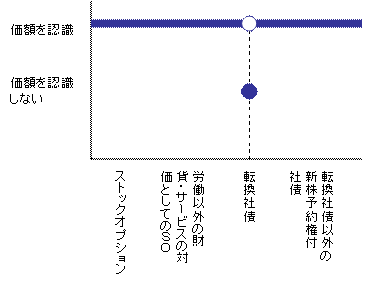マスコミでは、「ライブドアをケシカケたのは村上ファンド」「だから村上ファンドが悪い」的な報道が主流になりつつあるようですが、先にどちらが けしかけたかでインサイダー規制(167条)が適用されるかどうかが決まるわけではないですよね。
本日の読売新聞の記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060608-00000006-yom-soci
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060608it06.htm
によると、
25万株一気に購入、ライブドアから連絡あった日に
(中略)
関係者によると、ライブドア側の担当者は同年10月20日のメールで、「購入資金として200億円を用意する準備ができたので、会合の場を持ちたい」などと伝えていた。女性担当者は、この内容を村上容疑者に報告したという。ライブドアが用意しようとした200億円はこの当時、5000円前後で株価が推移していた同放送株の発行済み株数の約12%、400万株の購入資金に当たる。
ライブドア側の報告を受け、村上ファンドの投資顧問会社だった「MACアセットマネジメント」はこの日のうちに、同放送株を約25万株購入していた。MAC社の大量保有報告書によると、同ファンドは少なくとも同年8月以降は、10万株台の大量購入はしていなかった。
村上ファンドは、この日以降、11月4日に約17万株、同12日に約15万株などと断続的に大量購入を続けた。
とのことなので、ここまで読むと、「こりゃ村上ファンドは完全にインサイダー規制に引っかかってアウトじゃん」、と思いますよね。
(聞くところでは、M&AコンサルティングとMACアセットマネジメント[一任の投資顧問業者]の間にはチャイニーズウォールが敷かれていて、M&Aコンサルティングがインサイダー情報を取得するとMACに売買を停止するように指示が行ってインサイダー取引を防止する仕組みが構築されていた、という話もありますので、その両者の間でインサイダー情報の流通があった、ということを検察は別途立証する必要もあるかも・・・・ということは、さておき、)
一方、同記事によると、
ところが、12月に入っても、ライブドア側が同放送株をほとんど買い進めておらず、0・5%程度しか保有していないことを知った村上容疑者は、ライブドア幹部に「全然、買ってないじゃないか」と怒ったという。
とのことで、実際に買ってたのは村上ファンドだけで、ライブドアはこの時点までは「大量買付け」はしてないわけですよね。
メールの内容にもよりますが、10月20日でホントに「公開買付等の開始に関する事実」を村上氏が「知った」ということになるんでしょうか?
(記事の「怒ったという。」という文章には、「ライブドアが買うはずだったので村上ファンドも買い増したのにライブドアは買ってないじゃないか」という「期待はずれ」的ニュアンスが出てますが、村上氏はもともと普通の会話でも声がでかそうなので(笑)、怒ってるように聞こえた、というだけかも知れません。)
「共同買付者」ではないのか?
47thさんがおっしゃる「ライブドアと村上ファンドは『共同買付者』に該当するのではないか?」という可能性もまだ消えてませんよね。
ライブドアが買うと、5%を越えた時点で5日後に公表しないといけないわけですので、買い始めると市場が大騒ぎになるのは見えてました。が、村上ファンドはすでに10月時点で約12%を保有していたわけで、多少買い増しても怪しまれない。
ライブドアが後で引き取る可能性も前提に「共同で」購入して、ライブドアが食指を伸ばしているのをカモフラージュしようにした、と考えるのも筋が通ります。
「ライブドアの要請」に該当しないか?
また、47thさんの以前のエントリ(ブロック・トレードとインサイダー取引規制(2))の最後でも触れられていた、「(167条)5項4号」ですが、この条文では、公開買付者等(ライブドア)の要請により、あとでライブドアに売り付ける目的で村上ファンドが買い付けを行う場合には167条インサイダーの適用除外ということになっています。ただし、これには「ライブドアの取締役会が決定して」という条件が付いてます。
四 公開買付者等の要請(当該公開買付者等が会社である場合には、その取締役会が決定したもの(委員会等設置会社にあつては、執行役の決定したものを含む。)に限る。)に基づいて当該公開買付け等に係る上場等株券等(上場等株券等の売買に係るオプションを含む。以下この号において同じ。)の買付け等をする場合(当該公開買付者等に当該上場等株券等の売付け等をする目的をもつて当該上場等株券等の買付け等をする場合に限る。)
実際には、村上ファンドはライブドアの取締役会議事録を確認したわけではないでしょうから、これに該当するとしても(注意不足も含めて)真っ白でないのは確かですが、仮に、堀江・宮内・熊谷といった主要かつ取締役会の過半数のメンバーから「後で売ってくださいよ」といった要請を受けていたにも関わらず、取締役会の決議がないだけで懲役だとしたらキビシイですね。
マスコミでは、「後でライブドアに高く売り付けるために株を買った(ゆえに村上ファンド=悪人)」といった表現が使われているようですが、ライブドアの(取締役会の)要請によるものならむしろ逆に問題なかったはずです。そして、村上ファンド側はケアレスではあったものの、ライブドアの取締役会の決議により要請があったのとほぼ同様の実態を有していた可能性も高そう。
ライブドアはインサイダー違反ではないの?
スポーツ紙系の報道では、「村上逮捕はホリエモンの復讐」というような見出しで、「いっしょに経営権を取ろうと約束していたのに裏切られたので、検察に情報を提供した」というようなことも書かれているようです。
「いっしょに」ということだとすると、村上ファンドとライブドアは(少なくとも昨年の時点では)「共同買付者」だったということで、前述のとおりほんとに167条が適用できるのか?という気もします。
一方、「共同買付者であっても167条は適用される」という厳しい解釈を取るとすると村上ファンドはアウトなわけですが、昨年秋の時点で村上氏が「うちのファンドでも(5%以上)買い増していく予定だよ」「いっしょにやろう」とライブドア役員に告げていた場合には、ライブドアも167条違反、ということにならないでしょうか?
実際、大量保有報告書によると平成16年10月1日時点でのMACアセットマネジメントの持株比率は12.02%で平成17年1月5日に18.57%まで6.55%買い増してます。
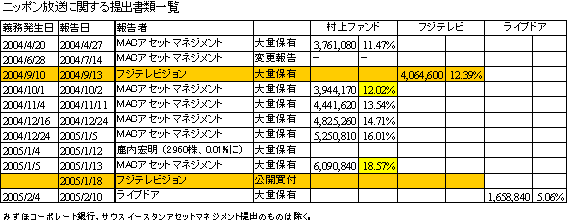
これに対して、「大量買付けを行うはず」のライブドアは、実際には1月中旬になってもニッポン放送株を約0.5%しか保有しておらず、本格的な取得を始めたのはフジテレビがTOBを発表した翌日の1月19日以降。(後掲の表ご参照。)
つまり、9月ごろから「いっしょに大量に買い付けよう」という話をしていたのだとしても、翌年1月までの間に「大量買付け」の事実が客観的にあったのは、どちらかというと村上ファンドの方の話。
両者ともニッポン放送株を買い付けていたのだとすれば、村上ファンドが167条の解釈上「黒」になるとするなら、ライブドアのほうがより黒になる可能性が高いんじゃないでしょうか。
村上ファンドよりライブドアの買い付け額の方がはるかに小さいですが、0.5%とはいえ10億円弱の金額になりますし、インサイダー取引というのは「額が小さいから許される」という話でもないです。
平成17年2月10日にライブドアが提出した大量保有報告書の「最近60日間の取得又は処分の状況」では、平成17年1月7日の取得がもっとも古い取得日として開示されており、合計株数と明細の差を取るとそれ以前に取得したものは157,720株。
その157,720株を取得したのは60日以上となる平成16年12月上旬より前、ということになりますので、その中に村上氏と緊密に連絡を取った時期以降に取得したものがあるとすると、ライブドアも167条違反である可能性が高くなりますね。
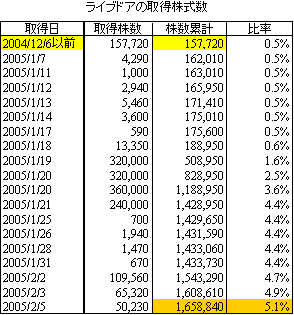
(追記:6/9、9:34)
大量保有報告書では、2004年12月上旬以前に157,720株持っていたことまではわかるものの、それらをいつから保有していたのかがわかりませんが、いただいたヒルズ黙示録
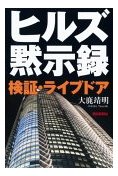
を読み返したところ、93ページに、
最初はライブドアの「純投資」として、いわば資産運用のつもりで前年の2004年7、8月ごろからニッポン放送株を買い進めている。ニッポン放送が最新の株主名簿を作成した2004年9月末時点では、0.1〜0.2%ほど取得していた。村上がどんなイグジットを考えているのか分からないが、とりあえず「提灯をつける」つもりで、見よう見まねで株を買い始めたのが真相だろう。
とあります。
株主名簿の名義と実際の保有株式数が一致しているとは限りませんが、もし一致していたとしたら、10月から12月上旬にかけて残りの0.3〜0.4%を買ったということになり、9月ごろから村上氏に「うちも買い進む」という旨の話を聞いていた場合には、ライブドアも同罪、ということになりえます。
(/追記)
つまり、ライブドアの役員の方々はまだ167条インサイダー違反では逮捕されてませんから、「復讐のため」に検察に情報提供したりしたら、自分にもさらに罪が加わっちゃう。ということは、「復讐説」というのは違うんじゃないですかね? 「毒食わば皿まで」ということか、あるいはそこまで深く考えてないということでしょうか?
(ではまた。)
付録:「言ったもん勝ち」について
ちなみに、先日のエントリで、「言ったもん勝ち」という表現を使いましたが、他のブログで「磯崎さんの言うとおり、聞いただけでインサイダーになるというのはおかしい」と多数引用されてるのを見て、誤解を招きやすい表現だったかも・・・と思っております。
「言ったもん勝ち」というのは「(実際には行うかどうか決まっていないようなどんなテキトーなことでも)言った方が相手の行動を制約できる、というのは、ちょっとねえ・・・」というニュアンスを込めたつもりでした。
つまり、わかりやすく例えれば、私が一昨年の10月あたりにタイムスリップして堀江社長に会って、「私、磯崎は、ニッポン放送の経営権を取得するために、50%超の株式を取得できたらいいなあ、と思ってるんです」と告げるだけでライブドアは株式を取得できなくなってしまうのか?また、私が「200億円程度なら調達できる目処が付きました」と付け加えたら、確実にアウトになるのか?というあたりですね。
「磯崎がそんな資金を調達できないのはあたりまえだが、ライブドアは可能性があった」ということであれば、どのへんの確かさがその境目になるのか?
もちろん、上記は私の頭の体操としての興味から考えていることであって、よいこのみなさんには、ぐっちーさんのおっしゃるとおり、「李下に冠を正さず」をオススメします。
(「光の中」を歩んでください。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。