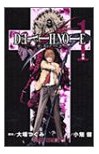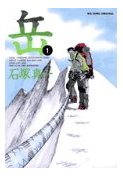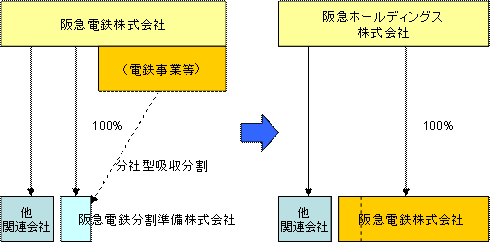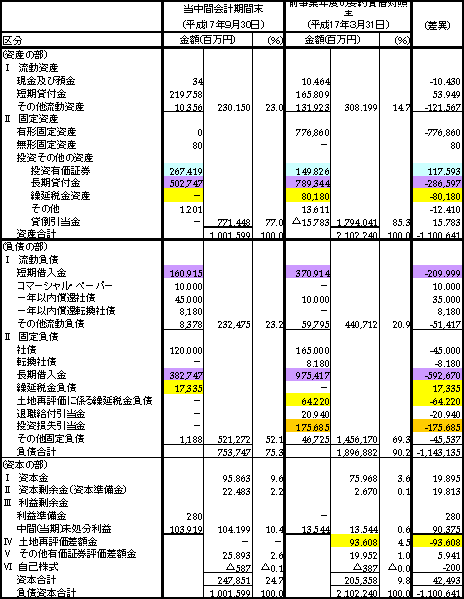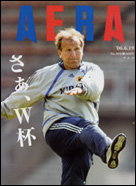村上ファンドとインサイダー取引の法解釈・運用をめぐって、各所で議論が繰り広げられてますが、当ブログでも、それについて何回かにわけて考えてみたいと思います。
インサイダー取引規制の複雑度
村上氏が逮捕された時に、マスコミやブログでも、「『プロ中のプロ』の村上氏ともあろうものが、なんでインサイダー取引のような初歩的な違反を犯したんだ?」とおっしゃる方々がたくさんいました。
確かに、「インサイダー取引が悪いこと」というのは「初歩的なこと」だと思います。が、では仮に、具体的事例に基づいて「これがインサイダー取引規制違反に該当するのかどうか?」と試験問題を出したら、テレビで「インサイダー取引がいけないなんて、私でも知ってますよ!」とおっしゃってたコメンテーターの方々等を含め、かなりの人が、落第点しか取れないんじゃないかとひそかに想像してるんですが。(私も、「条文持ち込みなし」で答えろと言われても、かなり自信がない、です。)
「プロ中のプロ」の金融機関等の人としゃべっていても、その方のインサイダー取引規制への理解度について「おやっ?」と思うことがしばしばあり、コンプラの指導をしている統括部門以外などでは、実は、かなり理解が怪しいんじゃないかと思ってます。
私がいつも愛読させていただいている、東証さんの
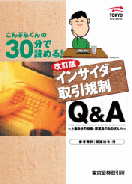
「こんぷらくんの30分で読める!インサイダー取引規制Q&A」
でも、166条、167条関係の証券取引法・施行令・内閣府令等の対比表になった条文だけで、B5版で50ページにもわたっており、「どこが『30分で読める』やねん!」って感じ。
(いえ・・・『30分で読める』とは書いてあるけど、『30分で理解できる』とは書いてないので、ウソではないです・・・。特に前半の解説部分は非常にわかりやすく、初心者にもオススメ。)
ただし、通常の金融機関や一般投資家の投資活動において、それが問題になるか、というと、ほとんどならないはずなんですね。
なぜかというと、通常の投資家は、そもそも他社のインサイダー情報に触れる機会も少ないですし、ぐっちーさんの「李下に冠を正さず」、あるいは、昨日ご紹介した小幡先生の「経済教室」(「法律にはグレーゾーンは存在せず、グレーゾーン取引はすべて違法取引だからである」)のように、通常の金融機関等においてはちょっとでも疑わしい取引については、取引自体を行わないような運用態勢をとっている(はずだ)からです。
つまり、図で書くと、
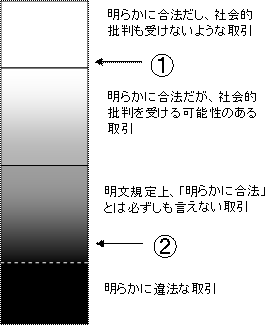
といった感じで、通常の金融機関等の運用は、上図の「1」あたりの「真っ白な」範囲までにとどめてる(はずな)ので、問題が起こる可能性は極めて低いわけですね。であれば、「インサイダー取引=悪」という程度の基本認識を持っていれば、業務には差し支えないはず。
一方、法治国家として、罪刑法定主義の観点から罪になるのは、明文上明らかに違法な領域と、条文解釈上違法と考えることも可能な、上図の「2」とかそのへんまでのはずです。
(注:合法性と社会的批判を2次元のマトリックスの図にしたほうがいいかとも思いましたが、ややこしいのでやめました。)
アクティビストの「受託者責任」とコンプライアンス
通常の金融機関やファンド等は、せいぜい議決権の5%未満程度の株式を保有するのが普通でしょうから、インサイダー情報に全く接しないような仕事の仕方をしていても、あまり大きな支障はないと思います。
一方で、(村上ファンドがどうかということはさておき、一般論として)、議決権の半数以下のそれなりの比率の株式を取得して、経営陣に経営改善や株主価値の向上の要求を突きつけるファンドを考えてみた場合、インサイダー情報にまったく接する可能性のないような「絶対安全領域」だけで活動して受託者責任が果たせるか、というと、これはちょっと無理だと思うわけですね。
保有する比率が低ければリスクも低いわけですが、例えば議決権の0.5%だけ株式を持って、サボってる経営者に意見を言っても、経営者が耳を傾けてくれるかというと、そんなわけない。
経営陣に要求を突きつけるわけですから、ファンドの運用者は経営陣と、経営統合や新規事業といった、仮に実行が決まればもろにインサイダー規制上の重要事実に該当するようなお話を積極的にするのがお仕事なわけです。
また、他にも大量に保有しているファンド等があれば、そうした相手の情報収集もしないで知らん顔してるだけで善管注意義務が果たせるかというと、そんなわけないと思うわけです。極めて大量の株式ですから、他の大量保有者の出方によってまったく情勢が変わってきますし、要求の方向性は一致していた方が、少ないリスク(保有比率)で、大きな成果が挙げられるわけです。
ボーっとして何もしないとか市場でちょろちょろ売っていくようなやり方で利益を十分に確保したexitができる可能性も低い。「落としどころを自らプロデュース」していく必要もあるわけですが、それらは「(仮に実行が決まれば)大量買付け等の事実」となることと隣り合わせなお話であるわけです。
ただし、もちろん、「明らかにインサイダー規制に該当する事実」を「聞いちゃった」(真っ黒な)場合には、売買等を停止しないといけないのは、当たり前のお話。
しかし、前述のとおり、「真っ白」な範囲だけで仕事してれば許されるという仕事でもないわけですね。明文で「OK」と決まっていること以外でも、例えば、弁護士等の専門家が、「違反とされる可能性が高いとは言えない」というような意見を出してきた事象について、「取引を一切停止」にすることが受託者責任として正しいとは言えないケースも往々にしてあるのではないかと考えます。
「そんなリスクが1%でもあるようなファンド、存在しなきゃいいじゃん?」と思われるかも知れませんが、
東証1部の上場企業の株式の時価総額だけで500兆円にもなるわけですから、そうした積極的な株主のプレッシャーによって「株価や利益率が低いままサボってると大変なことになる」と、経営者にも気合が入り、眠ってる資産その他のポテンシャルの活用に目覚めて、仮に価値が全体で1%上昇したとするなら、それだけで社会全体で5兆円も資産が増えるわけで、それは国民全体のプラスにもなるわけです。
(村上ファンドがどうかということはさておき、一般論として)、こうした株主価値向上の観点から経営者と積極的に関わりを持つプレイヤーが市場に存在することは、社会全体のために明らかに必要ですよね。そして、明文で合法であることが示されていなくても、合理的に考えて違法とはいいがたい行為であってファンドの利益としてプラスになる場合には、プレイヤーに課せられた受託者責任から考えて、その行為を選択しないといけないプレッシャーがかかる局面もあるんじゃないかと思います。
(続く)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。