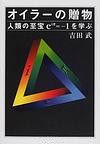ひさびさに、taka-mojitoさんからコメントいただきました。
磯崎さん、とんとご無沙汰しております。この夏からGoogle本社のご近所にきており、そろそろ日本のテレビ番組が恋しくなってきたもので「一人You Tube」に反応してしまいました。ぼくのために誰かにロケフリを設置してほしいくらいですが、「一人You Tube」でないといろいろ問題がありそうですね(実家にロケフリを設置するのであればセーフかもしれませんが。)。
おひさしぶりです。
先日、ひさびさにブログを拝見して、「あれ、海外に行かれたんだー」と思っておりました。
さて、ご存知かと思いますが、海外へのテレビ番組データの送信の適法性については、以下の差止請求に関する記事がご参考になるかも知れません。
「録画ネット」の事例
録画ネット社裁判記録
http://www.6ga.net/x_shiryo.php
「録画ネット裁判」で明らかになったタブー(2005/12/05)
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0512/05/news015.html
このサービスでは、ロケフリではなく、サーバーを使っていた、というところが一つのポイントです。
2004年7月30日に、NHKと在京民放5局から東京地裁に対し、「録画ネット(http://www.6ga.net/)」社のサービス停止を求める仮処分の申し立てが行われ、
2004年10月7日に、サービス停止の仮処分。
録画ネット側が異議申し立てを行うものの、2005年5月31日に、異議審で録画ネットが負け、2005年11月15日、知的財産高等裁判所でも、抗告棄却となったようです。
(録画ネット社のリリースを見ると、その後、録画「も」できるサーバーの販売サービスを引き続きやってるようですが・・・。)
この異議審の中で、決定は「業者側の管理・支配の程度等と利用者側の管理・支配の程度等を比較衡量して決するべき」、としてます。
この業者は、利用者に「販売」したサーバーをハウジングするという論理を取っているにも関わらず負けているので、この決定の論理で行くと、「ITに強い友人」などに頼んで金だけ払って機械の設置までやってもらうとアウトかも知れませんし、taka-mojitoさんが帰国された時に自分で設置して、ご実家の方も「ITには弱い?」場合には、自らが操作しているのでOKということになるのかも知れません。(後述の「まねきTV」のケースも参照。)
もう一つ、上記のITMEDIAの記事で、日本の放送局が仮処分申請したのも、オリンピックなどは、放映権の契約上、放送地域を日本国内に限定しなければならないから、としているところが「へー、なるほど」という感じです。
では、視聴者と放送局の関係(契約)において、国外への送信はどう扱われているのか。
民放の場合、民放と視聴者が契約してテレビ番組を見ているんではないと思いますが、NHKの場合、NHKと視聴者が直接契約しているので、この契約の中身が問題になるかも知れません。
NHK受信契約を味わってみる
ということで、子供のころからNHKにお世話になっているにも関わらず、生まれて初めて受信契約(規約)というものを読んでみました。
日本放送協会放送受信規約
http://www3.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/kiyaku_01.html
放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は,次の条項によるものとする。
以下、さらっと読む限りでは、「たとえ私的複製であっても、日本国外に複製データの転送等を行ってはならない」といった制限は書いてないようですね。
ただ、海外赴任される方が、実家にロケフリを置く場合に、受信契約をもう一つ締結する必要があるのかどうか、という論点はあります。
放送受信契約の単位
第2条 放送受信契約は,世帯ごとに行なうものとする。ただし,同一の世帯に属する2以上の住居に設置する受信機については,その受信機を設置する住居ごととする。
2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は,前項本文の規定にかかわらず,受信機の設置場所ごとに行なうものとする。
3 第1項に規定する世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい,世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。
4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は,部屋,自動車またはこれらに準ずるものの単位による。
5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置される場合においては,その数にかかわらず,1の放送受信契約とする。この場合において,種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は,次の順位で適用した種別の放送受信契約を締結するものとする。(以下略)
「子機」側の扱い
まず、私が自宅のロケフリ経由でNHKの放送を事務所で見る場合、事務所のパソコンは、受信規約における「受信機」に相当するのか?
ちなみに、私の事務所の区画には、ビルの共聴アンテナは来てませんし、(パソコン以外の)通常の概念でいうところの「受信機」は、事務所には存在しません。
パソコンや光ファイバー単独で「受信」をすることはできないので、これを「受信機」とするのは、ちょっと厳しいんじゃないかと思います。
法人が同居するオフィスの場合どうなる?
また、上記の第2項の主旨は、ビジネス用のスペースに設置されたものは、住居用とは別に契約しなさいよ、ということだと思いますが、「(略:事業者の場合、)放送受信契約は,前項本文の規定にかかわらず,受信機の設置場所ごとに行なうものとする。」ともあるので、(私の事務所のビル、場所柄、証券化SPCなどの法人が同じ事務所内に多数同居しているところがいっぱいありそうですが)、テレビが1台で同じ住所で法人格が10個ある場合に、「法人ごとに10契約必要だ」てなことは言われなさそうであります。
磯野家の場合は?
一方、第2条第3項には、「第1項に規定する世帯とは,住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい,」とあります。
「または」の後が、「独立して住居もしくは生計を維持する単身者をいい」と「or」条件になっているので、「同じ家に住んでても生計が別の単身者は、別に契約しろよ」、という趣旨だと思うのですが、じゃあ、「”マスオさん”のように生計が別で同じ家に住んでいるけど単身者ではない人は、該当しないか?」というと、当然、「磯野家とフグ田家で2契約してもらうこと」を意図しているはず。
なぜ「単身者」なんて言い回しをするんでしょ??
ロケフリ本体は「受信機」か?
第1条第2項には、「受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。 以下同じ。)」とあるので、ロケフリ本体自体は「受信機」に該当するんでしょうね。(「画面」は無くても、「受信」はしてるんでしょう。)
とすると、ご実家と「住居がいっしょでなく、生計も別」であろうtaka-mojitoさんは、当然、NHKの受信契約を、ご実家とは別に結ばなければならない・・・ように思われます。
事業者のカーナビやワンセグは受信料を払わないとあかんのか?
第3項を見ると、家庭用の場合には、「世帯構成員の自家用自動車等営業用以外の移動体については住居の一部とみなす。」とあるので、自家用自動車にカーナビについているテレビや、携帯電話のワンセグについては、別途受信契約は必要ないようです。
一方、第4項を見ると、「第2項(注:事業用)に規定する受信機の設置場所の単位は,部屋,自動車またはこれらに準ずるものの単位による。」とあるので、法人や個人事業で購入した(経費で落としている)車のテレビや携帯についているワンセグについては、それぞれ1台ごとに契約しなくちゃいけないんでしょうね。
事業者の方は、へたにワンセグ付きの携帯を従業員用に買ってはアカン、ということですね。
実際、大企業などは、休憩スペースごとのテレビとか、役員用自動車などのテレビごとに、NHKと受信契約を結んでいるんでしょうか?
まねきTV:ずばり「ロケフリ」を使ったケースの例
同じくITメディアの記事です。
ロケフリ利用の遠隔視聴サービス、中止求めるテレビ局の申し立て却下
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0608/07/news066.html
国内のテレビ番組をインターネット経由で海外などから視聴できるようにしたサービスが、テレビ局の著作権(送信可能化権)を侵害しているとして、NHKと在京キー局5社が業者にサービス中止を求める仮処分を申し立てていたが、東京地裁(高部眞規子裁判長)はこのほど、申請を却下した。
サービスは永野商店(東京都)の「まねきTV」。ソニーのロケーションフリー(ロケフリ)用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みエアボードを使って海外出張先から番組を視聴できるようにするもの。
同記事にあった、決定文のリンク
http://www.chronoworx.jp/maneki_tv/info/20060804.pdf
・・・・ということで、こちらは今年の8月4日に、業者の方が勝っているもよう。
多目的に使えるサーバーだと負けて、放送データの転送にしか使えないロケフリだと勝つ、というのが、非常におもしろい。
上記資料では、債権者(放送局)側の主張として、「海外の権利者から国内に限った放送としてライセンスを受けている」ので、「本件サービスのような事業が日本法上適法とされてしまうと」、日本の放送局にはライセンスしてもらえなくなるんじゃないか、みたいなことも主張されてます。
また、債務者(業者)側としては、
・ロケフリの保管は業者が行わなくても自分でもできること。
・ソニー自身が「海外在住者向けサポート」として、取付作業や環境設定を行っていること。
・ロケフリは、「社会的に好意的に受け止められている商品」であること。
などを主張しているところが面白いですね。
なお、債務者側が
(ロケフリ自体に、)CMをカットする機能がないので、債権者らのCMスポンサーの利益を損なうことがないこと
をあげてますが、さらっと読んだ限りでは、放送局側はそれについては何も言ってない模様。
HDDビデオメーカー自体にたいして「事を構える」のは、また別の戦略的判断が必要だということでしょう。(「チャプターを飛ばす機能は、放送事業者の利益を著しく損なう」と主張したら、HDDビデオの製造差し止めとかできるんでしょうか。CMを自動的にカットするのはまずいけど、チャプターを飛ばすのは、視聴者の勝手ですから、放送局も、それは厳しいと判断されているのかも知れません。)
弁護側は、藤田 康幸、志村 新、水口洋介、小倉秀夫の4名の弁護士の方々。藤田先生は、「法律業務のためのパソコン徹底活用Book」という本の原稿を書かせていただいた時にお世話になったんですが、他のみなさんもIT系にお強そう。
また、(そうは言ってませんが)、この製品を「ソニー」という企業が作っているところが、決定に大きく影響を与えたのは間違いないところでしょう。
ということで、「ロケフリ」の場合、今のところ「シロ」ということですね。
「まねきTV」のホームページ
http://www.manekitv.com/
を見ると、
NHK及び民放5社より仮処分申立却下決定に対する抗告が申し立てられました。
とのことですので、今後にも注目です。
まとめ
法律上の理屈はともかく、本件の本質は、このネットの時代に、何のプロテクトもかけずに放送されているコンテンツを、国境とか放送・通信といった区分で仕切ること自体、技術的にはほとんど意味が無い(「JM(記憶屋ジョニイ)」的世界だ)、ということでありましょう。
ロケフリやYouTubeは、そうした転換期に、そうした「矛盾」を気づかせてくれる製品であり、サービス、ということかと思います。
5年後、放送って、どうなっちゃってるんでしょうか。
(ではでは。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。