北朝鮮が核実験を実行しました。
今から10年ほど前の97年2月に、38度線を見てきました。
「その日」が、また近づいた気がしますが。38度線に行ったときのメモ(下記引用部分、一部加筆修正)をもとに、その時の感想を、ご参考まで。
−−−
前日にソウル市内で、韓国の某シンクタンクに勤めるK氏、先日まで東大で教鞭を取ってらっしゃった朝鮮半島問題専門家のおねえさま、先日金融庁を退職した(らしい)某氏と4人で、夜メシを食っていたときの会話。
(韓国は徴兵制なので、みなさん学生時代に38度線に行ってるわけですが、)
K氏 「私も徴兵された時に板門店は行きました。”北”の方からスピーカーでいろいろ言ってくるんですよね。」
私 「それって、『君たちはアメリカの傀儡政権に毒されている〜』みたいなやつですか?」
K氏 「いや、そういうんなら別に驚かないんですが、韓国の政界、財界の腐敗状況など、われわれが知らないようなことまで教えてくれるんですよ。いや、あれ聞いてると勉強になります。(笑)
われわれが行ったときも、『××大学のみなさ〜ん、お勤めご苦労様です〜』ってね。(笑)
何で我々が××大学から徴兵された部隊だって知ってるの?って感じですが、全部漏れてるんですよ。」
私 「それって・・・ソウルの相当深部まで”北”側の人が入ってるってことですよね・・・。」
同じ民族で戦っている、というのはこういうことなんですね。
−−−
(今もたぶん同じだと思いますが)、38度線にいけるのは外国人観光客だけ。(韓国の人は北に逃亡する恐れがあるということか、行かせてもらえない。)
ロッテホテルの前からバスが出発。基本的に、行くのは、日本人と(なぜか)オーストラリア人だけ。
バスで板門店に近づくに連れ、窓の外を行き過ぎる男達の顔が引き締まっていくのが、如実にわかる。緊張の中にいる人間というのは、かくも顔が引き締まってくるわけですね。
争いの無い中でへらへらと暮らしている人間とは顔つきが違う。
そのとき、「人は、恐怖と隣り合わせでないと美しくなれない生き物なんだろうか?」と思いました。
板門店に向かう平原の中の主要道には、山もないのに、ところどころ、コンクリートで作ったトンネルのような構築物があります。
ガイドさんによると、
「あのトンネルのコンクリートの中にはダイナマイトが仕掛けてあり、非常時にはあれを爆破することで、北からの戦車の侵攻を30分だけ食い止めることができます。」
との説明でした。
30分!
3日でも3時間でなく、30分。
そのわずか30分の間に、北がどうやってそれを乗り越え、南が戦闘態勢を立て直すために、何ができるのか。
朝鮮戦争時の戦闘を体験したからこそ思いつく仕組みなんだろうな、と。
−−−
北を望む板門店の丘の上に立っていたとき、ガイドさんが「有事の際には、あそこから北朝鮮の戦車が侵攻してきます」と説明。
朝霞の中を、その丘を越えて「キャタキャタキャタキャタ」と戦車の大群が侵攻してくるのを想像しただけで、全身の血の気が引いて、喉のところにグッとモノが詰まったような感じに。
「その時」に、自分が銃を持ってこの場に立っていたら、足がガクガクガクどころか、今までの人生で体験したことがないような恐怖を感じることになるんだろうなあ、と。
そう。朝鮮半島は、ただ「休戦」しているだけの「戦場」。
もちろん、戦闘状態にある戦場とはまた違うのでしょうけど、テレビで見て「戦場とは何か」を理解してたのと、「その場」にいるのとはまるで違うことが、(ほんのちょっとだけ)体で分かった気がしました。
“南”側の守りには、軍事境界線から幅何KmかのDMZ(非武装地帯)のすぐ後ろに世界最強の米第八軍がいます。
38度線からちょっと南の空軍基地で、F14だかF15だかが、24時間・365日、エンジンを回しっぱなしで待機してるわけです。
しかし、DMZの中には、拳銃以上の武器は持ち込めません。
ツアーのガイドさんは、
「有事の際には、後方の部隊が、45秒で軍事境界線(国境)まで到達できるように待機しています。」
と言っていました。
45秒!
しかも、後で説明をしにきた軍の広報担当者は、
「in thirty-eight seconds」
と言っていました。
訓練の成果で、記録は7秒縮まっていたようです。
(おしまい。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。

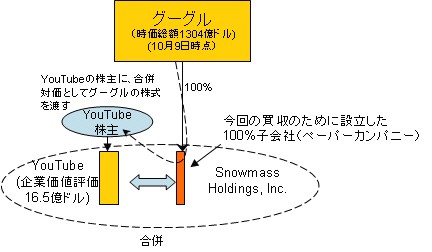
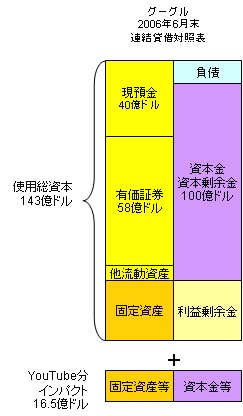

![FOMA_High_Speed_map[1].gif](https://www.tez.com/blog/archives/000767/FOMA_High_Speed_map%5B1%5D.gif)

