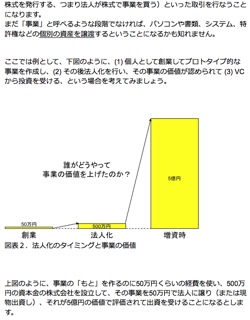本日12月26日の日本経済新聞朝刊16ページの、編集委員 渋谷高弘氏、村上徒紀郎氏による署名記事「社外取締役導入初の減少、上場企業、09年は9社減、1610社に」は、社外取締役の役割や事実関係について、いろいろ世間の誤解を招きかねない内容だと思いますので、コメントさせていただきたいと思います。
記事では、私が8月まで社外取締役を務めさせていただいていたカブドットコム証券について、
同社の特別調査委員会は「社長の経営管理上の問題があった。2人の社外取締役も社長をけん制する力が弱く、十分な機能を果たせなかった」と断定した。
とあり、社外取締役が2名しかいなかったようにも読めますが、実際には当時の取締役7名のうち、社長を除く6名全員が社外取締役でした。
特別調査報告書では、上記の社外取締役のうち、(なぜか)親会社である三菱UFJフィナンシャルグループの会長等を兼務していた方々を除く3名に対してのみヒアリングし言及しておりますが、私は、当時の社外取締役6名全員とも、社長を牽制する力が弱かったとは全く考えておりませんし、全上場企業の中でみてもかなりクオリティの高いコーポレートガバナンスを行っていたと考えております。
そもそも社外取締役は、基本的に単独で行動するのではなく、取締役会等の会議体を通じて社長や執行役を監督するのであり、また、社長の一挙手一投足を24時間監視しているわけでもありません。仮に、本件において社長が出したメールが問題だったのだとしても、そのメールを送信することまで社外取締役が監視できるわけもありません。
また、本当のワンマン社長なら、メールを出す場合に他人に相談なんかしないと思いますが、社長は特別委員会報告書にも記載されているとおり、他の役付執行役2名とメリット・デメリットを協議の上、メールを送信してるわけです。
すなわち、当時の社外取締役6名は、社長がワンマンで自分勝手に活動するのを見て見ぬ振りをしていたどころか、その逆に、社長が常に組織的意思決定を重んじて、重要な事項については前もって各社外取締役や執行役間で相談して行動する人間であることを確認した上で日常の経営を任せていたわけです。
記事には、「社外取締役が不祥事を防ぐという基本の役割」とありますが、これも読者に社外取締役の役割を誤解させる表現だと思います。社外取締役の役割の一つは、「会社の不祥事を防ぐための態勢が構築されているかどうかを監督すること」ではありますが、社長や従業員の一挙手一投足を24時間100%見張ることではありません。
これは監査法人や公認会計士における「監査の期待ギャップ」と全く同じ構造の話です。
「会計監査してるんなら粉飾や不正は100%見抜けるはずだ」という世間の期待に対して、会計士業界は何十年も根気よく「会計監査は、会社の取引の100%を抽出して行っているわけではないし、粉飾を100%完全に防げるものでもないんですよ」といったことを説いて来ました。
しかし、公認会計士が会計監査を主な本業とし、会計監査が正しく理解されなければメシが食えなくなる可能性があるのに対し、社外取締役の場合「社外取締役が本業」という人はほとんどいない。社外取締役に就任するのは、他社の経営者や弁護士、公認会計士など、多様な人々であり、「社外取締役全体」の品質を高めたり、社外取締役の性質やその限界を集団を代表して広報する機能は基本的には存在しないわけです。
記事では社外取締役が減っている理由についていろいろ解説してますが、社外取締役が減っている本質的な原因は、上記のように社外取締役全体を代表する広報活動も無い中で、この記事から垣間見えるようなマスコミの不勉強や過剰反応もあって、社外取締役のリスクが日増しに高まっているにも関わらず、就任するインセンティブが非常に小さいからではないかと考えます。
(ではまた。)
ご参考リンク:
カブドットコム証券 特別調査委員会報告書
カブドットコム証券社外取締役辞任について(コーポレートガバナンスについてのご参考)
池永朝昭弁護士のブログでのご意見について
池永朝昭弁護士のブログでのご意見について:その2
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。