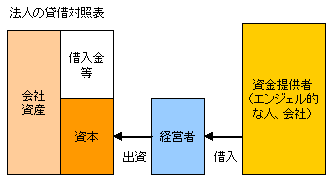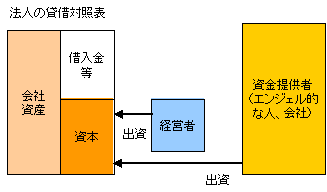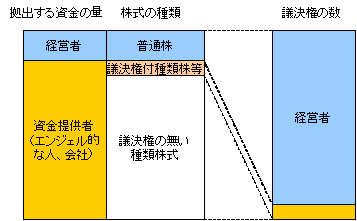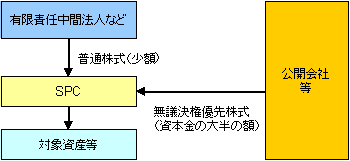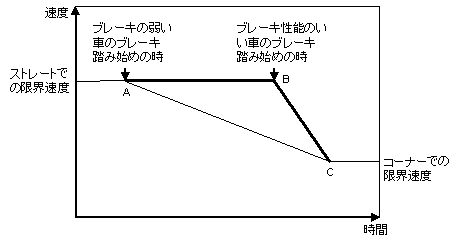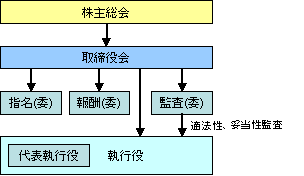「自己資金なしで(1円会社でない)会社を作る方法(種類株式の利用)」に、zerobaseさんからコメントいただきました。ありがとうございます。
ちょうどいま会社設立を考えているところです。いまは個人事業主なので。
1円設立だと法人成りできないとか、自分で数百万の資本金を用意するのは大変だとか、まさに実感してます。
とはいえ商法改正など待てないので来月にでも登記したい。ううむ。。。という感じです(汗
すでに事業を営まれており、そこで使っている資産が300万円以上の価値があるのでしたら、それを「現物出資」する、という手もあります。
また、パソコンや自動車などの「目に見える資産」でなくても、例えばすでにその個人事業の収益性が見えているのであれば、その「事業自体」の価値を評価して現物出資する、という方法も考えられます。
例えば、毎年200万円のキャッシュを今後5年間は生むと考えられる事業があれば、将来生むであろうキャッシュフローを年率50%(の高率)で割り引いたとしても、下表のように300万円以上になりますので、現物出資(だけ)で有限会社が設立できる可能性があります。
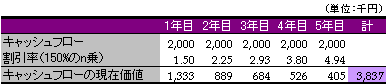
事業評価のポイントは、その事業計画に書いてあるキャッシュフローや利益等のほかに、過去の実績や実績を証明する帳簿がちゃんと残っているか、事業計画の妥当性や確実性などになります。
現物出資は必ずしも裁判所に検査役の選任を依頼する必要こそなくなりましたが、弁護士・会計士等の証明は必要です。(商法173条)。
商法は「資本充実の原則」を厳しく問うので、もし現物出資した財産の価値が証明金額を大きく下回る場合には、この現物出資の証明を行う弁護士・会計士等は、不足額担保責任や損害賠償責任が問われることになります(商法197条)。
ので、どの弁護士や会計士等に依頼しても、どんな事業でも評価してくれるということにはならないと思います。
ただし、将来的に年200万円程度のキャッシュすら生まない予定の事業なら、(「株式会社」とか「代表取締役」という名前が欲しい、というような「カッコ」の問題を除けば)そもそも法人化する意味があるんかいな?という話になりますので、客観的に見て法人化したほうがいい事業なら、資金が(あまり)なくてもほとんどの場合には法人化できる、と言うことができるかと思います。
ご参考まで。
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。