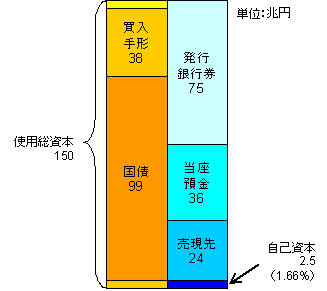6月号の(最近、表紙がちょっとおしゃれになった)M&A専門誌マール(MARR)に西村ときわ法律事務所の太田 洋弁護士による、「日本版ライツ・プラン−ニレコのセキュリティ・プランを中心に」という論文が載ってます。
小見出しを見てみますと、
・日本で第一号、米国と同じ基本構造
・株主平等原則に最大限の配慮
・コストの点で中規模公開会社に最適
・過渡的な事前予防策
・東証ガイドラインの扱いは疑問
とポジティブな感じで論旨が展開し、ニレコ型の特徴として、
� 一般的な米国型ライツ・プランで設定される(買収者だけが権利を使えない)差別的行使条件を備えておらず、株主平等原則に最大限に配慮している
� 社外有識者が判断
� 株主総会決議やSPCの設立、信託・信託管理人の設定といった複雑な手続きがいらないので、中小規模の公開会社に有力な選択肢
� フジテレビの事前予告スキームはTOBの手続きを経ない買収者には対処が事実上不可能だが、ニレコ型はOK
� 税務上も、インボイスの新株予約権の全株主への割当についての東京国税局の2004年11月11日付の回答に照らすと、(信託型がSPCに対する新株予約権の発行時や分配時に課税が生じる可能性があるのが課題であるのに対し)、ニレコ型ではこの点が相対的に問題が少ない。
の5つをあげています。
また、論文の最後も、
ニレコ型ライツ・プランの実効性やその副作用に対する最終的な評価は、いずれにせよ今後の歴史に委ねられることになろうが、いずれにしても、乱用買収に関する事前予防策の必要性が叫ばれる昨今の状況下において、我が国の企業にありがちな横並びの悪弊に染まることなく、事故の選択と責任においてこの問題に一つの回答を示したニレコの在り方は、他の公開企業においても参考となる点が多いものと思われる。
と、非常にポジティブな感じで締めくくられています。
途中、「いくつかの欠点が存在することは否めず」というような表現は出てくるものの、具体的にその欠点が何なのかはほとんど一切書かれてません。
「株主平等原則に最大限に配慮」といいつつも、新株予約権は3月末の株主に割り当てられるので、万が一このセキュリティプランが発動されると、4月1日以降に株式を取得した株主もトバッチリを食っちゃうというところが最大の問題点ではないかと思うのですが。
−−−
上記の論文には書いてありませんが、5月12日の日経新聞夕刊7面の記事(見落としてましたが)で、太田弁護士がニレコ方式の発案者であることがすでに公になってたんですね。
M&A精通、経験フル活用、日本初の毒薬条項を考案した弁護士太田洋氏(フォーカス)
産業機器のニレコが導入した日本初のポイズンピル(毒薬条項)を考案した。短期的利益のために資産を切り売りされるような買収から会社を守りたいとの要請に「経営者の保身とは違うと感じた。事業を守る防衛策はあって当然」と支援を請け負った。
M&A(企業の合併・買収)関連の陣容が厚い西村ときわ法律事務所の弁護士。学生時代、黒船などと騒がれた「ピケンズ事件」で小糸製作所の防衛に奔走する西村の弁護士の姿をテレビで見て事務所の門をたたいたという。
案件が少ない時代からM&Aを多く担当。(中略)二〇〇一年には任期付きで法務省へ。新株予約権導入など商法改正に携わった。三月末の株主に予約権を大量発行する今回の防衛策は、導入にかかわった制度を実地で使うやりがいもあった。
一時点の株主のみに予約権を発行するニレコ方式については証券取引所が「不適切」と自粛を要請。一部株主に発行差し止めを求める動きもある。先駆的試みだけにすんなりとは通らない格好だが「買収者だけ自由ではアンバランスで、現行法枠内で考えるとこうなる」と淡々と話す。
(おおた・よう=37歳)
ちなみに、差し止め仮処分申請をしているのは、5月10日の日本経済新聞朝刊によると、
ニレコの発行済み株式約六・八%を保有する投資ファンド会社、ザ・エスエフピー・バリュー・リアライゼーション・マスター・ファンド・リミテッド(英領ケイマン諸島)。
とのこと。
本日の日経朝刊には、
ポイズンピル(毒薬条項)発動の是非を勧告する特別委員会の三人の委員のうち、山田秀丸社長を外したと発表した。新たな委員には最高検察庁刑事部長などを歴任した高野利雄弁護士を選任した。
社長の参加で勧告内容が企業側の思惑に左右されかねないとの指摘が多かったため。十日に大株主の投資会社が新株予約権の発行差し止めの仮処分を申請しており、委員を第三者に限定して仮処分の結果を有利に運びたい考えとみられる。
ともあります。
新株予約権の申込期間は来週5月25日までで、発行日が6月16日。
果たしてこの新株予約権、発行できるのか否か。(わくわく)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。

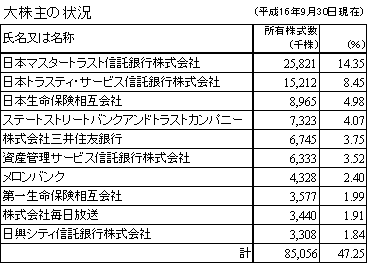
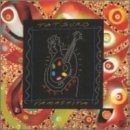

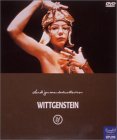
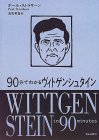
.jpg)