(タイトルのみ)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。

(タイトルのみ)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
東京地裁がニレコの新株予約権の発行を差し止めましたね。
本日の日経一面によると、
決定理由で鹿子木康裁判長は、買収防衛の予約権発行は「株主総会の決議が原則」と指摘。ただし(1)株主総会の意思が反映される仕組みがある(2)取締役会が恣意的に防衛策を発動することを防止できる(3)買収と無関係の株主に不測の損害を与えない——という条件を満たす場合は、取締役会による決定も許されるとした。
そのうえでニレコの場合は、六月の総会で株主の意思を確認する手立てを設けていないうえ、予約権行使の発動に関する特別委員会の勧告に取締役会が従わない余地があると判断。「株式希釈化などのリスクで既存株主が不測の損害を受ける」ことも考慮し、「取締役会決議による事前の買収対抗策としては相当性を欠く」と結論付けた。
3面によると、
ニレコは高裁が示した条件に加え、従業員や顧客、取引先など利害関係者の利益にならない場合も防衛策を発動するとしていた。今回、東京地裁は「取締役会の恣意的な判断を防止する判断基準とするには広すぎ、明確性を欠く」とした。
ニレコ以外でポイズンピル導入を予定する西濃運輸やイー・アクセス、TBSも従業員や取引先に悪影響を及ぼすかどうかを防衛策発動の判断基準としている。地裁の判断に沿えば、三社のケースは取締役会の恣意性が残る仕組みとみなされる可能性がある。
M&A(企業の合併・買収)に詳しい石綿学弁護士は「経産省の指針では、買収者が十分な情報を提供しない場合なども防衛策を取ってよいとしているのに、東京地裁は防衛策を取れる範囲を極めて限定している」と指摘。別の弁護士も「許されるのが有事と同じ条件ならば、事前型防衛策を導入する意味がなくなる」と疑問を投げかける。
とのことです。
今回の場合、「(3)買収と無関係の株主に不測の損害を与えない」という点が最も引っかかった点であるのは間違いないんでしょうけど、社外取締役等が企業価値が毀損するかどうか判断する「のりしろ」部分までトバッチリを食ったということでしょうか。
ライブドア−ニッポン放送のケースで、裁判所は「企業価値の判断はしない」というスタンスを打ち出したわけですので、社外取締役等の判断にある程度任せていただけると思っているのですが・・・企業価値が毀損するケースを事前に明確に列挙できるわけはないですし・・・。
前回・前々回の47thさんのご指摘のとおり、訴訟(裁判所の判断)によって差し止めされる可能性が残っていることが「フェアさ」の証でもあるということだとすると、今行われているのは、裁判所と社外取締役等との判断権限の縄張り争いの綱引きと考えられるかも知れません。
日本の現状だと、社外取締役、圧倒的不利って感じもします。
社外取締役の少ない会社が、委員会を作って取締役でない識者の先生等を入れたとしても、その方々の判断というのは(独立はしてるかも知れませんが)、訴訟されるリスクも小さそうなので、一般的にどこまで気合いを入れて判断していただけるものなのか、という点もあるかと。
買収防衛策を導入する会社が、取締役会の社外取締役比率を上げていく、なんてことをする動きが急速に広まるという感じもしません。
結局、社外取締役による経営監督という事例と実効性の認識が広まらないと、「なんでもかんでも裁判所にお伺いを立てる」ということにもなりかねないですね。
日経金融の3面にも解説が出ています。「さらに信託活用の動きが増えそうだ」という論旨で、「大手信託五行によると、上場企業が五行に寄せた相談は三月末で八百件超」とのことで、
西濃運輸が導入したのは、SPCを経由せず信託銀が予約権を引き受ける直接型。効果は同じだが、SPCの設立、管理コストがかからない。個人にとっては税制上の利点もある。通常は予約権取得時に所得税がかかるが、直接型だと予約権を行使して株を取得した時点で初めて税金がかかるため、課税時期を先延ばしする効果もある。
SPC型はそもそも、信託銀が株主に代わって直接予約権を引き受けられるか法的にあいまいだったため開発された。だが、直接型も金融庁から認められた。今後は直接型の利用が主流になる可能性が大きい。
と、今後は信託型でしかも直接型の利用が増えるだろう、と予測されてます。
課税については、以前申し上げたように、信託型で新株予約権を配る買収防衛策の場合、新株予約権が手元に来てから行使するまでの期間は非常に短いので(年末をまたがない限り同一課税年度)、直接型の方が課税時期を先延ばしする効果があるとまでいっていいかどうか。
また、コスト面ですが、
信託銀は「投資家、株主の理解を得やすい信託型への注目がさらに集まる」と期待しており、ポイズンピル信託が信託銀の新たな有力収益源となる可能性が出てきた。
とのですが、信託銀行というのは一行で数千億円規模の収益があるわけですから、その「有力収益源」ということは、業界全体で少なくとも数百億円の売上増が見込まれるということでしょうか?信託型を導入するのが上場企業1000社としても、1社あたり年間数千万円?
やはり、導入企業側からすると(SPCの設立運営コストどころじゃなく)コストがかかるということかも知れませんね。:-)
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
最終的に株主に分配できる分については、タイミング的に一瞬生じる部分をどう考えるかというところだと思うので、問題はやはり手残り部分でしょうねぇ。手残り部分の発生を防ごうとすると、事前に受益権者である一般株主の所在確認や受益の意思表示確認が必要になるので、新株予約権を直接配る場合と実務的に差が少なくなるのかなという気もします。
西濃運輸さんの場合、「新株予約権の交付を受けられる株主の皆様を特定する基準日を設定するために、株式分割や(法令・定款上可能となった場合には)剰余金の分配等を行うこともありますので、その場合、当社が別途ご案内する内容に従い、基準日に間に合うように名義書換手続をして頂くことになります。」というようなことが書いてあります。
株券に変えてから配る方式にすると、(そこが信託さんにお願いするメリットというか)、株式分割の子株を株主に配る事務フローとまったく同じフローに乗せられるのかなと単純に考えてました。(下図のようなイメージ。)
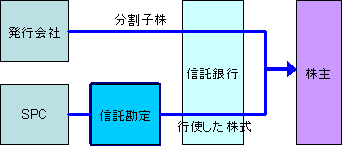
そういえば、(あまり深く考えたことなかったですが)、通常の株式分割で子株を株主に配る実務で名義人にうまく届かずに「手残り?」が出ちゃった場合というのは、どうしてるんでしょうか。
それは発行会社の「自己株式」になっちゃうのか、信託銀行さんで預かっておくなどして、後から株主が名乗り出てきたら渡す等の対応をしていただけるのか。
(どなたかご存じの方がいらっしゃったら、ご教示いただければ幸いです。)
あと、差止訴訟があるというと多少ネガティブな印象があるかも知れませんが、差止め段階で争われるのであれば、負けても会社としてはプランを撤回すればいいだけで、会社にはほとんど「損害」がないので(プランの設計や維持のコスト?)、代表訴訟で取締役の個人責任が追及される可能性が少なくなるという面では、実は有時の取締役の法的責任という観点からも望ましいところがあるんですよね。
信託が新株予約権を行使しようとしたときに差止訴訟がありうる、ということですよね?
「防衛できない可能性が増えるがフェアである」と。
武器商人が「どんな矛にもつらぬけない盾」を売るのは、まさに「矛盾」ってことでしょうか。
どうもありがとうございます。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
47thさんに、またコメントいただきました。
鋭い切り返しにたじたじなのですが、
またまた、なにをおっしゃいますやら。
しろーと相手に遊んでいただいて、ありがとうございます。<(_ _)>
SPCの指図で自己株を持っていいのか?
SPCに議決権を指図させるという話で、一つ論点があるのを思い出しました。
というのも、中間責任法人をかませれば、実質的に発行会社が出所となった資金で株式が取得できて、おまけに議決権も行使できるということになると、自己株取得規制を無効化できてしまうんじゃないかという話もありそうです。
なるほど、一般論としては有限責任中間法人をもたせて株を宙ぶらりんにすることができるので、おっしゃるような危惧がなくもないですよね。
ただ、今回の(例えばイー・アクセスさんの)スキームのような場合には、どうでしょうか。
私が、新株予約権でなく最終的なブツである株式自体を株主に交付してしまう方法でイメージしてましたのは、平時の際には、
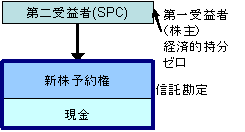
と、信託に預けられている資産は経済的には第二受益者であるSPCのモノになっているという感じ(この絵では、新株予約権の行使を予定して、鮭の稚魚のようにおなかに現金[数百万円程度を想定]をかかえてます。)で、
有事になって「基準日」が設定されると、
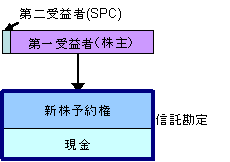
といった感じで、第一受益者である「基準日現在の株主(ただし新株予約権の条件に従い新株予約権を行使できない特定株式保有者等は除く)」に経済的価値が移るという感じのものです。
(注1:このとき同時に「時価」を基準に、第一受益者に課税所得が発生。)
(注2:信託型の場合、その後の株式発行等を予定して、多少多めに新株予約権を発行しておかないといけないと思われますので、第二受益者であるSPCの持分も残ってます。)
ここで、第二受益者であるSPCの指図をトリガーとして、信託が新株予約権の行使を請求。
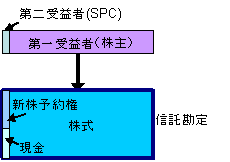
これであれば、(トリガーはSPCが引くにしても)、「株式」は経済的には第一受益者である発行会社の株主に保有されているわけですから、自己株式保有と同様の(経済的)問題は起こっていない気がします。
買収防衛策の「フェア」さ
なぜ、信託型が「好み」ではないかということについてはエントリーを書いてみましたので、よろしかったらご覧ください。
こちらですね。
信託型ライツ・プランと「好み」
http://www.ny47th.com/fallin_attorney/archives/2005/05/post_17.html
以下、一部引用させていただきますと、
「出口」での審査をどうするのか?
もう一つ、私の「好み」でない理由が、「出口」での審査がどうなるかが、今ひとつよく分からないところです。
「出口」というのは、買収防衛策の導入を「入口」に譬えて、実際に買収がなされた段階でプランを消却するかしないかという判断をする場面のことを指します。
信託型の場合、「入口」(導入時)段階で新株予約権をSPCや信託に発行する段階では不公正発行差止めという形で裁判所の司法審査に訴える余地があるのですが、買収が具体化していない段階では「そもそも取締役が買収防衛をするのは何事か」とか「仕組みとしてできが悪い」といった争い方しかできないので、今ひとつ身のある議論になりにくいところがあります。
そこで、実際に買収者が現れた「出口」段階での司法審査というのが、本来は重要になってくるはずなのですが・・・信託型の場合、誰に対して、どういう訴えをすればいいのか、今ひとつ分かりにくいところがあります。
「分かりにくい」というのも煮え切らない表現ですが、100%「できない」というわけではないものの、会社側の措置が適切かどうかという実体面での争いに入る前に、手続的な面で訴えの組み立て方や適法性にいろいろな論点があって、買収者が経営陣の判断を法廷で争おうとしても、そうした手続的な部分で「門前払い」をくらってしまう可能性があります。
つまり、信託型は一度導入してしまえば、後で具体的な買収の場面で経営陣の判断にチェックをかけるのが難しい構造になっているように思われるのですが、多分、逆にこの「法的安定性」というのは信託型のセールスポイントにもなっているんじゃないかという気がします。
心情的には、「実際に買収者があらわれたときに、消却の判断の適切性について訴訟で争われるかも知れない」というのは、依頼者(=経営陣)の立場からすれば居心地が悪いというのも分かるのですが・・・個人的には、むしろ「出口」段階でいい加減な判断をしたら裁判で負けるかも知れないという緊張感が自己保身目的の買収防衛策維持に対する抑止力となるべきじゃないかと思っているので、信託型は「好み」ではないところがあるわけです。
私も、特にSPC型だと有限責任中間法人という「宙ぶらりんな第三者」の存在を利用しているので、「その”第三者”が何をやろうが勝手だろ?」という論理に持って行かれると敵対的買収者がポイズンピルを解除しにくそうなので、そこがよさそうだな、と思っていたのですが、
逆に、「どんなときも訴訟で争うことができることがフェアなのだ」というお考えなわけですね。
(なるほどなるほど。)
随伴性のある?プラン
で、私の「好み」のプランというところなんですが、外野でわいわい言っていたつけがそろそろ回ってきそうな感じです・・・
(わくわく)
期待しております。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
47thさんから早速トラックバックいただきました。
信託型ライツ・プランは、「個人的にはあんまり好みではない」とのことですので、早く、47thさん「お好み」のプランを日本の法律の下で”実装”するとどんな感じになるのか知りたいなあ:-)、と思っております。(わくわく)
私も、当初、信託型に直感的に持っていた印象は、
・ 信託銀行を介在させないといけないので、(不動産流動化などで信託受益権を使う場合に発生する信託報酬やリーガルフィー等のオーダーから考えると)、結構コストが高くついちゃうのかなあ?、とか、
・ SPCや信託といった(会社と株主以外の)第三者が介在するので、税務上、ややこしいことになりそうだなあ、とか
いうような感じのものでした。
ただ、今回、2社のスキームを拝見させていただいて思ったのは、以下のような感想(印象)です。
まず第一に、日本だと、実務上、こうした株式に関する事務を行う事態になった場合には、何らかの形で証券代行(≒信託銀行)さんのお世話にならないといけないはずで、「ライツプラン(ポイズンピル)は実際に使われることはまずないはず」と言っても、いざ実際使うことになったら事務が破綻するということではそこがライツプランの弱点になりかねませんから、どのようなスキームを採るにせよ、あらかじめ信託銀行さんとかなり綿密な打ち合わせをしておく必要はあるはず。
めったにあることじゃない複雑なモノだけに、「バックアップサービサー」じゃないですが、少なくとも「有事」の際にそれなりの体制(お客様問い合わせ窓口等も含め)を展開できて、株主名簿との連携もうまく取れて、法務知識もあるアウトソース先というのは信託銀行さん以外に考えにくいわけで。
今年はドサクサなのでライツプラン関係のフィーが高騰してる・・・かどうかはさておき、ドサクサ的要因が落ち着いてくれば、信託型のスキームそれ自体にはそれほど高コスト要因は無いのかな、という気もしてきました。
第二に税務上も、(例えば「時価」をどう考えるかが読めないといった)不確実な部分はあるにせよ、「理論上」はそうしたいくつかの部分がクリアになれば、(当初危惧していたような)御無体な税金が当事者のだれかに課せられることはあまりなさそうだなあ、という感じもします。
ということで、「注:以下、本当に「即興」ですので、裏はとっていない点あしからず」とのことではありますが47thさんにコメントいただきましたので、私も脊髄反射的に、感じたことをコメントさせていただければと思います。(以下、太字の見出しは47thさんのもの。)
業法上の問題?
まず、考えられるのは銀行法と独占禁止法上の株式保有規制ですかね?
銀行法と独占禁止法で、確か銀行は5%を超えて事業会社の株式を保有できなかったはずで、仮に信託銀行がライツを自ら行使すると、ここへの抵触が問題となってきます。
もっとも、例外的に、受託者として保有している株式で、議決権行使について受益者の指図に従うこととなっているものであれば、この5%算定の枠の外になっていたと思うのですが、「一定基準日における不特定多数の株主」を受益者とするときにも、この例外が適用されるのか?、とか、受益者が特定できなかったり、諸事情で受益者への分配ができなかった株式はどうなるのか?、といったことを考えると、信託銀行が自ら行使するというのは難しいような気もします。
例えば、イー・アクセスさんのリリースの「信託契約の要項」によると、
3. 受益者
第一受益者:基準日現在の株主(ただし新株予約権の条件に従い新株予約権を行使できない特定株式保有者等は除く)基準日は、特定株式保有者が出現したことを会社が公表した後に設定し、公表する。
第二受益者:委託者
とあって、SPCが「第二受益者」というのになっているようです。
信託銀行が信託に基づいて自ら行使するのではなくて、SPCが指図して行使させれば、問題ないような気もするのですが。(←裏取りなし。)
投信法との関係
もう一つすぐに思いつくのは、投信法との関係です。信託に行使価額相当額の金銭を委託して、これが行使価額の払い込みに充当されると、投信法にいう投資信託に該当する可能性が出てくるような気がします。
このリスクそのものは、新株予約権という金銭以外の財産を信託するSPC型ではない直接型にもあって、直接型について、一応お墨付きが出ていることからすれば、程度問題という側面もあるのでしょうが、厳密にいうと別の種類のリスクということになってくるような気がします。
ヨーロッパでは、「信託」は十字軍以来の(「法人」より長い)伝統があるとかで、頼めばなんでもやってくれそうなオーラを醸し出していますが、日本だと(昨年改正されたとはいえ)まだいろいろ使いにくいんでしょうか。
SPCが行使価格相当の(少額の)キャッシュを持っていて、有事の際にはSPCが信託勘定に振り込んで行使を指図するというのでも信託法に引っかかっちゃうでしょうか。
開示規制?
理屈の上では信託型の場合には、一般株主に分配するものとして受益権(指図権)、新株予約権、株式という3つがあるのでしょうが、株式の分配の場合は証取法上の売出し規制との関係を考える必要があるように思います。
これは、本当は新株予約権自体の分配のときにも同じなのですが、発行価額と行使価額の合計が1億円未満に抑えていると違う状況になるのかも知れません。(実は昔考えたときには、行使価額1円というのは、余り考えていなかったので、この点は詰めて考えたことがありません)
「時価」ベースでいくと新株予約権をタダで配るのも株式をタダで配るのも同じような気がしてましたが、「売出し」の定義である「50名以上の者を相手方として、均一の条件で、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合」というのを字面どおりに解釈すると、一方的にタダで新株予約権や株式をあげちゃう行為は「売り付け」でも「勧誘」でもない気もします。
「信託勘定の中」で第二受益者から第一受益者に経済的価値がやりとりされたのか、SPCから株主に「証券の譲渡」が行われたと見るのか、というのも信託のミステリアスな部分ですね。
手残株の処理?
机の上では、信託銀行が株式を引き受けるといっても、それは一時的なことで、最終的には全て一般株主に分配されることになる「はず」です。
しかし、実際には名義書換失念株、所在不明株主、外国株主etc・・・で、信託銀行の手許に株式が残ってしまう可能性があります。
この場合の手残株をどう処理するかというところで、自己新株予約権の取得や消却と違って、相対による自己株式の取得については会社法上厳しい手続的規制がかかってしまいます。
というわけで、株式の場合「残ったから消してしまいましょう」というわけにはいかず、手残り株の処理やその間の議決権や配当受領権の処置という困難な問題が残ってくることになりそうです。
逆に、前回述べたように、何かの理由(長期に不在にしていた、郵便物が書類の山に埋まっていた、病気になってどたばたしていてそれどころじゃなかった、等)で期間内に新株予約権を行使できなかった一般株主がいたとした場合、(買収者だけでなく)その人にも非常に大きな損失が発生しちゃいますが、すでに株式が発行されていれば、そうした人の救済もしやすいのかなあ、と思ったりもしました。
税務上のインプリケーションの違い?
最後に、これは本当に直感的なものなのですが、信託レベルで行使する場合には、莫大な額の行使益が一時的に認識されるわけです。磯崎さんは、すぐに無償分配すれば、損金で相殺できると仰るのですが、寄附金認定されてしまうと益だけが残ってしまう形になってしまうような気がします。ただ、この問題は、新株予約権の場合にも同様の問題は生じ得るので、理論的に見れば、程度問題なのですが、市場価格のついている株式と、一義的な時価算定の困難な新株予約権では実務的なリスクは変わってくるような気もします。
この点は、先日の国税庁の自民党向けの資料において、
契約条件によりSPCに寄附金課税は生じない。(注:�[行使時]の時点の時価と�[付与時]の時点の時価との差額が譲渡損益と認識されるとともに、�[行使時]の時点の時価が費用・損失と認識されることから、結果として、�[付与時]の時点の受贈益に見合う費用・損失が生ずる。)
と書いてあるので、今のところ寄付金課税する気はなさそうだな、と安心しておりました。
「信託導管理論」的にいくと、
(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
法人税法第十二条
信託財産に帰せられる収入及び支出については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者がその信託財産を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、合同運用信託、投資信託、特定目的信託、(中略)に帰せられる収入及び支出については、この限りでない。
一 受益者が特定している場合 その受益者
二 受益者が特定していない場合又は存在していない場合 その信託財産に係る信託の委託者
(中略)
4 第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定に関し必要な事項は、政令で定める。(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
法人税法施行令第十五条
(1、略)
2 法第十二条第一項の場合において、受益者が特定しているかどうか又は存在しているかどうかの判定は、同項に規定する信託財産に係る収入及び支出があつた時の現況による。(信託財産に係る収入及び支出の帰属)
所得税法第十三条(略、法人税法と同様)
ということで、信託契約で、「いつ(行使時か、交付時か)」受益者が確定すると設計するかで、課税関係も変わってくるのかなと考えたり。
(まとまりませんが、今回はこれにて。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
(以下、さらっと考えてみただけで、後から調べ直して内容が変わる可能性がありますので、ご注意下さい。)
本日は、西濃運輸さんの信託型企業買収防衛策と、イー・アクセスさんのそれを比較して見てみたいと思います。
これも、先日の「税務編」と同じく、すべて「どーせ実際に発動されることはないんだから、発動後の細かいことはどーでもいいじゃん」ということかも知れませんが。
信託型ライツ・プラン導入のための新株予約権の発行について(西濃運輸)
http://www.seino.co.jp/seino/news/pdf/20050517_news_lights.pdf
スキームを図示すると、以下のようになると考えられます。
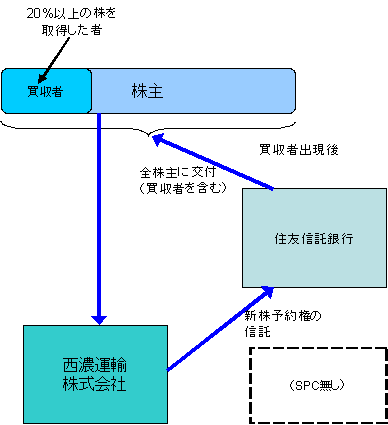
両者の条件の概要を表にまとめると、以下の通り。
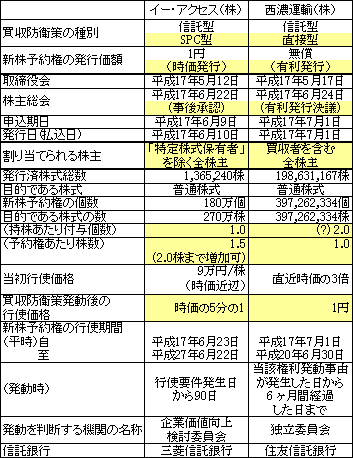
「SPC型」か「直接型」か
西濃さんは、SPCを使わずに直接、新株予約権を信託する形にしています。
この方式は先日述べたような税務上の違いだけでなく、
・「信託に対して発行」とは言うものの、発行会社が自分で自分の新株予約権を保有する形になるのではないか、という点
・投信法に抵触しないか、という点
などが課題になると言われていたようですが、後者は5月12日の自民党企業統治委員会への金融庁の回答で払拭されましたし、前者も新株予約権は自己株式のような商法上の保有規制がそもそもない上 実際には自分で使えないわけですから、どーでもよさそうです。
西濃運輸さんのリリースでは「当社は、委託者としての地位に加え、受益者としての地位も有しますが、信託財産を構成する新株予約権については何らの権利も有せず、またこれを取得することもありません。」と注釈されています。
「SPC型はSPC設立のコストがかかる」というような説明が行われることがありますが、有限責任中間法人一つ作る正味の設立費用は、せいぜい50万円以下でしょうし、理事等に支払う報酬(決算・税務申告込み)も、せいぜい年間2〜3百万円程度?でしょうから、トータルのコストを考えれば、それほどべらぼうな差があるわけではないと思います。(他にSPC型の場合にかかる何か大きなコストってありますでしょうか?)
コストの差を厭わなければ、スキームをトータルで考えて(イー・アクセス型のままというわけではなくて、ですが)「SPC型」の方が多少いい感じなのかな、という気もします。税務上も、SPC型の方が有利になることはあっても不利になることはほとんどなさそうですし。
「時価発行」か「有利発行」か
イー・アクセスの場合、新株予約権の時価を1円として取締役会の権限で発行し、株主総会でスキーム自体の承認を(任意で)得る形を取ってます。
これに対して、西濃運輸の場合、無償(有利)発行として、株主総会の決議で発行する形をとってます。
どっちでも同じなんでしょうね。どうせ近々開かれる株主総会で了承を得るんだったら、あえて時価発行として取締役会決議で先行して発行するメリットは何かあるんでしょうか?(「買収の危機が迫っていて、一刻も早く防御したい」、というのではないとすれば。)
買収者に交付するかしないか
イー・アクセスの場合、そもそも買収者には新株予約権を交付しないんですが、西濃運輸は買収者を含めて新株予約権を交付し、新株予約権の条件で買収者は新株予約権を行使できないことにしています。
つまり、買収者を新株予約権交付の段階で差別するのか、新株予約権の条件で差別するのか、ですが。
理屈としては、SPC型だと発行会社から資本関係や人的関係が切れている第三者のSPCが新株予約権を交付するので、「その第三者が株主を差別しようがしまいが勝手だろ?」と言えるということなんでしょうか?
直接型だと発行会社と信託とはまだ「へその緒でつながっている」ので、買収者を含めた全株主に交付して株主平等原則っぽい配慮はしつつ、「新株予約権の条件がもともと違うので買収者は行使できませんが、決して株主様自体を不平等に扱っているわけじゃないですよ、てへへ」、という形をとってるということなんでしょうか?
(これも、どっちでも同じ気がしますが、上記のような理由だとすると、なんとなくSPC型の方がブロックが堅くなる気もします。)
付与する個数
イー・アクセスの場合、株主の持つ1株に対して新株予約権1個を交付し、その1個が1.5株を取得可能となっているんですが、西濃運輸の場合、(何個割り当てるのか記述がさらっと見た限りよく読み取れないのですが、発行済み株式数の2倍の個数発行されるところを見ると2個?交付されて)、新株予約権1個が1株を取得可能となってます。
どっちがいいんでしょうか?
また、株式分割等の際の株数の調整ですが、イー・アクセスのは「調整の結果生じる1株の100分の1未満の端数株式は、これを切り捨てるものとする」となっているのに対し、西濃運輸の方は、「調整の結果生ずる1 株未満の端数は切り捨てる」となってます。
西濃運輸の方は、1単元1000株ですから、より細かい調整ができるかというとそうではなくて、例えば1.9分割すると、新株予約権1個あたり発行できる株式数は1.9の小数点未満切り捨てで1株。つまり、実質約2分の1に減ってしまうわけです。だから西濃運輸さんは新株予約権の個数を多めに2倍発行してあって、実際には株主の持ち株1株に対して1個しか交付されないということなんでしょうか?
なぜイー・アクセスは2割払い込ませるのか?
買収防衛策発動後の行使価格ですが、イー・アクセスの場合、時価の5分の1のキャッシュの払込が必要ですが、西濃運輸の方は1円で行使できます。
株主にしてみれば、持株の時価の20%も払い込まないといけないというのはそれなりに負担なはずです。なぜイー・アクセスは、そういうスキームにしたんでしょうか?(有利発行と解されると株主総会決議を経ないと発行できないわけですが、それ以外の理由で。)
買収者は新株予約権をもらえないので議決権比率は薄まるが、他の人が2割払い込んでいて企業価値はアップするので、買収者からの「著しく不公正な発行だ!」等という理由での差し止めが成功しにくいから、ということなのかなとも一瞬思ったのですが、
ただ、先日申し上げたとおり(下記に数式を再掲)、2割の払込があっても買収者の株式の価値は40%以上下落すると考えられますので、「経済的損失が少ないから不公正ではない」ということはいずれにせよ言いにくいんじゃないかと思いますが・・・。
![]()
(そもそも、買収者が経済的に損失を被るようにしないと、買収防衛策としての意味がないはず。)
ということで、2割だけ払い込ませるというのは、なんか中途半端な気がするんですが。
株式自体を交付しちゃうのはダメか?
株主に新株予約権を送りつけて「行使してください(行使しないと、あんたにとって損だよ)」と、なかば行使を強要するというのではなくて、SPCないしは信託が新株予約権を自分で行使して、取得した株式を株主に交付する、というのではダメでしょうか?
ポイント1:原資
2割も払い込ませるというイー・アクセスの方式ではSPCや信託に行使の原資がないから無理ですが、1円で行使できる方式ならSPCや信託に数百万円程度現金を持たせておけばいいわけですから、原資的にはスキーム構築可能なはず。
ポイント2:株主・信託銀行双方の事務コスト
株主にややこしい新株予約権の書類を送りつけても、これだけ複雑な内容だと、「意味がよーわからん」という株主は多いと思われます。(おそらく信託銀行が代行するであろう)事務処理説明窓口(コールセンター)の説明負担とか、想定する電話回線の本数や人員等の体制のコストにも大きく影響しそうです。
株主も、たとえ「1円」であっても、書類を書いたり払い込みしたりしないといけないわけですしね。
税務上も、全付与対象株主の取得時の時価を一つにそろえられるわけですから、翌年2月くらいになって、「税務申告のやり方がわからん」等の質問に対応するコールセンターの説明負担もその分かなり楽になりそうです。(システム上、株主毎の行使日のlookup等も不要。)
ポイント3:苦情対応、一般株主からの訴訟リスク
また、行使しない株主に希薄化を発生させるのが目的のスキームですから、万が一、何かの理由(長期に不在にしていた、郵便物が書類の山に埋まっていた、病気になってどたばたしていてそれどころじゃなかった、等)で期間内に行使できなかった一般株主にも非常に大きな損失が発生しちゃいます。それらの苦情や訴訟への対応を考えただけでも気が重くなりそう。
複雑な数回のやりとりを株主に強いるより、最初から最終的な目的物である株式が送られてくる方が、株主にとっての負担ははるかに楽だし、親切ではないでしょうか。
ポイント4:強制転換との比較
新会社法では、発行会社側から強制転換条項を付けられるようになるようですが、信託型ではニレコ方式と違って、せっかくSPCや信託という一括処理できる主体を使ってるので、現行法下でもそのへんまで気を利かせられる気がします。
(良く存じませんが)、仮処分等の事務手続きとして、バラバラの株主が各自勝手に新株予約権を行使するよりは、SPC等がまとめて新株予約権を行使する方が差し止めされやすい、等の「解毒」の問題に関係するんでしょうか?行使の意志決定者が1人に特定されることで「解毒」されやすくなるんだったら、新会社法で発行会社側から強制転換させるスキームも差し止めされやすそうですが・・・。
ポイント5:税務
税務上も、以下のように株を直接交付しても特に問題ないどころか株主にとってもリスクが抑えられるメリットがあると思いますが、どうでしょうか。
(1) SPCが有利発行の新株予約権の付与を受けた時の受贈益について課税を受けることになるが、新株予約権1個あたりの時価を例えば1円程度と設計しておけば、発生する受贈益は数百万円程度に抑えられ、中間法人の理事等に支払う経費(数百万円)と相殺されて実際には課税はほとんど発生しないはず。
(2) 発動時に新株予約権を行使しても利益は発生しない。それを株主に交付した時に「株式数×(株式の時価−行使価格1円その他1株当たり取得費)」分の譲渡益が発生するが、交付によりほぼ同額の費用又は損失が発生するので、行使してすぐ(同一年度内に)譲渡すれば結果としてSPCに課税は発生しない。(新株予約権の場合の国税庁の見解と同じ)
(3) 受け取る株主側としても、先日触れた「時価にタイムバリューが含まれるのか?」「新株予約権の本源的価値は、希薄化分を調整すべきかどうか」といった、税務上明確でない形而上学論争的リスクを背負わなくて済む。
(行使によって株価は希薄化分の調整を受けるはずなので、譲渡される株式の時価は明確になるはずである。)
前述の通り、バラバラの日程で新株予約権が行使する場合と違って、全株主の新株取得日と取得価額が統一されてわかりやすいということもあります。
マニュアルやQ&Aは作ってあるのか?
いざプランが「発動」した場合の事務手続きマニュアルとか株主からの質問に対するQ&A、送付する手続き解説資料なんかはもう作ってあるんでしょうか?
作ってないといざというときあわてる気がしますし(ただでさえ慌ただしいはず)、一方で、どーせ使わないものをあらかじめ作っておくというのは経費のムダ、という気もします。
「いいとこどり」案
以上をまとめて、両者のいいとこ取りをすれば、
・ SPC型とし、
・ 行使価格→有事には1円、発行価格→無償(時価は1円とか)の「有利発行」として株主総会で決議
・ 有事の際には、SPCまたは信託が新株予約権を行使して行使した株式を買収者以外の株主に交付
というあたりが、(万が一、プランを無視して買収者が一定以上の株式を取得した場合にも)、一番、株主にも会社・信託側の事務処理的にも負担が少ない方式のような気がしますが、どうでしょうか?
(注:この2社以外の信託方式の中身は、まだよく見ておりません。)
−−−
以上、先日の税務編と同じく、「どーせ使わないんだから、使った時の細かいことはどーでもいいじゃん」ということかも知れませんが、ジャスト頭の体操まで。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
(以下、さらっと考えてみただけで、後から調べ直して内容が変わる可能性がありますので、ご注意下さい。論点が多くて、昨日中にはまとまりませんでした。すみません。)
■要旨:
長々と書いてますが、一言でいうと、最後の段落の通り、事前予告型や信託型は税務上ややこしくて、米国型の(株式に随伴して流通する)ライツプランの登場が待たれますね、という点に尽きます。
■以下、本文(長いです)
前回に引き続き、イー・アクセスの信託型買収防衛策をケースとして取り上げ、これを税務的に見たらどうなるかについて考えさせていただきたいと思います。
nsm9950cpa さんからコメントいただいてますように、今年の4月下旬の自民党の法務部会(企業統治委員会)において、国税庁が新株予約権を用いたライツプランに対する課税方針を示しています。
(ちなみに、web上でこの文書が見つからないんですが、どなたか、URL等をご存じでしたらご教授いただければ幸いです。)
(追記、20:49:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/4068/01.htm
に載ってます。kuronekoさんに教えていただきました。ありがとうございました。>kuronekoさん。)
この国税庁の見解については、旬刊経理情報の最新号(2005/6/1号)の特集「敵対的買収防衛策の税務とポイズンピル信託の活用」の、「各種防衛策の仕組みと税務問題−ポイズンピルを中心に」(ユナイテッド・パートナーズ会計事務所パートナー・税理士 松崎 為久氏)でも図解(追記、20:49:上述国税庁の資料に書いてあるのと同じ図です)入りでまとめてらっしゃいますので、ご興味のある方はご参照ください。(ちなみに、定期購読のみでバックナンバー1部だけの購入はダメみたいです。)
nsm9950cpaさんのコメントでも、この国税庁の見解について整理していただいてますので、(横着して)これを引用させていただきますと、
ライツプランの税務上の取扱いについては、4月28日開催の自民党の企業統治に関する委員会において、国税庁が基本的考え方を明らかにしています。
この時の説明では、ライツプランを以下の3つに分類しています。
�事前警告型ライツプラン
ライツプランの導入については事前警告のみ行い、敵対的買収者が現れた時点で新株予約権を付与する方法
�信託型ライツプラン(直接型)
�信託型ライツプラン(SPC型)
税務上の取扱いは、最後にまとめましたので、それを参照していただければと思いますが、結論としては、税務の観点から考えるとSPC型は、��より不利な扱いになります。
「不利」にも関わらずSPC型を採用した理由についてnsm9950cpaさんは、下記のように投資信託法上の扱いが不確定だったからではないかという見解を述べられています。
それでは、イー・アクセスが何故SPC型にしたかの疑問が残りますが、それは投資信託法上の疑義があったことによると思います。
4月28日の自民党の委員会では、投資信託法上、信託銀行に直接、新株予約権を発行できるかどうかが不明確との話がでており、金融庁の見解を示してもらうことを宿題にしていました。
5月12日の自民党の委員会において、金融庁から回答が示され、投資信託法上、可能ということになりました。すなわち、投資信託法第5条の2に抵触しないということです。
イー・アクセスのライツプランのプレスリリースは、5月12日ですので、金融庁の投資信託法上の見解が出る前に、スキームを作ったことから、SPC方式を選択したものと推定できます。
nsm9950cpaさんがまとめた「税務上の取扱い」は以下の通りです。
(税務上の取扱い)
株主に対する課税関係は、�と�の場合については、法人株主については、新株予約権の付与時に時価相当額の受贈益が生じ、個人株主については、行使時に株式の時価と権利行使価額との差額に課税されるとしています。また、�については、法人株主、個人株主ともにSPCから株主へ新株予約権を譲渡した時点で、時価相当額の受贈益・経済的利益が生じるとして課税対象になります。�のSPC型であれば、個人株主に対する課税が取得時点であり、�、�の行使時の課税よりも早く課税され、税務上不利な扱いになっています。
この違いは、所得税法施行令84条3号の規定自体が商法280条の21第1項(新株予約権の有利発行決議)に基づき発行された新株予約権は、課税時期を権利行使時と定め、収入金額を「権利行使時の株価−(新株予約権の取得価額+行使払込額)」と定めていることに関係します。
(中略)SPC型は、SPCから株主へ譲渡することを前提にしていますので、付与時の課税にならざるを得ないと国税庁は考えたものと思います。
この国税庁さんの見解を図示すると、下記の通りとなると考えられます。
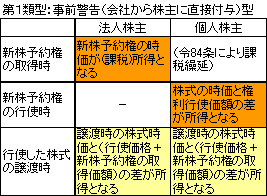
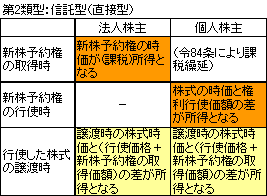
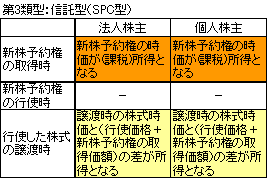
今回のスキームの場合、新株予約権の取得と行使は、(年末年始をまたがない限り)、個人の場合には同じ課税期間になりますので、イー・アクセスさんとしては、実際に第3類型が第2類型に比べて「不利」になることは無いと判断されたのかも知れません。
問題となるこの所得税法施行令第84条の条文は、下記の通りですが、
所得税法施行令第八十四条(株式等を取得する権利の価額)
発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合(法人税法第二条第十四号(定義)に規定する株主等として与えられた場合を除く。)における当該権利に係る法第三十六条第二項(収入金額)の価額は、当該権利の行使により取得した株式(これに準ずるものを含む。)のその行使の日(第四号に掲げる権利にあつては、当該権利に基づく払込みに係る期日)における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。
(中略)
三 商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議に基づき発行された同項に規定する新株予約権 当該新株予約権の行使に係る新株の発行価額(当該新株予約権の行使により当該発行法人の有する自己の株式の移転を受けた場合には、当該株式の譲渡価額)
四 有利な発行価額により新株(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を取得する権利(前二号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る新株の発行価額
ここでいくつか(ちょっとマニアックな)疑問がわいてくるわけです。
「会社から与える権利」なのか「株式等の譲渡」なのか?
1つめの疑問。上記で国税庁さんが言う第三類型(SPC型)において、SPCから株主に対して行われる譲渡は、令84条でいう「発行法人から権利を与えられた場合」に該当せず、一般の有価証券(株式等)の譲渡に該当するわけですよね。
租税特別措置法第三十七条の十(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
3 前二項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
一 株式(株式の引受けによる権利、新株の引受権及び新株予約権を含む。)
(以下略)
第1、第2類型だと「発行法人から(直接)権利を与えられた場合」に該当すると思いますが(だからこそ84条が適用されて課税が繰り延べられているわけですが)、第3類型のSPCは(実態はともかく形式上は)イーアクセスとは資本・人的関係がない有限責任中間法人で「全くの第三者」であり、その法人からの譲渡は、「発行法人から(直接)権利を与えられた場合」ではなく、単なる「株式等」の譲渡に該当するかと思います。
(スキーム図再掲)
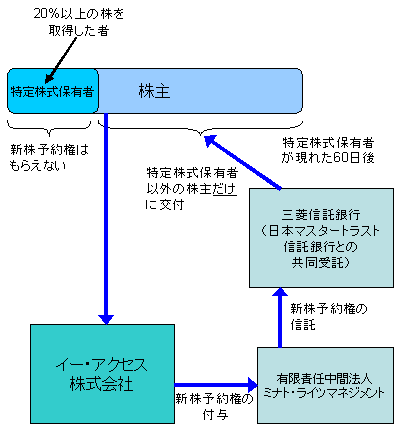
今回の場合、株主は新株予約権を無償で受け取るので、どっちにしろ、受け取った個人株主に、「譲渡を受けたときの新株予約権の時価」分の所得が発生しちゃうのは(時価>0円なら)しかたのないところです。問題は「何所得」になるのか。
(会社から直接付与される)第1、第2類型の場合には、前述の松崎氏の論文では「行使時に雑所得(総合課税)」となると書いてあります。
第3類型の場合が何所得に該当するのか書かれていないのではないかと思いますが、一般には、法人から個人への低額譲渡では、個人側がその法人の従業員等であれば「給与所得」、従業員でない場合には「一時所得」として所得税が課税されることになっていると考えられます。
所得税基本通達36-36〔給与等とされる経済的利益の評価〕
(有価証券の評価)
使用者が役員又は使用人に対して支給する有価証券(令第84条各号に掲げる権利で同条の規定の適用を受けるもの及び法人税法第2条第14号に規定する株主等として発行法人から与えられた新株等を取得する権利を除く。)については、その支給時の価額により評価する。この場合における支給時の価額については、23〜35共-9及び昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」の第8章第2節《公社債》の取扱いに準じて評価する。
(一時所得の例示)
所得税基本通達34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(中略)
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
企業の個人株主の中には、創業者などの「大口株主」もいれば、役員も従業員も取引先の個人事業者もいます。今回の新株予約権の付与の場合、目的としては「従業員」ではなく「株主」に付与したいわけですが、株主割当ではなく「買収者」にも付与されないので、話がややこしくなります。
この新株予約権の譲渡が、イー・アクセスからの譲渡ではなく、実態としてもSPCからの譲渡であり全個人株主が「一時所得」扱いとみなしてもらえればしめたもんです。
「一時所得」とみなされ、
{新株予約権の時価−特別控除額(50万円)}×1/2
だけが課税されるのと、「給与所得」や「雑所得」として(1/2されずに)総合課税されちゃうのでは、雲泥の差です。
SPCという「全くの第三者」から譲渡を受けた新株予約権は、通常の有価証券の取得と同様として取り扱われるのであれば、無償でこれをもらった株主はどの株主も一律、新株予約権の「時価」分が一時所得として課税されることになり、後は、株式を譲渡するまで課税されないはずです。
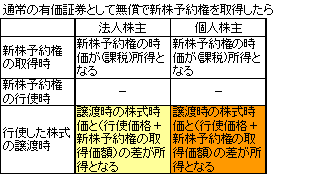
つまり、第2類型じゃなくて第3類型とすることで、税務上、役員や従業員の株主等に対する課税が給与所得とみなされない可能性が高まり、実効税率も半分になるのであれば、第3類型を選択した方が、税務上「有利」になるとも言えるかも知れません。
ちなみに、税制適格ストックオプションの場合の新株予約権の課税関係は以下の通り。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第二十九条の二
商法(略)第二百八十条ノ二十一第一項に規定する新株予約権(略)を与えられる者とされた当該決議(以下この条において「付与決議」という。)のあつた株式会社又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数の百分の五十を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人の取締役又は使用人である個人(当該付与決議のあつた日において当該株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人(以下この項及び次項において「大口株主」という。)及び同日において当該株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人(次項において「大口株主の特別関係者」という。)を除く。以下この項、次項及び第五項において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人(政令で定めるものに限る。以下この項、次項及び第五項において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議に基づき当該株式会社と当該取締役等との間に締結された契約により与えられた当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権に係る契約において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この項、次項及び第五項において「特定新株予約権等」という。)を当該契約に従つて行使することにより当該特定新株予約権等に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、(以下税制適格の要件、省略)
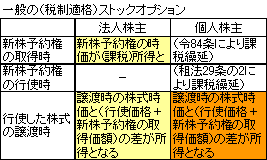
じゃあ、こうした第1類型や第2類型の買収防衛策で従業員等である株主が新株予約権を取得したときに税務署が「それは給与所得だ」と言うかどうかですが、実際にはその可能性は限りなく低いとは思います。
一方、このSPC型の付与スキームであれば、「発行法人」からでなく「第三者」からの有価証券の譲渡とみなされるのであれば、本件から離れて、会社が役職員向けに税制適格でないストックオプション(年間1200万円以上行使できるとか、付与後2年以内に行使できるとか)を発行する場合に、株式譲渡時に分離課税で済むというのにも使えてしまうという可能性についてはどうでしょうか?
昔は、「成功報酬型ワラント」のように、分離型の新株引受権付社債を第三者に発行しておいて、社債部分を早期償還し、新株引受権だけを第三者を経由して従業員等に付与するというスキームがよく使われていましたが、新株予約権を使った税制適格ストックオプションが発行できるようになってからは(面倒なので)あまり見かけません。これと同様のことをSPCを使って今やったらどうなるんでしょうね?
実務上の事務手続き
(基本的には交付されない可能性が高いはずですが)、実際にこの新株予約権が交付されることになったら、確定申告の仕方など税務上の取扱いも含めた(ややこしい)説明資料を全株主に送付しなきゃいけないのは間違いなさそうです。
(ちゃんと理解して確定申告書が書ける株主は、ほとんどいないことが予想されます。→大混乱必至?)
そもそも新株予約権の「時価」とは何か
新株予約権を無償で譲り受けたり行使した場合、(何所得になるかはともかく)その「時価」分が所得になるのはわかります。では、この新株予約権の「時価」とはそもそも何でしょうか?今回の場合、ホントに「時価」に課税されるんでしょうか?
論点1:time valueを含むのかどうか
前述の旬刊経理情報の記事で松崎氏は、所得税法上、法人税法上、新株予約権についての明確な時価算定の基準がなく、唯一、財産評価基本通達193-2、
(ストックオプションの評価)
193-2 その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、ストックオプション1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数のときは、0とする。)によって評価する。この場合の「課税時期におけるその株式の価額」は、169《上場株式の評価》から172《上場株式についての最終価格の月平均額の特例》まで又は174《気配相場等のある株式の評価》から177−2《登録銘柄及び店頭管理銘柄の取引価格の月平均額の特例》までの定めによって評価する。
で、「ストックオプションの評価は本源的価値(intrinsic value)部分だけでいい」とされているのが参考になるのみで、所得税や法人税で一般的に、「時間的価値(time value)」部分が評価に含まれるのかどうかが不明確であることを問題にされております。
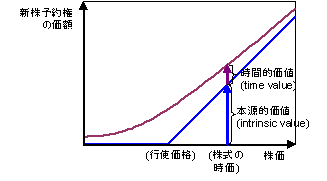
ただし、オプションの条件を適当に調整することによって、実務上はtime valueの部分を著しく小さくすることができるので、それで解決する部分があるということもおっしゃってます。
実際に大規模なスキームの実務では、この部分についての評価を第三者から取得するんでしょうね。
(例えば、イー・アクセスのスキームでSPCに対して新株予約権を付与する時の発行価額を1円/1個としていますが、これも特殊な場合しか行使できないことを勘案すると、その程度の評価額にしかならない、てな意見書等を取得しているのかも知れません。)
論点2:dilution分はどないすんねん?(一部追記、変更、20:00)
もう一つ、松崎氏の記事では、「ポイズンピルとして利用される新株予約権は行使価格が1円というようなディープ・イン・ザ・マネー(超有利発行)となるため、どの場合でも有事の際に最低限本源的価値相当額の課税が法人株主および個人株主に課税されることになる。」とされてます。
ただ、ポイズンピルのように非常に大きな希薄化(dilution)が発生するような新株予約権の発行の場合に、単純に原資産の価格が正規分布する確率で変動するブラック・ショールズ的なモデルでプライシングしていいのか、それとも新株予約権による希薄化分を時価に反映させて考えるかどうかは論点になるんじゃないでしょうか。
(そう、この新株予約権は行使しないと希薄化しちゃうので、半強制的に行使「させられる」わけです。)
(例えば単純化した例として)、株価が10万円のときにほぼ全株主に1株に対して1個づつ、1円で1株が取得できる新株予約権が付与されたとしたら(理論的には全員が行使するに決まっているので)、実態としては2倍の株式分割をするのとほぼ同じわけですから、直前の株価だけを見てストックオプションの価値が少なくとも99,999円ある、てなことを言われても困るわけです。
実質は、このストックオプションの価値は、「ゼロ」ですよね。というか逆に、払い込まないと自分の資産が2分の1の価値になっちゃうわけですから、新株予約「権」というよりは、新株購入「義務」みたいなもんで、株主にとっては迷惑な話とも言えます。
今回のイー・アクセスさんの場合でも、払込金額はそれまでの時価の2割、新株予約権は買収者以外に一人当たり1個で、1個あたり1.5株が買えて、買収者は2割以上株を取得した人ですから、払い込まずに放っておけば、
![]()
と、約6割に希薄化してしまうわけです。
また、希薄化により、買収者からその他株主に価値が移転するわけですが、それについての(国税庁さん等の)見解はどうなんでしょうか。
米国型のライツプランをキボンヌ
説明が長くなりましたが、これらの税務上の話はすべて、株主割当で新株予約権を割り当てないためにややこしくなってるわけです。「第1〜3類型」の中には入ってませんが、米国型のライツプランやニレコ型や、インボイスさんの先日の全株主へのストックオプションの付与のように、株主割当で新株予約権を付与すれば、少なくとも税務上の問題はより発生しにくいと考えられるわけです。
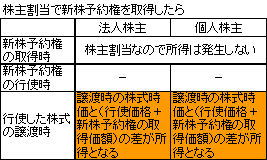
平時に全株主にライツを付与し、(ニレコ型と違って)株式の譲渡とともに「随伴して」ライツも転々と譲渡されていくような米国型ライツプランと同様のスキームが、(現行法内でスキームが組めるのかどうかはおいといて)早くできるようになって欲しいところです。
新会社法で、会社側から強制的に行使させられるようになったりできれば、株主側としては面倒もないので、なおいいですね。
(本日は、これにて。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
(23:59追記あり。)
前回に続いて、イー・アクセスさんの信託型のライツプランについて。
企業価値向上新株予約権(eAccess Rights Plan)の導入について
http://www.eaccess.net/press_img/2705_pdf.pdf
このプレスリリースには図がついてないので、スキームの全体像を図示してみました。
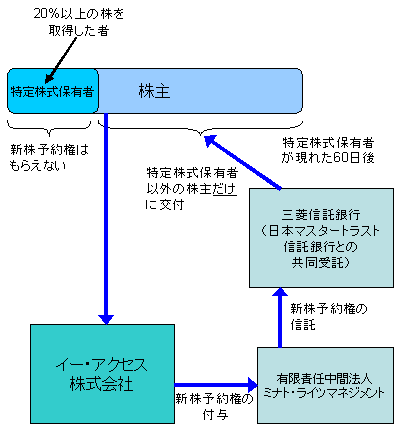
1.新株予約権の付与
まず、イー・アクセスが有限責任中間法人ミナト・ライツマネジメントに新株予約権を付与します。「有限責任中間法人」というのは、証券化や流動化に係わってらっしゃる方は見慣れてらっしゃるわけですが、一般の方のために平たく解説しておきますと、平成14年4月の「中間法人法」の施行から使えるようになった「株主のいない有限会社」みたいなもんです。連結から切り離したり倒産隔離したりといった資本関係を宙ぶらりんにしたいときによく使われるわけです。
この新株予約権の条件の主要なところをピックアップしますと、以下の通り。
・新株予約権の目的となる株式の種類及び数:新株予約権1個あたり当社普通株式1.5株(〜2倍)
・発行する新株予約権の総数:180万個
・発行価額:1個あたり1円
・行使に際して払込みをなすべき額:(時価の)5分の1
現在の発行済株式数が1,365,240株(Yahoo!ファイナンスによる)。この防衛策が発動されると、株式数は約2.5倍〜(ただし買収者を除く)となるわけです。
2.新株予約権の信託
有限責任中間法人ミナト・ライツマネジメントは、三菱信託銀行(日本マスタートラスト信託銀行との共同受託)に、この新株予約権を信託します。
3.特定株式保有者が現れたときに新株予約権を交付
議決権の20%以上を取得する「特定株式保有者」が現れた場合、その60日後に信託銀行が新株予約権を株主に交付します。ただし、買収者(特定株式保有者)は新株予約権をもらえません。
当然、社外取締役で構成される「企業価値向上検討委員会」が認めた(友好的な)買収者の時には、この新株予約権が消却されるので、買収者は影響を受けないわけです。
株価への影響
これ、買収者以外の既存株主には極力影響を与えないように非常によく考えられたスキームではあると思うのですが、発表(5月12日)後の株価は・・・・以下のとおり、あまり好感されてないようです。
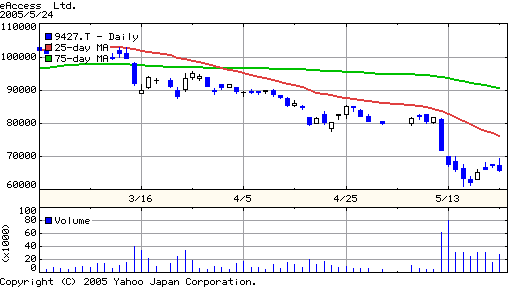
(買収防衛策一般の特性と、この方式固有の問題点を含めて)、一般株主の方の気持ちを想像するに、下記のような感じでしょうか?
(1) なんやようわからん。(→わからんものは売り。)
(2) 新株予約権を発行するってことは、とにかく売りだ。
(3) (ライブドアのような)買収者が買収できないということは株価が上がるチャンスがそれだけ減るということじゃないか。→売り。
(4) よく考えると、実際、このスキームが使われることになったら、課税関係が生じるというウワサで、ややこしそうだ。→売り。
(5) 買収者以外の一般株主には影響を与えないと言いながら、時価の5分の1の金額(×1.5株分)は払い込まないと希薄化してしまう。(そのときにそれだけの資金があるかどうかわからないし。)
米国では、ライツプラン(ポイズンピル)の導入が株価に与える影響は中立だ、という研究があるとか無いとか。ポイズンピルというのは買収する場合には事前に交渉のテーブルに着いてくださいねと言う「紳士的な脅し」であって、米国でも(間違って使われたケースを除けば)実際に使われる例は皆無ということなので、(このスキームがアメリカの一般的なものと違ってまだ課題がある点を考慮するにしても)、ここまで下げ要因にならなくてもいいんじゃないか、という気もします。(わざわざ「企業価値向上新株予約権」ってな名称も付けられて株価にも配慮されているんじゃないかと思いますが・・・・あまり役に立ってなさそう。)
実際、こういう買収防衛策が入っていると、例えば、ライブドアによるニッポン放送株取得のケースを考えてみても、
「35%も取得するんだったら、時間外取引を利用して6,050円で取得するなんてケチなこと言わずに、6,300円くらいでTOBかけてフジテレビと株価のつり上げ合戦を演じてくださいよ」
といった交渉も可能だったはずで、必ずしも株価を押し下げる要因だけじゃない(というか本来、委員会は株価をつり上げる方向に行動するはず)と思うんですが。
「社外取締役が株主のためを考えて決定します」と言ってるのに、日本ではまだ社外取締役が中立の立場で行動するという信用というもんが無いんでしょうか?
他の買収防衛策を導入される企業も、こうした実際のケースにおける株価の動向には注目せざるを得ませんね。
(ということで、本日はこれにて。続く・・・・予定。)
(追記:)
おとといあたりまでバタバタしてまして、他の方のブログを良く読まないで書いてましたが、同様のことはすでに(当然)、他の方が書いてらっしゃいますね。
47thさん、
http://www.ny47th.com/fallin_attorney/archives/2005/05/post_6.html
HardWaveさん、
http://blog.livedoor.jp/hardwave/archives/21934611.html
小林雅さん、
http://venturecapital.typepad.jp/blog/2005/05/post_3a2e.html
(では。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
イー・アクセスさんが発表された信託を使った買収防衛策について。
企業価値向上新株予約権(eAccess Rights Plan)の導入について
http://www.eaccess.net/press_img/2705_pdf.pdf
買収防衛策では、(企業に損害を与える可能性のある)敵対的買収者だけに損害を発生させて(損害が発生するよと脅しをかけておいて)、それ以外の一般の株主に損害を与えないかというところが、株主平等原則といった法律論的な観点からのみならず、一般株主や世論の支持を得るためにも非常に重要ではないかと思います。
ニッポン放送がフジテレビに発行しようとして差し止められた新株予約権による防衛や、ニレコ型の買収防衛策では、確かに敵対的買収者にも損害を与えるものの、他の一般株主にも損害が発生してしまうところが大きな問題点なわけですが、このイー・アクセスさんが発表されたプランでは、信託(とSPC)を用いることで、このへんをクリアしてらっしゃいます。
一方、この方法は、新株予約権が発行された後に譲渡が行われるわけですので、SPC、株主といったあたりの税務上の問題が発生し得ます。
このへん、国税庁さんも見解を出し始めてはいらっしゃいますが、
新株「ポイズン・ピル」非課税に…経産省・国税庁方針(読売新聞)
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/keizai/20050428/20050428i507-yol.html
ちょっとこのイー・アクセスさんの買収防衛策をケースとして取り上げて、こうした仕組みについて勉強させてもらおうかなと思います。
この新株予約権の税務というのは、役職員向けのストックオプションの場合のみ(所得税法ではなくて)租税特別措置法で定義されているとか、税務上の「オプションバリュー」が必ずしもはっきり定義されていないとか、いろいろディープなところがありまして、MSCBが「オプション性」が関連して一般の人がよくわからくなっちゃうのと同じかそれ以上(税務が絡むので)に、理解しづらくなっているのではないかと思います。
(続く。・・・おそらく・・・・)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。
ライブドアからフジテレビに、ニッポン放送株を保有する株式会社ライブドア・パートナーズの譲渡が完了し(新社名株式会社LFホールディングス)、フジテレビのライブドアへの第三者割当による払い込み(44,000 百万円)も完了したと、リリースがありましたね。
株式会社ライブドア・パートナーズ株式譲渡および株式会社ライブドアへの第三者割当増資払込完了のお知らせ
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104676/00033763.pdf
旧株式会社ライブドア・パートナーズは、すぐにフジテレビと合併するようです。
合併に関するお知らせ
http://www.c-direct.ne.jp/japanese/uj/pdf/10104676/00033764.pdf
(デューデリジェンスでも何も出てこなかった、ということで。めでたし、めでたし。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。