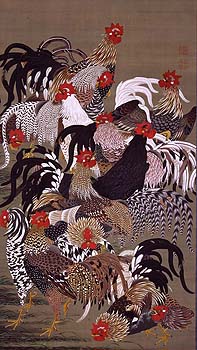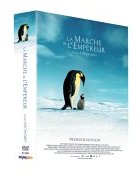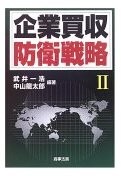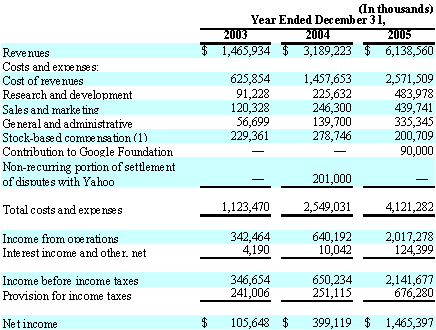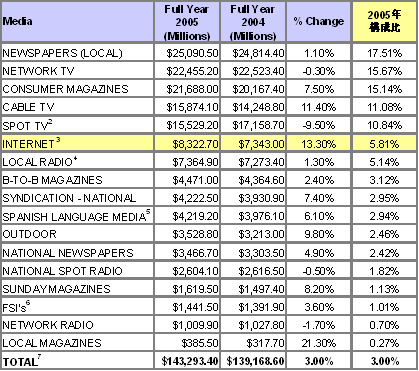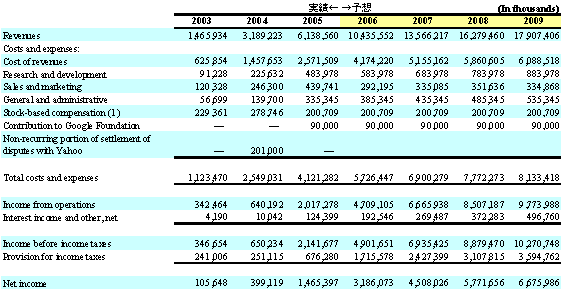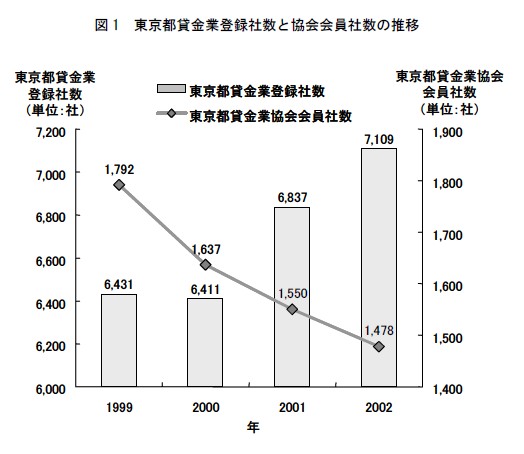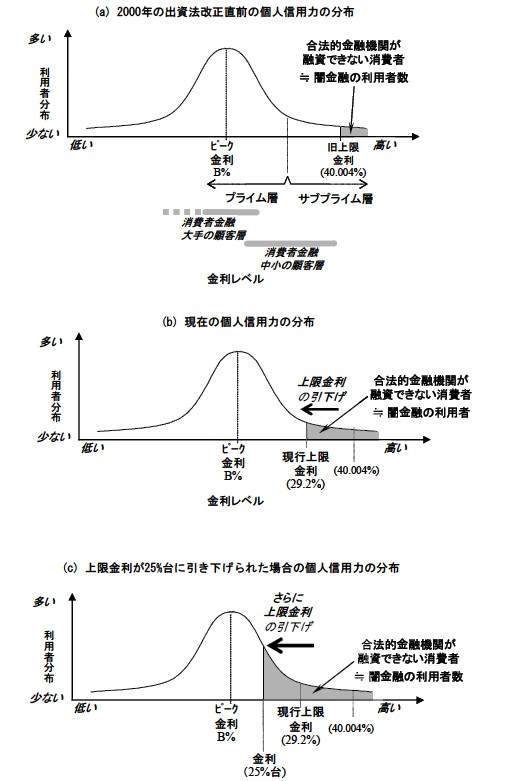さて、東証さんが決算短信のXBRLデータを試験公開されはじめました。
(リリースはこちら。)
XBRLとは
XBRLについては、以前、「EDINET開示の義務化とXBRL」という記事で取り上げさせていただきましたが、平たく言うと「会計版のXML」です。
今までの企業の開示データ(決算短信など)は、webに開示されているものもhtmlやPDFで作成されてるので、人間様ならば「その会社の売り上げがいくらか」といった情報を抽出することが可能ですが、コンピュータは、どこに売上とか利益とかのデータが書いてあるか皆目わからない。これがXMLとなると、タグ付けされた特定の項目をアルゴリズム的に拾うことによって、直接、コンピュータが「○○社の売上はいくら」と答えられるようになるわけです。
仮に、すべての上場企業や有価証券報告書を発行している企業などがXBRLで情報開示するようになった暁には、プログラミングがちょっとできる人なら、高価なデータやインプット要員がいなくても、Yahoo!ファイナンスの企業情報とか決算情報と同様の(または、より複雑な)ページを、チョチョっと作成して公開する、なんてことも可能になるはず。
換言すると、XML化というのは、その情報の持つ「意味」のレイヤーと「表現」のレイヤーをアンバンドル(分離)する、ということでもあります。
実際にデモを見ると「おおっ!」と感動するんですが、ちょっとしたexcelのマクロで、日本語の財務諸表が一瞬にして英語(米国会計基準[風])の財務諸表に変わったり、韓国語の財務諸表に変わったりします。しかも単なる「翻訳」ではないので、会計基準の違いによって、特定の科目が資産の部に表示されたり、自己資本に表示されたり、といった表示方法も変更されるわけです。
「意味づけされたデータ」の意味
こういう「規格モノ」は、一定以上の利用がはじまればポジティブ・フィードバックが働いて利用が急速に増えるわけですが、逆に言えば、一定の「しきい値」に達するまでは、その規格に対応しても誰も使ってくれない → 誰も取り組まない → 誰も使わない、という逆のフィードバックが重くのしかかります。
ということで、わたしは、こうした「セマンティック(semantic)」なウェブやデータというのは、「理想はともかく現実的には普及しないんじゃねーの?」と思ってました。が、ここへ来て、ブログのブームでRSSやatomが大きく普及して、大成功例がひとつ出来ちゃいましたね。
数年前から伊藤穣一さんが「ブログ、ブログ」とおっしゃってるのを聞いても、「んなもん、流行らんでしょ・・・」と冷めた目で拝見してまして、RSSの配信やトラックバック等、プッシュ的ツールのスパイラル的効果もあって「ブログ」が流行語大賞のトップテンに入るまでなるなどという未来像はまったく予想できてませんでした。(そんな私が、今、ブログを書いて大量のトラフィックをいただいている、というのも皮肉なお話であります。)
そのお詫びと、isologueを本の中でご紹介いただいた御礼とを兼ねて、ちょっと伊藤穣一さん(とTechnoratiのシフリーCEO等)のご著書のご紹介。

伊藤 穣一+デヴィッド・L・シフリー&デジタルガレージグループ (著)
また、ビジネス系の情報がXML化された未来を妄想したものとして、
「オープンな法体系(SF小説風)」
というものも過去に書いてますので、お暇な方はご覧ください。
「意味づけされたデータ」とGoogle
こうした「セマンティックな」データとしてよく引き合いに出される例として、商品の価格情報があります。
例えば、現在ネットで商売している人は、楽天(さん)に商品を掲載したり、カカクコム(さん)に情報を出したりして、トラフィックを呼び込んでいるわけです。つまり、ただホームページを作って待っていても客は誰も来てくれない。商品コードや価格情報タグ等が付されたメタなRSS等での「セマンティックな」データが配信されて、世界中すべての「ある商品」の価格等の情報が「横串」で突き刺して検索・比較できる状況を想定すれば、楽天・カカクコム・ヤフオク・eBay等のどこにモノが出品されているかに関係なく、消費者は全世界を文字通り「ひとつの市場」として利用することができるという、劇的な変化が想定されます。もちろん、RSS配信などで、(ほぼ)リアルタイムで情報を入手することも可能。
楽天・カカクコム・ヤフオク・eBayといったサイトは、そのような「透明な器」になるのは直接的には商売のマイナスになる(気がする)ので、少なくとも当初は対応したがらないはずですが、一度「しきい値」を超えると、そうした情報配信に対応していないと出店者の商売にマイナスなので、対応せざるを得なくなるはず。
話がそれますが、GoogleのAdSenseも単なる「広告」というよりは、こうしたモールやオークションの提供しているサービス(トラフィック誘導機能)を一部代替しているとも考えられますし、Googleの今後のポテンシャルを考える場合にも、「広告費」だけを上限として考える必然性はなくて、「モール」「オークション」「店舗コスト」「営業マンの人件費」等、ビジネスをするためのありとあらゆるコストやマーケット規模が分母になってくる可能性があるわけです。
(もちろん、そうした「メタな検索」での勝者がGoogleになると決まってるわけではありませんが。)
同様に、XBRLの普及は、投資家が現在、アナリスト情報や金融情報サービスに払っている代金の一部を、「単なる検索技術」が代替する可能性・・・でもありえます。
XMLのマーケティング
以上のように、XBRLは「コンピュータが読めるデータである」ことが本質であると考えると、東証さんの決算短信XBRLデータ試験公開サイト
http://www.tse.or.jp/listing/xbrl/top.html
は、その「真逆」になっているところが非常に面白いですね。
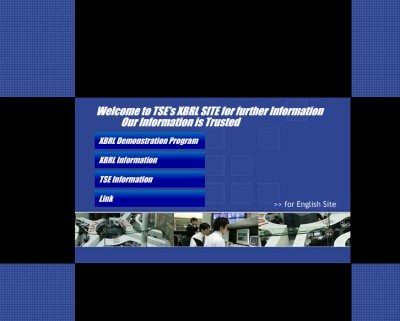
トップページでは、まずflashの画像がチカチカ表示されますが、これは人間に対してもさることながら、「Google様」にとってはほとんど意味が無いデータ。続いて表示されるメニューも、なぜか英語のみ。おまけに、文字は全部「画像」で表示されてまして、ボタンの画像の「alt」タグも全部ブランクですから、コンピュータに全く読めないことはもちろん、視覚障害者の方々にも読めませんし、はたまた英語がわからない日本人にも、なんだかよくわからないメニューになってます。
もちろん、普及のターゲットはまずは「人間様」なのでしょうけど、ブログの成功を見ても、鍵は今や「コンピュータ様」にいかに理解してもらうかなので、こういう「徹底的に反SEO的なつくり」は、普及の妨げにはなってもプラスにはならないんじゃないかと思った次第です。(平たく言って、Googleで上位に表示されないのでは?)
XBRLから話がそれますが、(ブログの成功に習うなら)、一足飛びにXBRLを普及させようという大上段なアプローチよりは、例えば東証さんのTDnet情報をRSSで配信したりしたら、XML的投資情報普及のマーケティングとしてはものすごく大きなインパクトがあるんじゃないでしょうか。
例えばパソコンのスクリーンセーバーや常駐ソフトにRSSリーダーの機能が組み込まれていれば、投資家は自分の興味ある会社や業種の発表を「リアルタイム」に「直接」知ることができるわけですから、投資家層や金融ビジネス関係者に、RSSリーダー機能[を持ったスクリーンセーバーや常駐ソフト]が爆発的に普及するのはほぼ確実かと。
(追記:投資情報をRSS等でばら撒く場合、証取法上も情報の真贋が極めて重要な問題(風説の流布等)になりえますが、東証さんはすでにTDnetの開示情報に対するデジタル署名サービスをはじめてらっしゃいますし、技術的に簡単にクリアできる話だと思います。)
XBRLとかXMLのような「オープンな規格」を普及させるためには、まずは、利用者側の「マインド」を高めることや、周辺の「ツール」を作れる人の層を分厚くしておくことが重要なはず。一度、そうした層の厚さが「しきい値」に達したら、後はポジティブ・フィードバックで坂道を転げ落ちる岩のように普及が進む・・・はずです。
見る人が多ければ、開示する企業の側も(多少手間がかかっても)XBRLに対応するインセンティブも沸いてきます。また、ベースとしての「リーダー(reader)」が普及していれば(普及していてこそ)、追加的なタグ情報(つまりXBRL)の処理機能を載せるのはわけない、というもんじゃないかと。
そういう「web2.0っぽい」XBRLのマーケティング策はいかがかな、という思いつきでした。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。