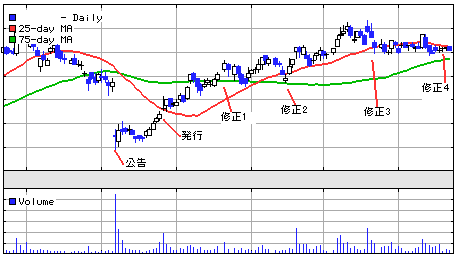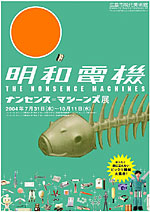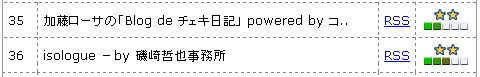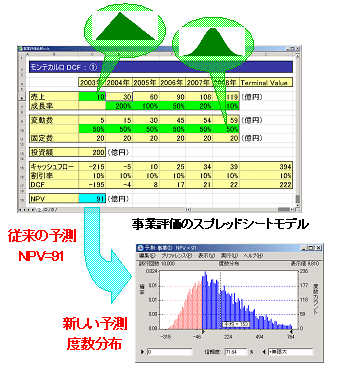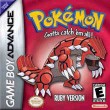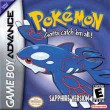切込隊長blogに、「木村剛3 〜実は私もビートルズマニアです」
http://kiri.jblog.org/archives/001264.html
が掲載されました。
いやー、いろいろ調べてらっしゃって、大変興味深いです。
事の当否は私はよく存じませんが、そんな中、いろいろ気づいた点についていくつかコメントさせていただければ。
以下、目下いい具合に懸案となっております木村氏の例のアレに関する質問事項を日本振興銀行関連に絞って掲載しておきます。ゆとり教育でウキウキな世代からの愛の質問状でありますが、証拠物件の関係上質問をとりあえず8つに限定しておきました。
また、既存の報道で木村氏が事情について語らなかった点についてが中心となっております。
ということで、切込隊長氏が木村剛氏に公開質問をされているのですが、その中から;
0. 「株主の代理人」について
木村氏は書きました。
少なくとも「株主の代理人」たる私の場合、日本振興銀行に関する情報発信におきましては、第三者に対して証明できる事実の上に構築される主張でなければならず、しかも、後日訴えられることがあろうとも整斉と説明できるものでなければなりません。
その通りです。委員会等設置会社ですから、第三者に対して証明できる事実のうえに構築される必要はあるでしょう。
(ここは、あえてつっこませていただければ、委員会等設置会社でなくてもそうですね。)
つまり、木村氏がブログ開始以来たびたび語られてきた日本振興銀行に関する積極的で前向きなお話は、すべて第三者に対して証明できる内容であるということです。
例えば、このようなエントリーがあります。
5月19日の時点においては、何ら特別な営業活動を展開していないにもかかわらず、累計で80億円を超える金額のお申し込みをいただいています。
前回のエントリーで書いた、「零細中小企業向け融資のビジネスモデルは、アウトバウンド&ピンポイントでないと成立しにくいのでは?」という仮説からすると、「何ら特別な営業活動を展開していないにもかかわらず、申し込みがたくさん来ちゃってる」という状態は、「うれしい状態」というよりは、かなりヤバい兆候と見た方がよかったのかも知れません。
大半はとても貸せない客だとすると、申し込みを一応にでも審査して、貸せない理由を説明し、「庶民の味方の銀行じゃなかったのかよぅ」等、食い下がってくるせっぱつまった企業側をなだめる、というオペレーション上のコストは、それはそれはデカそうです。このビジネスモデルの場合、普通のビジネスと正反対で、本を書いたりPRしたりする「目立つこと」は、もしかすると「業務効率を下げる要因」だったんではないでしょうか。
2. 日本振興銀行の設立の経緯について
木村氏は、元衆議院議員の野中広務氏のこの言葉を覚えておられるかと思います。「小泉さんの周りで、民間から政府や審議会に入り、規制緩和だの旗振りをしている人の中に、その分野でしっかり自分の商売をしている人がいる。国民からすれば道義的に許されない話だ」
本件は木村氏が日本振興銀行を設立する際に、どのようなアプローチで設立に漕ぎ着けたのか?という話です。
2002年10月に金融庁でまとめられた金融再生プログラムに、「銀行免許認可の迅速化」www5.cao.go.jp/shimon/2002/1030/1030item1.pdfとかいう一文が盛り込まれていますが、通称「竹中プラン」を取りまとめたのは木村氏ご本人ですな。これは木村氏での講演でも語っておられるほどのことで証明するまでもないでしょう。
で、その「銀行免許認可の迅速化」で受益があったのはどこか。木村氏の手がけた日本振興銀行、それそのものではないですか。金融庁内のヒヤリングにおいても、本件につき問題点を指摘したと聞いています。つまり、自らが金融政策のガイドラインを作り、方針を決めさせて、その一方で素晴らしい速度で銀行予備免許が交付されたと、そういうことでしょうか。
前後関係がよく頭に入ってないのですが、「自分の関与する銀行」立ち上げのために答申を書いたのだったらちょっと問題ですが、答申を書いた後に「銀行を設立すべきだ」と思い立ったんだったら、まあ、アリかなとも思いますが。
同様に、2003年4月10日の段階で、日本振興銀行を設立するための母体となる中小新興企業融資企画株式会社が資本金4億円で設立されています。その企業の目的は、何と「銀行設立に係るコンサルタント業」。何ですかこれは。
これは、ふつうの設立準備会社の定款の目的によく使われる言い回しではないでしょうか。
5.日本振興銀行の増資について
日本振興銀行は、今年8月から10月にかけて約5億円の増資が行われています。
2004年8月10日 24億8,000万円→26億7,570万円
2004年9月25日 26億7,570万円→28億6,070万円
2004年10月18日 28億6,070万円→29億9,000万円
商法上、増資額の半分までは資本準備金に組み入れられるので(商法284条ノ2�)、資本金が約5億円増えていたら増資額は最大10億円になります。この増資は新聞でもあまり詳細に報道されてないようですが、日経金融の記事によると、
振興銀、筆頭株主に木村剛氏——9月末、11%程度を保有
2004/10/07, 日経金融新聞3面
日本振興銀行の九月末の筆頭株主に社外取締役の木村剛氏が浮上したことが明らかになった。振興銀は四月の開業以降に八月、九月と二回に分けて第三者割当増資を実施し、引き受け先の一人だった木村氏が九月末時点で発行済み株式総数の一一%程度を保有した。
振興銀は「将来的に上場するまでは銀行経営に安定感を持たせるため、既存株主を中心に株式を割り当てる方針」としており、今回もその一環と説明している。
四月開業時の資本金は約二十五億円で、発行済み株式総数は四万九千六百株。木村氏は三%弱の保有比率で、株主順位で上位十位から外れていたという。株式額面は五万円で、八月と九月に増資した結果、九月末の発行済み株式総数は六万四千八百二十八株。資本金は二十八億六千七十万円になった。
十月半ばにはさらに木村氏個人と木村氏が社長を務めるKFiを相手に第三者割当増資をおこなう計画で、最終的には資本金で三十億円弱、資本準備金が五億円程度になる見通しだ。
とあるので、やはり増資額は10億円だったんじゃないかと思われます。
(どーでもいいですが、額面株式が廃止されて久しいのに、「額面」が5万円ってのもヘンな書き方ですね。)
改正商法では、日本振興銀行の定款に株式の譲渡制限の定めがあるので、株主以外の者に対する新株発行は、株主総会の特別決議だけではなく、取締役会で「新株の割当を受ける者」「株式の種類・数」についても決議されることが必要です。
どちらかというと、「取締役会だけでなく、株主総会の特別決議も必要となります」の方がいいでしょうね。
先に取締役会で決めてから株主総会にもかける必要があります。(商280条ノ5ノ2)
しかし、株主に対する新株発行は、授権枠内で取締役会の決議による新株発行が認められます。したがって、基本的には既存株主に対する増資が行われたものと認識しています。
ところで、木村氏は「株主の代理人」であり、既存株主の便益を保護する立場にあり、正常な業務が行われているか内部監査をする役割にあります。
この手の増資は、一般的に既存株主の財産が希薄化するものであり、企業が資金調達をする場合は増資以外の方法を充分考慮し選択するよう「株主の代理人」は主張しなければなりませんが、木村氏は本件増資を行うにあたってそのような主張をしましたか。
また、増資にあたって株主全員にレターを送付しましたか。
商280条ノ5ノ2第1項でいうところの、「株主以外ノ者ニ対シ発行」というのは、商法が非常に不親切な書き方でわかりにくいんですが、「現株主以外の者に対し」ということじゃなくて、「現株主にプロラタ(同比率)で新株を引き受けさせない場合には」という意味なんです。
ですから、現株主の「一部」に新株を引き受けさせる場合であっても、同条の規定により、株主総会の特別決議は必要。(取締役会だけじゃだめ。)
もし、株主総会招集通知(レター?)を送っていなかったとしたら、増資が無効になる可能性があります。(が、さすがに、そんな初歩的なミスはやってないと思いますが。)
第二百八十条ノ五ノ二
株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株主ハ新株ノ引受権ヲ有ス但シ株主以外ノ者ニ対シ発行スルコトヲ得ベキ株式ノ種類及数ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ(以下略)
取締役会でちゃんとした議論が行われたのかどうかは重要な論点ですが、銀行の場合、BIS規制上の自己資本増強が必要になったら、基本的には増資か劣後debtでの調達しかないわけで、これも(よっぽど独断で決めたりしてない限り)、実際には説明責任が果たせないということはなさそうです。
ちなみに、本件は、「取締役会社間の取引」(商265条。いわゆる利益相反取引)に該当しますので、木村氏分の増資については、木村氏を抜いた取締役たちで決議しないといけません。
(実体上はともかく、これも初歩的な話なので、少なくとも議事録上はそういう形の決議が行われた形になっているものと思われます。)
委員会等設置会社なので、新株発行の内容決定の権限を執行役に権限委譲している可能性もありますが、譲渡制限会社なので取締役会の権限として残してる可能性が高いのではと思います。執行役に権限委譲してる場合でも、商265条で取締役会でも(木村氏を抜いた)決議が必要かと思います。
ちなみに、委員会等設置会社の取締役は、正確に言うと、自分で「内部監査」をしなきゃいけないわけではなく(内部監査は「業務執行」の一部という性質があるので、どちらかというと「やってはいけない」方かも知れません。)、取締役会が「内部監査を含む内部統制の体制」を構築する義務を負っている(商法施行規則193条)、ということです。監査委員会のメンバーになると、より監査っぽいことをやらないといけませんが、それも監査委員としての監査であって内部監査とはちょっとちゃいます。監査委員でも指名監査委員(商法特例法第21条の10)は、ズカズカ現場に乗り込む権限があるわけですが、他の取締役は基本的に「監査」はせずに「監督」をするだけです。
8.社外取締役の責任免除条項について
日本振興銀行株式会社の全部謄本においては、以下の記載があります。
(社外取締役の会社に対する責任の制限に関する規定)
「会社は商法266条第19項の規定により、社外取締役との間に、同条第1項第5号の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度は、1000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額となる」(1月28日)
「当会社は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下、「特例法」という。)第21条の17第5項で準用する商法代266条第19項の規定により、社外取締役との間に、特例法第21条の17第1項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金1000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額となる。」(3月12日)
これらは、社外取締役に関する規定として一般的なものであり、通常の事業会社が内部監査の目的で社外取締役を起用する場合に利用されるものです。社外取締役の規定は諸種ありますが、基本的には取締役会に出席し、企業の経営そのものに関与しないのが通常です。当然、銀行内に部屋やデスク、秘書などを置かず、経営上問題とされる事項を書類などでチェックし、内部から監査することで初めて社外取締役として責任を制限されるものと認識しております。
これは「内部監査の目的で起用される場合」だけとは限りません。社外取締役は過去にその会社に勤務したことがないなど、商法上の要件を満たすかどうか(その他、独立性の要件があったほうがより望ましいですが)の話であって、部屋やデスクや秘書がいちゃいけないということは全くないです。
もちろん、社外取締役が「業務を執行」しちゃうというのは論外。
また、「経営姿勢」の観点からは、新興のベンチャー的金融機関の社外取締役に個室や専用秘書が必要かというと、ビミョーではありますね。
ところで、木村氏は例えば役員および従業員の人事に関することや、メモ書き、指示書、あるいは融資審査に関する会議に参加するなど、具体的に経営そのものに関与する、つまり社外取締役以外の業務に関与してきましたか。あるいは、具体的な融資先の選定や、人材の採用、会議の主催や定期的な参加をされてきましたか。事実上、人事や業務面での執行が認められた場合、社外取締役規定が無効となります。
当然、社外取締役である以上、専用室や専用秘書などは銀行費用では雇用されてないこととは思いますが、一部風評ではそのような事態を指摘されておりましたので、念のため。
取締役は、執行役の業務執行を「監督」しないといけないですし、(木村氏がそうかどうかは存じませんが)指名監査委員なら、むしろ会議にオブザーバーとして出席しないといけないでしょうね。また、「監査」というと、書類だけひっくり返してるイメージがあるのですが、監査の手法にも会議への出席や現場への立ち会い等のいろんな手法があります。
また、単なる「チェック」と違って、監査には「アドバイス機能」的な側面も存在するというのが監査論の基本です。
ただ、もちろん「具体的な融資先の選定や、人材の採用」をやってたとしたらそれはまずいですし、実質的に会社を切り盛りしたりするのはダメです。
・・・ということで、私、双方どちらの方の味方をするものでも批判するものでもございませんが、私の興味あるところについてだけ、ちょっとだけコメントさせていただきました。
(ではまた)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。