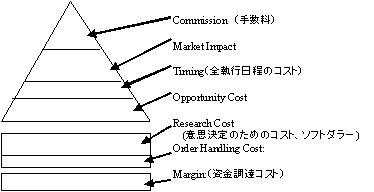先日のMSCBの議論の中で、47thさんから「会社法は、取引費用(transaction cost)を節約するための契約の雛形(standard from of contract)に過ぎない」という観点をいただきました。
会社法ではないですが、租税法の領域で同様の観点を持つ面白い論文を見つけましたので、ご紹介します。
租税回避の経済学:不完備契約としての租税法(渡辺 智之)
http://www.mof.go.jp/f-review/r69/r_69_153_168.pdf
要約:
経済活動のグローバル化や情報通信技術の発展などを背景にして,租税回避の問題が大きな注目を浴びるようになってきているが,租税回避に関する経済学的分析はまだほとんど行われていない。その結果,経済学においては,租税回避と脱税,あるいは租税回避と節税の区別すら必ずしも明確には行われてこなかったのではないだろうか。本稿は,「法と経済学」の成果を援用しつつ,租税回避の経済学的な位置付けとその社会厚生上の評価にとりかかろうとする試みである。
本稿ではまず,租税法の不完備な性格と納税者のインセンティブを考えると,租税回避は必然的に発生することを述べる。次に,租税回避を「否認されるかもしれないタックス・プラニング」と規定した上で,租税回避行動の簡単なモデルを提示する。その上で,租税回避が租税法の不完備性を補完する役割を持っていることを評価して,租税回避を根絶することは不可能なだけでなく,必ずしも望ましくないと主張する。一方,租税回避を納税者の最適化行動に委ねた場合には,租税回避が社会的に最適な程度を超えてしまう可能性が強いことから,何らかの租税回避抑制策が必要なことを述べるとともに,いくつかの具体的な抑制策とその効果について検討する。
契約理論等の基礎知識がなくても、文章としてスーッと読めますので、ご興味のある方はご一読を。
どのへんが面白いと思ったかというと
この論文でも、
一方,租税法は課税当局と納税者の間で結ばれる「契約」の内容を示したものであるという見方がある(Scholes et al.(2001);p.4)。但し,課税当局はこの「契約」の条件(租税法の内容)について,一般には個々の納税者と交渉することはなく,納税者が受け入れなければならない標準的な契約内容を租税法という形で提示する。
というように、法律というのは契約の「ひな型」なのだ、という考え方に立っているところが一つ。
また、「脱税」「節税」「租税回避」等の違いを、「経済学の立場から」検討しているところが2つめ。
法律論の立場からは、「脱税」は法律違反、「節税」は法律が予定するところに従って税負担の減少を図る行為であるのに対して、「租税回避」は法が予定しない異常な法形式を用いて税負担の減少を図る行為、というような説明が定着しているんじゃないかと思いますが、「脱税」だろうが「節税」だろうが、税負担の結果だけから見ると厚生経済学的観点からは同じじゃん?というような問題提起もなされた後、筆者は結局、
節税を「否認されないタックス・プラニング」,
租税回避を「否認されるかもしれないタックス・プラニング」
とする立場を採用されてます。
要は「リスク」という観点から節税と租税回避の違いを経済学に落とし込もうという試みですね。(ふむふむ。)
また、
租税法の不完備な性格と納税者のインセンティブを考えると,租税回避は必然的に発生する
とか、
まず,租税回避がゼロの状況が必ずしも社会的に望ましくないことを説明しよう。第一に,前節で議論したように,あらゆる場合に対する適用を明らかにするような租税法の文言を書くことは技術的に不可能であり,仮に,それを目指して,租税法を制定しようとすれば,租税法の文言は無限に長くなり,その制定・適用に伴う費用がどこまでも大きくなって,その費用が租税回避を根絶する便益を上回ってしまうであろう。第二に,本節の議論が示唆するように,仮に租税回避が全く行われなくなれば,租税法の不完備性は,そのまま存続し,租税法の適用に関する予見可能性の向上がもたらされない可能性がある。この意味で,ある種の租税回避は,租税法の不完備性を補完する役割を果たしてい
る可能性がある。即ち,租税回避という納税者の行動が,現行の租税法の不十分な点を浮き彫りにし,租税法の改善を促す契機になりうるのである。従って,租税回避が全く行われない状態が,社会的に望ましいとは必ずしも言えない。
というようなことをおっしゃってるのも、(税収を考えるべき)財務省財務総合政策研究所のフィナンシャル・レビューに掲載された論文だということを考えると面白いのではないかと。
つまり、租税回避というのを租税法に対する「ハッキング」と考えると、「ハッカーが存在することによって、システムのセキュリティレベルが向上するという面もあるんだよ」みたいなことを言っているようなもんでしょうか。
(これもまた「荒っぽい例え」なので、ツッコミどころ満載ですが。[笑])
MSCBの問題は不完備契約の問題か?
ちなみに、(この論文からは直接つながらないですが)、MSCBの問題は不完備契約の問題なんでしょうか、どうでしょうか?
法律として「不完備」だから、法が予定しない条件のCBが出てきちゃった、という見方もできないことはないと思いますが、私は、一般の人にはオプションバリューがピンと来ないという「限定合理性」的問題の側面が強いような気もします。
これも、以前申し上げたように、新聞社等が公共財的にオプションバリューを公表することにしても、そのコストは非常に小さいでしょうし、それによって、有利発行かどうか微妙な線上のものは、「取締役会での決定だけでなく、株主総会の特別決議を経ないとリスクありまっせ」、ということになって、そういう手続きをちゃんとを踏むか、または事実上発行できなくなるかのどちらかに明確に振り分けられるようになっていく気もします。
(ご参考まで。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。