先日のエントリのコメント欄でkazuhiro5384さんに教えていただいた、
東洋経済新報社 (2007/02)
売り上げランキング: 9142
が、Amazonから届いたので早速読み始めたら、大変面白くて最後まで一気に読了。
日本経済新聞社の一連の不祥事等を扱った本ということで、タイトルと表紙から、「(再販制とか記者クラブ制度とか)新聞業界のドロドロした現状の暴露本」的な本かなあと想像して読み始めたんですが、さにあらず。「コーポレートガバナンス」の本でした。
商法の歴史とか、コーポレートガバナンスに興味がある方には、お勧めです。
著者の大塚氏は、日経子会社の不正経理を株主総会で追及したことにより同社を懲戒解雇になり、法廷闘争の末、解雇が撤回され同社に復職。現在、日本経済研究センター主任研究員として、コーポレートガバナンスの研究に携わってらっしゃるそうです。
「日刊新聞法」についても、(ちょっと触れているだけかと思ったのですが)、かなりの分量を割いて説明されています。
ベンチャーでVCから資金調達して株式公開したりバイアウトしたりという、「アメリカ型資本主義一直線」の会社のコーポレートガバナンスについては、最近では世間でもだいぶ議論が深まってきているかと思います。一方、非公開会社で「利益だけが目的」とは割り切れず、別の(高尚な)目的も平行して追求しつつ、株式公開しないで長期に安定して「いい」会社として存続していく方法はないものかなあ?と模索している企業は、結構多いのであります。
(公開企業より、未公開企業のほうが1000倍くらい数が多いので、当たり前ではありますが。)
そうした企業にも、本書に書かれている日経新聞を中心とする新聞社のコーポレートガバナンスは、(反面教師として)ご参考になるのではないかと思います。
ということで、本書によって、新聞社の事業構造改革と「日刊新聞法」(1) (2)で考えてきた私の疑問も、おかげさまでかなり解決しました。
以下、戦前からの日刊新聞法の歴史について本書を頼りに紐解いていきたいと思います。(また、「通りすがりのもの」さん他のみなさんにいただいたコメントも、大変参考になります。ありがとうございます。)
−−−
本書では、
日本の商法は戦前と戦後で大きく変わった。GHQの意向を受け一九五〇年(昭和二十五年)に米国法制を導入した抜本的な改正が行われたからである。(中略)「株式の譲渡制限を認めない」というGHQの方針で、株式会社の株式は完全に自由に売買することにあった。改正前の商法では株式に譲渡制限を設けることを認めていたので、一八〇度の転換であった。(p34)
と、戦前からの商法の流れが説明されています。(なるほどなるほど。)
しかし、当時の新聞業界は過小資本で、多くの新聞社は株式の譲渡制限を設けていた。譲渡制限が禁止になると、新聞社が外部資本による買収の脅威に晒されるとの危機感が芽生えたのだ。新聞業界は商法改正が五〇年五月に成立すると、新聞業界だけに譲渡制限を残そうと動き出した。同年一一月に『朝日』、『読売』、『毎日』、『日経』の四社が全国の日刊紙に呼びかけ、今回の特殊指定と同様、政界への働きかけを始めた。(p35)
新聞社にだけ譲渡制限を認めさせることは、きわめて虫のいい話である。”新聞社横暴”という批判を避けることも必要で、政府提案の特例法を国会に提出させることは鼻から無理だった。となると、方法は一つしかない。議員立法である。(p164)
ということなわけですが、当時まだ占領下なので、国会だけでなくGHQを納得させる必要があるわけです。
元々、新聞社の株式譲渡制限は言論統制のために導入されたにもかかわらず、その事実を正直に話すとみもふたもない。そこで(略)「報道の自由」を持ち出すことにし、(略)、譲渡制限の必要性を強調したのだが、GHQのウェルシュ反トラスト課長はまったく関心を示さなかった。
時あたかも、朝鮮戦争とレッドパージの最中である。「報道の自由」が駄目だとわかると、共産主義への脅威を持ち出すことにした。
「日本の新聞社の特異性として著しく過小資本であり、(略)」
すると、ウェルシュ課長は、「『朝日新聞』の資本金はいくらと言ったのか」と問い直し、「約九万七〇〇〇ドル(注:3500万円)と答えると、「本当か」と信じられぬ顔つきだったという。その二日後、GHQは特例法制定に同意した。(p166)
「譲渡制限が言論統制のために導入された」というのはピンとこないかも知れませんが、どういうことかというと、
明治以降の新聞は、言論人が資本を出し、自らの主張を展開するものが多かった。言論人が持つ新聞の存在は戦時体制下の政府・軍部にとって言論統制上、望ましくない。(中略)
その一環として最初に手がけたのが通信社の一社統合だった。(略)次に狙ったのが新聞社の一社統合構想(一元的統制会社設立構想)だった。(中略)
この大統合構想に、『朝日』、『毎日』、『読売』の三紙が「全国に独立した新聞社は一社もなくなる」と猛反発し、新聞業界は大混乱になった。(中略)
田中理事長が四一年(昭和一六年)一一月二四日にまとめた裁定案は、�新聞社はすべて法人組織とし、株式、出資は役員を含む社内従業員だけが保有する社内株式保有制度にする(以下略)。
新聞社の社内株式保有制度はこのときに始まったのであり、新聞業界全体で七〇%あった社外資本は半年後にわずか七%に急減した。(p36)
ということです。
大塚氏の主張は、このように現在の新聞社の株式保有構造は、戦時下の言論統制で原型ができあがったものだからそれはすなわち悪いのだ、というニュアンスが感じ取れます。しかし、例えば、リクルート社なども、役員・従業員等で株式を保有し、上場を志向しないという意味では似たような構造だと思いますが、風通しのよい社風を形成されてらっしゃると思いますので、必ずしも、譲渡制限がついているとか、持株会が存在するからダメというわけではなく、その「運用」が問題ではないかと思います。一方で、新聞社の譲渡制限(ひいてはコーポレートガバナンス)に、そういった「血なまぐさい歴史」の影響があるのも確かなんでしょうね。
ということで、昭和26年に議案が審議されはじめるのですが、当初案は、
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、商法第二百四条の規定にかかわらず、株式の譲渡を禁止し、又は制限することができる。
前項の規定による株式の譲渡の禁止又は制限は、定款をもつて定めなければならない。
というものだったのが、さすがに「株式会社」なのに、譲渡を「禁止」して投下資本回収の機会を奪うのはまずかろうということで、法務委員会で、
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、商法第二百四条の規定にかかわらず、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者であつて取締役会が承認をしたものに限ることができる。
前項の規定による株式の譲渡の禁止又は制限は、定款をもつて定めなければならない。
という形に修正されて成立した、とのことです。
この後、昭和41年に、一般の株式会社も譲渡制限が認められることになったのと同時に、
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
と、現在の形になったようです。
つまり、このときに日刊新聞法では「取締役会が承認」という文言が取れて、譲渡の承認については商法に一元化し、商法の規定と「セットで」使うようになったとのことです。すなわち、現在の条文だと、形式上は「公開会社でも日刊新聞法を使える」というように読めますが、経緯を見ると、事業に関係のある者の間で自由に譲渡ができるようにしよう、なんて発想は、なかった模様。
また、このときに「既存の株主であっても、事業に関係なくなったら株主をやめないといけない」規定を定款に盛り込めるようになりました。
新聞界の要望は「定款または取締役会の決議により、株式の保有制限ないし株主の資格を制限することができる」というものだった。(中略)しかし、商法は買い手が気に入らなければ承認しないことを認めているのだから、新聞社が勝手に「事業関係者」の内規を作り、それに基づき承認か不承認か決めれば済む話なのだ。(中略)
結局、法務省は新聞業界の圧力に屈し、改正に応じたのだが、そこはしたたかだ。特例法から「取締役会の承認」を削除、代わりに(略:上記のような)文言を追加した。(p227)
以上の話を表に整理すると、以下のようになるんじゃないでしょうか。
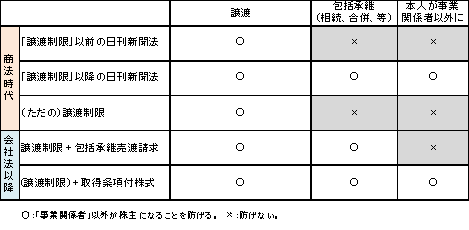
昭和41年に「譲渡制限」が商法に導入される前の日刊新聞法は、株主が死んで相続したり株主自身が「事業関係者」の要件を満たさなくなった場合には、その人から株を奪う方法は用意されていなかったが、昭和41年以降、そういう場合にも株を奪い取ることができるようになった。これは、かなり強力な規定です。
旧商法時代は、日刊新聞法以外でこれを実現する方法はなかったんじゃないかと思います。
ただ、売渡義務を課したところで、創業家の大株主が相続した場合に「株主やめて」とは言いづらいでしょうし、逆に、持分比率の非常に小さい従業員株主などが死んで相続しても大勢に影響ないでしょう。生きてる本人に「あんた株主やめて」というのも、よほど、条件をきちんと定義し説明もしっかりしてないと、トラブルの元かと思います。
結局、一般の会社に譲渡制限が認められるようになった昭和41年以降は、日刊新聞法の意味は半減したんじゃないかと思います。
さらに会社法施行以降、相続や合併など、包括承継によって株主になった人に売渡請求をできる制度ができました。さすがに生きてる株主本人に「あんた株主やめて」というのは、もう一ひねり必要ですが、「事業関係者でなくなった」ことを取得条件とする取得条項付株式を使えばうまくスキームが組める気もします。
ということで、やはり、会社法施行以降、日刊新聞法を特別法として置いておく意味は、ほとんどないのではないかと思います。
株主を関係者に限ったり、持株会を作ること自体は悪くないはずなので、著者の大塚氏も指摘されてますが、大事なのは、譲渡や運用方法に関する規定をきちっと整備し、社員株主などにもその規定をしっかり認識させ、必要であれば契約書等に合意内容を残すとか、そうした規定にcomplyした運用を行うことじゃないでしょうか。
日刊新聞法を利用している新聞社各社におかれましては、会社法施行を契機に、株式保有構造を含めたコーポレートガバナンスをきちっとした建付けの体制に生まれ変わらせるのがよろしいんじゃないかと思います。
(ではまた。)
[PR]
メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):
「note」でのお申し込みはこちらから。








http://hecacon.blog92.fc2.com/blog-entry-119.html
ã?¤ã??ã??æ¤?ç´¢ï??YSTï??ã??ã?¤ã??ã??ã??ã?¯ã??ï??ã?¢ã??ã?´ã?ªã?ºã??ã??æ?´æ?°é?…
【本】新聞の時代錯誤
新聞の時代錯誤—朽ちる第四権力
大塚 将司 東洋経済新報社 2007/3
日経が、大塚さんを訴えましたね。本書は、その元日経記者によるコーポレー…