ベンチャー企業が投資家から出資を受ける際の「交渉」がどのようなものなのかについて、その実態はほとんど知られていない。本連載では先月号まで2回にわたり、スタートしたばかりのあなたの会社「A株式会社」を例に、資金調達に取り組むベンチャーの姿を追ってきた。引き続き今月は、A社と投資家とで繰り広げられるハードな交渉の詳細を見ていくことにしたい。こうした投資家との交渉ノウハウは起業家や起業予備軍必須の知識である。
さて、A社のメンバーは、外資系や金融機関系など、さまざまなカテゴリーのVCを精力的に訪問した。まずは金融機関系のVCを何社かまわったが、担当者レベルの反応が悪く話が先に進まなかった。その後も金融機関系のVCではいずれも最終意思決定者に会えなかった。A社の力不足も否めないが、足を運んだ金融機関系VCは、1999年から2000年初めにかけての国内外IT系企業への投資でかなりの損を重ねており、「アツモノに懲りている」という印象だった。
また、外資系のVCでは投資条件で合意できなかった。A社の事業に対する理解度は高いと感じたし、興味も持ってくれたのだが、面談した外資系VCもインターネットブーム期の投資で痛手を負っているようで、日本からの撤退を準備しているVCもあった。米国のいわゆるITバブル崩壊の影響は大きいようだ。
さらに、何人かのエンジェルと呼ばれる人にも会ってみた。感触のいい人からは「君たちの事業はよくわからないが、金は出せるかもしれないよ」といった反応が得られた。しかし、株主になってもらう人には自分たちの事業への理解が欠かせないと考えるA社のメンバーには、こうしたエンジェルからの出資は受け入れられなかった。
結局、スタートアップ企業への投資を中心に手掛ける独立系のVCに資金を出してもらうことに決めた。ここでは名前を「Bファンド」としよう。Bファンドは数人で運営している小規模なVCで話が進むのも早かった。Bファンドのパートナー(*)はA社が取り組もうとしている分野に太い人脈を持ち、取引先の紹介など資金以外のメリットも期待できる。このことがA社の意思を固めさせた。
●ハードなネゴシエーション
ベンチャーと投資家の交渉は、どのように行われるのだろうか。引き続きA社を例に見ていこう。まずA社は、Bファンドのスタッフの前で自分たちのビジネスプランのプレゼンテーションを行った。A社メンバーは、それまでにも10社以上のVCでプレゼンを行ってきたこともあり、「前フリで相手をぐっと引き込んで」「ここでドンと盛り上げて」と、プレゼンのコツは完全に身に付けていた。A社が手掛けるビジネスに詳しいBファンドのメンバーは、A社が売り込みたいポイントをすばやく理解して、うなずいたり「ほう」という表情をしたりしていた。ミュージシャンが観客のノリがいいといい演奏ができるように、プレゼンテーションでも聞き手が理解して聞いてくれるといいプレゼンができるものだ。今回は、A社メンバーは自分たちの力を出し切った最高のプレゼンができたと思った。
しかし、投資家との交渉においてはプレゼンテーションの反応が好かったからといって安心してはいけない。A社の場合も、喜んだのもつかの間、プレゼン終了後にVCから嵐のような質問が待っていた。業界に詳しいだけに、ツボを突いた質問が次々に襲ってくる。他のVCでは適当にごまかしたあまり触れられたくないポイントについても、見逃さずに鋭く切り込んでくる。こうしてハードな交渉を重ねた結果、A社が当初持ち込んだビジネスプランはかなり修正されることになった。当初のビジネスプランでは、投資はなるべく控えてできるだけ早く損益分岐点(*)に持って行き、人員も少人数のままゆっくり着実に成長していこうと考えていたが、Bファンドのパートナーに「このままでは投資できない」と言われたのである。A社の取り組もうとしている事業は、業界の注目度が高く競争も激しいため、のんびり成長していたのでは競合企業に追い抜かれてしまう。思い切って社員数を増やし、より高い売り上げ目標を達成できる計画でなければ、投資はできないというわけだ。
しかし、Bファンドの言うことを鵜呑みにして、できないことを約束するわけにはいかない。A社メンバーがこの宿題を会社に持ち帰って議論を繰り返した結果、Bファンドが紹介してくれるという大手企業との提携など、新たな営業上の施策が実現すればより高い目標が達成できそうだという強い確信が得られた。このため、これらを修正した新しいビジネスプランに変更することで、両者は合意に至った。
今回の事例のように、投資家とこのようにハードな交渉をして、その過程でビジネスモデルを変更することは、日本ではまだ多いとはいえないが、シリコンバレーでは少なくない。
●ベンチャーの資本政策
A社の場合、この変更は資本政策面からもプラスだった。資本政策というのは「どのような株主に、いくらの株価で、何株の株式を割り当てるか」という計画である。当面、資金の心配をせずに、まとまった開発やプロモーションを行っていくには、5,000万円くらいの資金があるとありがたい。一方、IPO(株式公開)まで考えた場合、現時点での外部株主の持株比率は、どうしても全体の3分の1以下に抑えたい。そこから逆算すると、5,000万円の外部資金を入れるにはA社の現在の企業価値が1.5億円はないと厳しい。(*)当初の事業計画ではこれに届かない。
日本で株式を公開する際は、社長をはじめとする安定株主の持株比率が高いことが求められる。逆に、キャピタルゲインを狙っているVCのような外部の投資家は安定株主とみなされず、あまり高い持株比率になることができない。日本の株式市場は、特にベンチャーなどの小型株の取引について、米国に比べて一般投資家の参加が少ないために流動性が低い(取引量が少ない)。このため、もしVCが大量に株式を持っていた場合、公開後に大株主であるVCが株を売りに出すと、その大量の株式の引き取り手が少ないため、株価が下落すると考えられている。米国では、未公開の段階でVCが高い持株比率であっても、公開後にVCから徐々にバトンタッチして株を譲り受ける存在として、機関投資家(投資信託や年金などを運用する主体)の役割が大きい。しかし日本では、そうした機関がベンチャーの株式を吸収する機能が弱いので、ちょっと株が放出されると株価が崩れる可能性が出てくるわけだ。
株式公開時は、VCの機能を持つ証券会社が株式を引き受けて、自社の顧客にその株式を割り当てて(販売して)いくが、証券会社としても自社の売った株の値段が下がって自分の顧客に損をさせるのは非常に困る。そのため、安定した株価の形成を望む証券会社からは「社長が筆頭株主でないと……」「やはり会社の役員が5割以上株式を持っていたほうが……」といった発言が出てくることになる。こうした状況は、これから証券市場が発達していけば徐々に解消されてくるはずだが、残念ながら当面は社内役員など安定株主の持株比率が高い会社でないと公開が難しい現状が続きそうだ。このため、A社が未公開の段階であと1回発行済株式総数の10パーセント強の資金調達を行い、株式公開時にさらに10パーセント程度の株式を放出すると考えたとき、現時点で全株式の3分の2くらいは創業メンバーで持っておきたいのである。(「図表1参照)
図表1.資本政策の一例
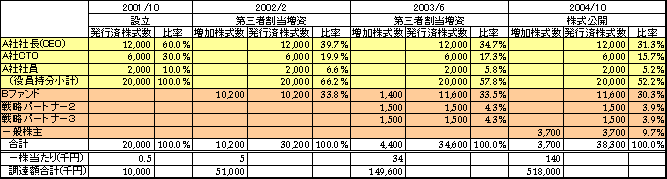
次回からは、ビジネスプランに大筋で合意したA社とBファンドが、どのようなLOIを締結し、最終的にA社がどのような金額の投資を受けることになったかについて見ていこう。
※A社ならびにBファンドその他の投資家に関連する部分のストーリーは記事のために作った例であり、実在の企業・団体等とは関係ありません。
「損益分岐点」…収益と費用が同じになる操業レベル。
「企業評価1.5億円」=5千万円÷(1/3)
5千万円が3分の1だとすると、全体の企業価値は1.5億円必要、となる。
「パートナー」
米国のVCは、従来、出資者であり経営者であるパートナーが運営するpartnershipとよばれる日本の組合や合名会社に似た無限責任の組織形態がファンドを運営することが多かった。現在ではアメリカのVCも有限責任の「LLC (Limited Liability Company) 」と呼ばれる組織形態をとることが多くなったし、日本でも株式会社形態をとることも多いが、最近設立されたVCの中には代表者について「パートナー」という呼称を取るところがあるため、この例ではパートナーという呼称をとった。
Isozaki, Tetsuya 磯崎哲也
磯崎哲也事務所代表/公認会計士
コンサルファームで、新規事業コンサル、インターネット技術調査などに従事した後、オンライン証券ベンチャーの設立に参画。その後、投資ファンドのパートナーやCFOなどとして、多数のベンチャー企業の現場に関与。2001年7月より現職。
https://www.tez.com/
