先月号では、「A株式会社」が、ベンチャーキャピタル「Bファンド」とのハードなネゴを乗りきり、なんとか投資の口頭での確約(ソフト・コミット)を取り付けるところまで行った。ただし、A社が当初考えていたビジネスの展開は「のんびり成長しすぎ」ということをBファンドに指摘され、実現可能性を検討した上で、より思い切った投資をするビジネスプランに改められた。この修正されたビジネスプラン(抜粋)を見てみよう。(図表1参照)
図表1.A社の企業価値
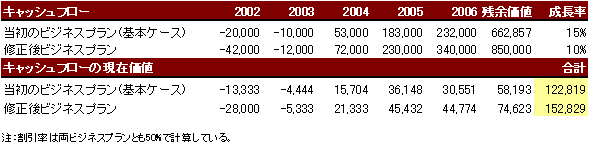
前回のビジネスプランでは、当初の投資金額を抑えていたため、当初のキャッシュフローのマイナスが少なかったが、今回は、かなり思い切って投資することにしているため、その分、2002年度・2003年度のキャッシュフローのマイナス幅は大きくなっている。しかし、2004年度以降のキャッシュフローは当初案よりも勢いよく増加していくプランになっている。
●「企業価値」の最終決定
2001年12月号でも述べたが、DCF法で現在価値を算出する場合の基本的な考え方は、数式1の通りになる。毎年のキャッシュフロー(Ci)を、一定の割引率(r)で割り引く、というものだ。しかし、実際のビジネスプランにおいては、無限にキャッシュフローを想定しても意味はない。特に、変化の激しいIT系の事業においては来年のこともよくわからないのに、10年も先のキャッシュフローを考えてもほとんど意味がないのは明らかだ。
数式1:
このため、実際には、5年後くらいに事業を売却してそこでキャッシュが入ってくるとみなして企業価値を計算することが多い。この事業を売却したとみなしたときの企業価値を「残余価値(terminal value)」と呼ぶ。残余価値も企業価値であるから、その計算方法にはいろんな考え方があるが、今回の場合、計画の最終年度のキャッシュフローが一定の率で成長していくとして、DCF法と同様の考え方で計算した。(こうすると、最終年度のキャッシュフローを「割引率−成長率」で割るというシンプルな式で表せる。数式2参照。) A社案では、当初この最終年度以降のキャッシュフローの増加率を15%としていたが、Bファンドからこれは高すぎだと指摘されて10%に削られることになった。
数式2:
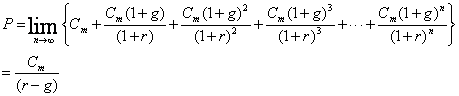
注:Cmは、最終年度のキャッシュフローrは、割引率。gは最終年度以降のキャッシュフローの成長率。
毎年のキャッシュフローを割引く割引率としては、50%が使われた。これは、現在の金利水準より相当高い、かなりリスクを見込んだ率である。A社は、スタートアップしたばかりで現在はまだサービスも開始していないので、本当に計画通りいくのかどうかリスクが高い、と言われればその通りではある。悔しければ、何らかの形で自分たちで資金を工面して、より企業としての実態を作ってからVC(ベンチャーキャピタル)に話を持ち込むしかない。
しかし、A社スタッフの場合、そもそも、お金持ちの叔父さんがいるわけでも自分たちが何千万円も貯金があるわけでもないのでVC回りをしてきたわけである。しかし、数年前まではスタートアップの企業に資金を提供するVCなど日本にはなかったし、出しても「額面」での投資がほとんどで、とても1億円以上の評価をしてくれるような土壌はなかった。ITバブル崩壊などと言われて投資が過度に冷え込んでいる現在の環境をも考え合わせれば、これでもかなり好条件とも言える。また、Bファンドが、中身もわからずただ企業価値のディスカウントをネゴってくるVCだったとしたら、A社スタッフも、自分の会社を安く見られたという寂しさや悔しさが残ったかも知れないが、Bファンドの態度は一貫して、理由を示しながら条件を提示し、「いっしょに経営をしていこう」というポジティブな意欲の感じられるものだった。このため、A社スタッフも多少不満な面があっても最終的には説得されることとなった。
実は、ベンチャーファンド自体も、通常、自己資金はほんの一部で、大半は投資家から集めてきた資金である。ファンドの運営をやっている会社(「GP」(=General Partnerの略)などと呼ばれる)が投資を決める際には、自分の直感やセンスも重要ではあるが、ファンドに出資してくれた投資家への説明責任(accountability)も欠かすことができない。つまり、ファンド運営者の場合、ファンドへの出資者に説明できない行動は取れないし、取ってはならないのだ。だから、VCがこちらに好感を持ってくれているなとは思っても、それで交渉が甘くなるということはなく、条件はあくまで合理的に決まると考えておいたほうがいいだろう。
●「LOI」を締結!
投資を受けるときに注意が必要なのは、企業価値には、投資を受ける前の価値(pre-money)と、投資を受けた後の価値(post-money)がある、ということだ。「投資を受けた後の価値」=「投資を受ける前の価値」+「投資金額」である。図表1でBファンドが投資をするといった修正後の1.5億円は「post」の価値だ。5千万円投資を受けるとすると、preでは約1億円の企業評価になる。
A社スタッフは、当初、なるべく外部株主比率を下げたいという思いから、pre1.5億円で評価して、約5000万円投資して25%の出資比率でどうか、と食い下がっていた。しかし、Bファンド側は、今回のビジネスプランは、Bファンド側も大口の取引先を紹介するなど、出資以外のバリューをつける「共同経営者」的な協力をすることや、約5000万円の投資をすることによってはじめてこのビジネスプランが可能になることなどから、あくまで投資「後」で1.5億円の価値であると主張した。最終的には、修正したビジネスプランに基づき、投資後の企業価値1.53億円と見て、投資後の発行済株式の約34%、5100万円を出資してもらうことになった。
もちろん、この5100万円だけでIPOまで資金を持たすというのはかなりきつい。Bファンドのパートナーは、これからの事業の進捗を見て、追加投資を考えよう、と言ってくれた。「この目標を達成したら次の投資」と、事業計画上の目標(マイルストーン)を定めて、小分けで投資を行っていく、いわゆる「マイルストーン投資」というやつだ。Bファンドとのディスカッションであがった課題の一つは、A社が技術には絶対の自信を持つ技術者集団ではあるが、財務やマーケティングの経験を持つ担当者が一人もいない、ということだ。そこでBファンドから設定された目標は、この業界で活躍できる実力あるマーケティング担当者を連れてくること、営業が軌道にのってきたら、IPOまで引っ張って行ける専任の財務担当者を連れてくることだった。もちろん、売上高や顧客数の目標を達成することも盛り込まれている。
こうしたマイルストーン投資はA社スタッフ側にとってもありがたい。もし、A社が順調に成長していくとすれば、後になればなるほど企業価値はあがるはずだ。体制が整わない段階で大量の資金を投入してしまうと、株式の持分を大量に外部株主に放出しなければならないが、成長に合わせて資金調達ができれば、こうした持株比率のバランスをうまくとりながら資金調達が行えることになる。
最終的に、BファンドはA社に、こうした内容を記入したLOIを手渡した。
●LOIの内容は?
では、そのLOIの内容はどんなものだったのだろうか?まず、このLOIは守秘義務などの条項を除いて法的拘束力がない(non-bindingである)ことが定められている。つまり、投資するかどうかはこの後詳細にA社の内容を見るデューデリジェンスの結果を見てから決めるということである。また、ディスカッションの結果決まった投資金額、発行株式数、などの条件も書かれている。
さらに重要な点としては、EXITの目標が定められたことがある。今回は、A社は、IPOに向けて最大限努力することがうたわれた。
経営としては必ずしも不調ではないがIPOもバイアウトもしないという状況を、投資関係者は「living dead(生ける屍)」と呼んで敬遠する。会社の経営者や従業員は、毎月食っていければそれでいいとも言えるが、投資家は資金がキャピタルゲイン付きで返ってくるのでなければ投資した意味がない。実は、この2つの状態には大きな隔たりがあり、会社側と投資家で大きく利害が分かれるところだ。この条件はBファンドの強い希望によって盛り込まれた。
この他にも、先買権(pre-emptive rights)や、共同売却権(co-sale right)、希薄化防止(anti-dilution)清算時の残余財産分配の優先権(liquidation preference)などという、A社メンバーが聞きなれない条項が付けられた。これらの条件は、日本の今までの投資慣行ではあまり盛り込まれなかった条件であり注意が必要であるため、次回以降じっくり見ていくことにしよう。
※A社ならびにBファンド、その他の投資家に関連する部分のストーリーは記事のために作った例であり、実在の企業・団体などとは関係ありません。
Isozaki, Tetsuya 磯崎哲也
磯崎哲也事務所代表/公認会計士
コンサルファームで、新規事業コンサル、インターネット技術調査などに従事した後、オンライン証券ベンチャーの設立に参画。その後、投資ファンドのパートナーやCFOなどとして、多数のベンチャー企業の現場に関与。2001年7月より現職。
https://www.tez.com/
